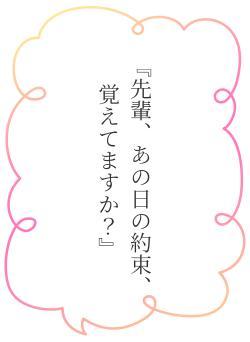悠真は、自分でも驚くくらい穏やかだった。
福岡の町並みは何も変わらないのに、どこか違って見える。
川沿いの道も、何度も通った本屋も、
今は全部、澪と見た景色になっていた。
---
夜、自分の部屋でベッドに寝転びながら、悠真はスマホを見ていた。
澪が撮ってくれた何枚かの写真。
笑ってる顔、驚いた顔、真剣に本を読んでる横顔。
そのひとつひとつに、心がふわりとほどけていく。
(俺、こんなふうに誰かに惹かれること……もう、ないと思ってたんだけどな)
---
母が亡くなってから、悠真の世界は止まっていた。
誰かと深く関わることも、気持ちを話すことも怖かった。
「また、大切な人を失うくらいなら、最初から誰とも関わらない方がいい」って、そう思ってた。
でも、澪は違った。
最初は、どこか透明で、今にも消えてしまいそうな空気をまとってた。
けど、何度か会ううちに、少しずつ色が変わっていくのがわかった。
笑ったり、驚いたり、時々黙り込んだり――
その全部が、ちゃんと“生きてる”って感じさせてくれた。
---
(澪が福岡に来てくれて、本当に良かった)
(この町が、俺にとっても新しくなった気がする)
---
次の日、悠真は澪と待ち合わせをして、少しだけ遠くの町まで出かけた。
電車で20分、澪が読み込んだ小説の“舞台”のモデルになった街だ。
「ここ……見たことある。小説に出てきた場所と、そっくり……」
目を輝かせる澪を見て、悠真は自然に微笑んだ。
「ほら、ここ。このカフェがモデルになったって、作家が昔のインタビューで言ってた」
「……すごい。ほんとにあるんだ、物語の中の場所が」
澪は店の前で立ち止まり、静かに深呼吸した。
「生きててよかった」――ぽつりと、そうつぶやいた。
---
“澪が生きてるって感じてくれる町なら、
この町が、俺の一番好きな場所であってほしい。”
---
帰り道、夕焼けの中で悠真は言った。
「澪が福岡にいるなら、俺……この町がもっと好きになる気がする」
「だから、これからも一緒にいてほしい」
その言葉に、澪は何も言わず、ただうなずいた。
言葉がいらないほど、心があたたかくて、涙がにじんでいた。
---
“福岡は、死ににきた場所じゃなくて、
生きたいって思える場所になった。”