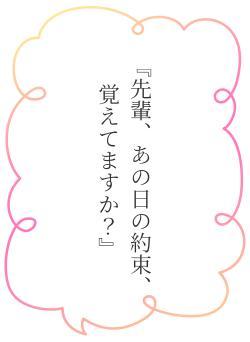夏休み目前。
生徒たちの制服が少しずつ夏服に移り変わっていくころ、
私は放課後の図書室で、日課の整理をしていた。
「……よう、まだいたの?」
顔を上げると、入口に立っていたのは高瀬くんだった。
「忘れ物、取りに来ただけ」
そう言いながら、彼は棚に寄って数冊の本を眺める。
その手元を見た私は、思わず声を出した。
「それ、全部小説だよ」
「だよな。……でも、おまえが読んでるのって、こういうのだろ?」
どこか気まずそうに笑った顔に、胸の奥がきゅっとなる。
その日の帰り道、たまたま彼と駅までの道が一緒になった。
「……ねぇ、高瀬くんって、普段どんな本読むの?」
「本? ほとんど読まねーよ。野球漬けの毎日だし」
「じゃあ、なんでさっきの?」
「……あー、それは、その」
しばらく沈黙のあと、彼は小さく口にした。
「おまえと話したいから、ちょっと頑張ってみた」
心臓が跳ねた。
不意に、胸の奥に灯がともるような感覚が広がる。
「……じゃあさ」
そう言って、高瀬くんが少し照れたように笑った。
「今日は、一緒に帰ろう?」
頷いた私は、彼と並んで歩き出した。
夏の夕陽が落ちかけた道を、ゆっくり歩いていく。
ほとんど話さなかったけれど、沈黙は心地よかった。
やがて訪れた分かれ道。
「じゃあ、またね」と手を振って、私はひとり歩き出す。
その数秒後だった。
「……おい、待って!」
後ろから走ってくる足音に振り返ると、
高瀬くんが息を切らしながら近づいてくる。
「ど、どうしたの?」
聞き終えるよりも早く、彼の手が私の腕をつかんだ。
「……おれ、ずっと言いたかった」
夕暮れの光の中、真剣な目で見つめられる。
鼓動が早くなって、呼吸の仕方を忘れそうになる。
「おれと付き合って」
その言葉は、まっすぐで、不器用で、あたたかかった。
私はしばらく黙ったまま、彼を見つめ、
そして、そっと頷いた。
「……うん」
だけど。
「これ、秘密にしてていい?」
そのあとの私の言葉に、彼はほんの少しだけ目を見開いて、
すぐに、ふっと息を抜いた。
「いいよ。誰にも言わない。俺たちだけの秘密な」
こうして、ふたりの“秘密の交際”が始まった。
誰にも言えない関係。
それでも、夏が来るのが少し楽しみになる──そんな日々の始まりだった。
生徒たちの制服が少しずつ夏服に移り変わっていくころ、
私は放課後の図書室で、日課の整理をしていた。
「……よう、まだいたの?」
顔を上げると、入口に立っていたのは高瀬くんだった。
「忘れ物、取りに来ただけ」
そう言いながら、彼は棚に寄って数冊の本を眺める。
その手元を見た私は、思わず声を出した。
「それ、全部小説だよ」
「だよな。……でも、おまえが読んでるのって、こういうのだろ?」
どこか気まずそうに笑った顔に、胸の奥がきゅっとなる。
その日の帰り道、たまたま彼と駅までの道が一緒になった。
「……ねぇ、高瀬くんって、普段どんな本読むの?」
「本? ほとんど読まねーよ。野球漬けの毎日だし」
「じゃあ、なんでさっきの?」
「……あー、それは、その」
しばらく沈黙のあと、彼は小さく口にした。
「おまえと話したいから、ちょっと頑張ってみた」
心臓が跳ねた。
不意に、胸の奥に灯がともるような感覚が広がる。
「……じゃあさ」
そう言って、高瀬くんが少し照れたように笑った。
「今日は、一緒に帰ろう?」
頷いた私は、彼と並んで歩き出した。
夏の夕陽が落ちかけた道を、ゆっくり歩いていく。
ほとんど話さなかったけれど、沈黙は心地よかった。
やがて訪れた分かれ道。
「じゃあ、またね」と手を振って、私はひとり歩き出す。
その数秒後だった。
「……おい、待って!」
後ろから走ってくる足音に振り返ると、
高瀬くんが息を切らしながら近づいてくる。
「ど、どうしたの?」
聞き終えるよりも早く、彼の手が私の腕をつかんだ。
「……おれ、ずっと言いたかった」
夕暮れの光の中、真剣な目で見つめられる。
鼓動が早くなって、呼吸の仕方を忘れそうになる。
「おれと付き合って」
その言葉は、まっすぐで、不器用で、あたたかかった。
私はしばらく黙ったまま、彼を見つめ、
そして、そっと頷いた。
「……うん」
だけど。
「これ、秘密にしてていい?」
そのあとの私の言葉に、彼はほんの少しだけ目を見開いて、
すぐに、ふっと息を抜いた。
「いいよ。誰にも言わない。俺たちだけの秘密な」
こうして、ふたりの“秘密の交際”が始まった。
誰にも言えない関係。
それでも、夏が来るのが少し楽しみになる──そんな日々の始まりだった。