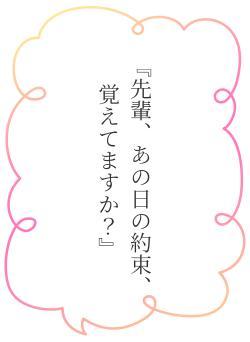それから、私たちの間には──
“秘密を知っている者同士”だけが共有できる、特別な静けさが生まれた。
音楽室の前を通るたびに、私は無意識に足を止めるようになっていた。
それはまるで、呼ばれているような感覚だった。
そんなある日。
扉の隙間から、あの日と同じ旋律が、ふわりとこぼれ出ていた。
「……やっぱり、おまえか」
弾き終えた彼が振り向き、私と目が合った。
けれどもう、驚きも動揺もなかった。
「……黙っててくれて、ありがとな」
彼は照れたように言って、そばに置いてあった椅子を少し引いた。
迷った末に私は、その椅子にそっと腰を下ろした。
沈黙を破ったのは、彼の方だった。
「この前のノートの話だけど──」
「えっ……」
「ほんとに、いいと思ったんだよ。おまえの言葉」
頬が、かぁっと熱くなる。
「……ありがとう」
彼の手元に目を向けると、白くて長い指が鍵盤をなぞっていた。
ごつごつした野球の手だと思っていたのに、その動きはどこまでも繊細だった。
「ピアノ、いつから?」
「小さい頃から。……でも、皆にはナイショだけどな」
そう言って笑うその横顔が、少しだけ切なげで、私は目を逸らした。
「……なんか、落ち着くんだ。音も、おまえの小説の言葉も」
それが、初めてだった。
誰かが“私の好き”を、ちゃんと見てくれた瞬間だった。
──放課後の音。
それは、ピアノの旋律と、心に響く静かな言葉。
ふたりの距離は、まだ曖昧なまま。
けれど確かに、少しずつ、近づいていた。
“秘密を知っている者同士”だけが共有できる、特別な静けさが生まれた。
音楽室の前を通るたびに、私は無意識に足を止めるようになっていた。
それはまるで、呼ばれているような感覚だった。
そんなある日。
扉の隙間から、あの日と同じ旋律が、ふわりとこぼれ出ていた。
「……やっぱり、おまえか」
弾き終えた彼が振り向き、私と目が合った。
けれどもう、驚きも動揺もなかった。
「……黙っててくれて、ありがとな」
彼は照れたように言って、そばに置いてあった椅子を少し引いた。
迷った末に私は、その椅子にそっと腰を下ろした。
沈黙を破ったのは、彼の方だった。
「この前のノートの話だけど──」
「えっ……」
「ほんとに、いいと思ったんだよ。おまえの言葉」
頬が、かぁっと熱くなる。
「……ありがとう」
彼の手元に目を向けると、白くて長い指が鍵盤をなぞっていた。
ごつごつした野球の手だと思っていたのに、その動きはどこまでも繊細だった。
「ピアノ、いつから?」
「小さい頃から。……でも、皆にはナイショだけどな」
そう言って笑うその横顔が、少しだけ切なげで、私は目を逸らした。
「……なんか、落ち着くんだ。音も、おまえの小説の言葉も」
それが、初めてだった。
誰かが“私の好き”を、ちゃんと見てくれた瞬間だった。
──放課後の音。
それは、ピアノの旋律と、心に響く静かな言葉。
ふたりの距離は、まだ曖昧なまま。
けれど確かに、少しずつ、近づいていた。