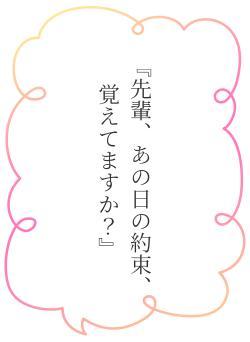風見ヶ丘高校、2年生になって最初の春。
同じクラスになった生徒の名前を、私はほとんど覚えていなかった。
廊下ですれ違っても話すことのない子ばかりで、毎年、それは変わらなかった。
ただ、ひとりだけ――彼の名前だけは、自然と耳に残った。
高瀬大翔。
野球部のエースで、誰にでも明るく話しかける、クラスの中心にいるような存在。
私とは、まるで違う世界の人。
だからこそ、目が合うことなんてないと思っていた。
その日も私は、いつもと同じように図書室に向かっていた。
ホームルームが終わるとすぐに鞄を持ち、誰にも話しかけられないように、足早に教室を出る。
図書室は3階のいちばん奥にある。
廊下の突き当たりに、静けさを閉じ込めたようなその空間が、私は好きだった。
けれど――その日は、途中で足を止めてしまった。
上の階から、ふと聞こえてきたのは、微かに響くピアノの音。
4階の音楽室。いつもは放課後に誰も使っていないはずの場所から、綺麗な旋律が降ってきた。
音に引き寄せられるように、私は階段をのぼった。
――そして、見てしまった。
真剣な顔で鍵盤に指を落とす、高瀬大翔の姿を。
え?
一瞬、頭が真っ白になった。
運動部の彼が、ピアノを弾いているなんて、まったく想像できなかった。
しかも、その音は、とても綺麗で、やさしくて――思わず息を呑んでしまった。
ドアの小さなガラス越しに、私は立ちすくむ。
すると、大翔がふいに顔を上げた。
目が合った。
思わず視線をそらしかけた私に、彼はゆっくりとドアを開けた。
「……見た?」
私は小さく頷く。
「誰にも言うなよ」
その声は、いつもの教室で聞く明るさではなくて、
少しだけ不安そうで、少しだけ、頼るような響きがあった。
「……うん」
私は、それだけを口にして、その場を離れた。
けれど、胸の奥には静かなざわめきが残っていた。
“本当の彼を知ってしまった気がする”
それが、私、香月紬と高瀬大翔のはじまりだった。
音楽室の出来事以来、私は彼のことが少しだけ気になるようになっていた。
でも、あの日のことには触れられることもなく、私たちはただの“クラスメイト”として、静かに日々を過ごしていた。
……はずだった。
「なあ、これどこに出せばいいんだっけ?」
そう言って、教室の隅で本を読んでいた私に、唐突に声をかけてきたのが高瀬くんだった。
彼は環境委員で、私は図書委員。直接関わることなんてほとんどないはずなのに、不思議だった。
「えっと……それは、分別の貼り紙に──」
そう言いかけた私の手元を、彼はふと見下ろした。
ノートの上に、学校とは関係ない小さな物語の文字が並んでいる。
「……それ、なに書いてんの?」
そう聞かれて、私は思わずノートを閉じた。
誰にも見せたことのない、“もうひとりのわたし”を、彼に見られた気がして。
放課後の図書室。
今日も、静かな空気の中で私はペンを走らせていた。
図書委員の仕事を終えたあとの、ほんのひととき。
この時間だけが、私が“わたし”でいられる、大切な居場所。
──カツ、カツ。
足音に顔を上げると、そこには見慣れた姿が立っていた。
「……高瀬くん?」
「あー……やっぱ、おまえだった」
彼は、手に私のノートを持っていた。
慌てて立ち上がろうとしたけれど、もう遅かった。
「ちょっと、それ返して──!」
「ん? “風のない夕暮れに、きみの声だけが響いていた”……」
ぱら、とページをめくる彼の指が止まる。
「……これ、おまえが書いたの?」
「っ、それ……違う。授業の……メモで……」
苦しい言い訳だった。
彼はふっと笑って、ノートを閉じた。
「へぇ、意外。……でも、こういうの、いいと思うよ」
「……誰にも言わないで」
「んー……どうしよっかな」
からかうような笑みが口元に浮かぶ。
「……あの日のこと。音楽室で、おれがピアノ弾いてたの、見たよな?」
「……うん」
「じゃあ、こうしよう。おまえがそれ黙っててくれるなら──
このノートのことも、誰にも言わない。……交換条件な」
彼はそう言って、ノートを私の手にそっと戻した。
「秘密、ひとつずつ。……これでおあいこだな?」
「……ずるい」
「よく言われる」
目が合った瞬間、どこかくすぐったいような沈黙が生まれた。
音楽室の出来事も、このノートの中の言葉も、
まだ誰にも知られたくない、小さな“わたし”だった。
けれど彼は、それを奪わなかった。
ただ、そっと心の隣に置いただけだった。
同じクラスになった生徒の名前を、私はほとんど覚えていなかった。
廊下ですれ違っても話すことのない子ばかりで、毎年、それは変わらなかった。
ただ、ひとりだけ――彼の名前だけは、自然と耳に残った。
高瀬大翔。
野球部のエースで、誰にでも明るく話しかける、クラスの中心にいるような存在。
私とは、まるで違う世界の人。
だからこそ、目が合うことなんてないと思っていた。
その日も私は、いつもと同じように図書室に向かっていた。
ホームルームが終わるとすぐに鞄を持ち、誰にも話しかけられないように、足早に教室を出る。
図書室は3階のいちばん奥にある。
廊下の突き当たりに、静けさを閉じ込めたようなその空間が、私は好きだった。
けれど――その日は、途中で足を止めてしまった。
上の階から、ふと聞こえてきたのは、微かに響くピアノの音。
4階の音楽室。いつもは放課後に誰も使っていないはずの場所から、綺麗な旋律が降ってきた。
音に引き寄せられるように、私は階段をのぼった。
――そして、見てしまった。
真剣な顔で鍵盤に指を落とす、高瀬大翔の姿を。
え?
一瞬、頭が真っ白になった。
運動部の彼が、ピアノを弾いているなんて、まったく想像できなかった。
しかも、その音は、とても綺麗で、やさしくて――思わず息を呑んでしまった。
ドアの小さなガラス越しに、私は立ちすくむ。
すると、大翔がふいに顔を上げた。
目が合った。
思わず視線をそらしかけた私に、彼はゆっくりとドアを開けた。
「……見た?」
私は小さく頷く。
「誰にも言うなよ」
その声は、いつもの教室で聞く明るさではなくて、
少しだけ不安そうで、少しだけ、頼るような響きがあった。
「……うん」
私は、それだけを口にして、その場を離れた。
けれど、胸の奥には静かなざわめきが残っていた。
“本当の彼を知ってしまった気がする”
それが、私、香月紬と高瀬大翔のはじまりだった。
音楽室の出来事以来、私は彼のことが少しだけ気になるようになっていた。
でも、あの日のことには触れられることもなく、私たちはただの“クラスメイト”として、静かに日々を過ごしていた。
……はずだった。
「なあ、これどこに出せばいいんだっけ?」
そう言って、教室の隅で本を読んでいた私に、唐突に声をかけてきたのが高瀬くんだった。
彼は環境委員で、私は図書委員。直接関わることなんてほとんどないはずなのに、不思議だった。
「えっと……それは、分別の貼り紙に──」
そう言いかけた私の手元を、彼はふと見下ろした。
ノートの上に、学校とは関係ない小さな物語の文字が並んでいる。
「……それ、なに書いてんの?」
そう聞かれて、私は思わずノートを閉じた。
誰にも見せたことのない、“もうひとりのわたし”を、彼に見られた気がして。
放課後の図書室。
今日も、静かな空気の中で私はペンを走らせていた。
図書委員の仕事を終えたあとの、ほんのひととき。
この時間だけが、私が“わたし”でいられる、大切な居場所。
──カツ、カツ。
足音に顔を上げると、そこには見慣れた姿が立っていた。
「……高瀬くん?」
「あー……やっぱ、おまえだった」
彼は、手に私のノートを持っていた。
慌てて立ち上がろうとしたけれど、もう遅かった。
「ちょっと、それ返して──!」
「ん? “風のない夕暮れに、きみの声だけが響いていた”……」
ぱら、とページをめくる彼の指が止まる。
「……これ、おまえが書いたの?」
「っ、それ……違う。授業の……メモで……」
苦しい言い訳だった。
彼はふっと笑って、ノートを閉じた。
「へぇ、意外。……でも、こういうの、いいと思うよ」
「……誰にも言わないで」
「んー……どうしよっかな」
からかうような笑みが口元に浮かぶ。
「……あの日のこと。音楽室で、おれがピアノ弾いてたの、見たよな?」
「……うん」
「じゃあ、こうしよう。おまえがそれ黙っててくれるなら──
このノートのことも、誰にも言わない。……交換条件な」
彼はそう言って、ノートを私の手にそっと戻した。
「秘密、ひとつずつ。……これでおあいこだな?」
「……ずるい」
「よく言われる」
目が合った瞬間、どこかくすぐったいような沈黙が生まれた。
音楽室の出来事も、このノートの中の言葉も、
まだ誰にも知られたくない、小さな“わたし”だった。
けれど彼は、それを奪わなかった。
ただ、そっと心の隣に置いただけだった。