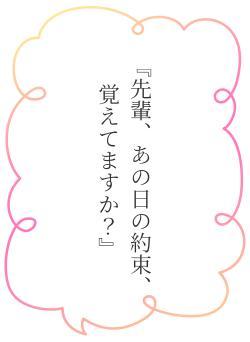高校の許可を取って、大翔くんとふたりで母校を訪れたのは、日曜日の午後だった。
正門をくぐると、懐かしいはずの空気が胸の奥をふわりとくすぐった。
けれど、その空気の中に自分の記憶が結びつくことはなくて、
私はただ、「ここにいたことがあるらしい」という不思議な気持ちのまま、校舎の中へと足を運んだ。
「こっち」
大翔くんが歩き出す。
迷いのない足取りで、校舎の階段を上がり、3階の図書室を通り過ぎて、4階へ向かう。
そして、音楽室の前で、静かに立ち止まった。
「……ここだよ」
扉を開けると、ふわりと冷たい空気が頬にふれた。
誰もいない、昼下がりの音楽室。
窓際のカーテンが揺れ、その隙間から差し込む光が、
静かに床のタイルを照らしている。
「……ここ、覚えてる?」
大翔くんの声が、背後からやわらかく響く。
私は静かに首を振った。
「なんとなく見たことある気がするけど……
記憶に、はっきりとは残ってないの。ごめんね」
彼は「ううん」と小さく笑いながら、
部屋の隅にある椅子を引いて、私にも座るように促した。
私は、その隣に腰を下ろす。
しん、とした空間に、ふたり分の気配だけがあった。
「ここでさ……
紬が初めて、オレの“秘密”を見ちゃったんだよ」
「……秘密?」
「うん。朝早く来て、こっそりピアノを弾いてたの。
誰にも言ってなかったんだけど、
たまたま来た紬にバレちゃって」
私は思わず彼の顔を見た。
「……ピアノ?」
「そう。
高校ではずっと野球部だったし、ピアノなんてキャラじゃないって、
誰にも言えなかったんだよね」
彼の言葉は、どこか懐かしさをまとっていて、
それがまた、私には“知らない自分”を突きつけてくる。
──ここにいた“私”。
彼と、なにかを交わしていた“私”。
「……ごめんね。
きっと、そのときの私は、びっくりしながらも笑ってたんだろうけど……
今の私は、うまく想像することしかできないの」
私の声に、彼は少しだけ目を伏せてから、穏やかに微笑んだ。
「それでもいいよ。
今の紬に、少しでも“そのとき”を感じてもらえたなら、
それだけで十分だから」
私は静かに頷いた。
窓から差し込む光が、
どこか懐かしさを帯びたまま、ふたりを包んでいた。
──それは、思い出せないけれど、たしかに“心”が動いた時間だった。
正門をくぐると、懐かしいはずの空気が胸の奥をふわりとくすぐった。
けれど、その空気の中に自分の記憶が結びつくことはなくて、
私はただ、「ここにいたことがあるらしい」という不思議な気持ちのまま、校舎の中へと足を運んだ。
「こっち」
大翔くんが歩き出す。
迷いのない足取りで、校舎の階段を上がり、3階の図書室を通り過ぎて、4階へ向かう。
そして、音楽室の前で、静かに立ち止まった。
「……ここだよ」
扉を開けると、ふわりと冷たい空気が頬にふれた。
誰もいない、昼下がりの音楽室。
窓際のカーテンが揺れ、その隙間から差し込む光が、
静かに床のタイルを照らしている。
「……ここ、覚えてる?」
大翔くんの声が、背後からやわらかく響く。
私は静かに首を振った。
「なんとなく見たことある気がするけど……
記憶に、はっきりとは残ってないの。ごめんね」
彼は「ううん」と小さく笑いながら、
部屋の隅にある椅子を引いて、私にも座るように促した。
私は、その隣に腰を下ろす。
しん、とした空間に、ふたり分の気配だけがあった。
「ここでさ……
紬が初めて、オレの“秘密”を見ちゃったんだよ」
「……秘密?」
「うん。朝早く来て、こっそりピアノを弾いてたの。
誰にも言ってなかったんだけど、
たまたま来た紬にバレちゃって」
私は思わず彼の顔を見た。
「……ピアノ?」
「そう。
高校ではずっと野球部だったし、ピアノなんてキャラじゃないって、
誰にも言えなかったんだよね」
彼の言葉は、どこか懐かしさをまとっていて、
それがまた、私には“知らない自分”を突きつけてくる。
──ここにいた“私”。
彼と、なにかを交わしていた“私”。
「……ごめんね。
きっと、そのときの私は、びっくりしながらも笑ってたんだろうけど……
今の私は、うまく想像することしかできないの」
私の声に、彼は少しだけ目を伏せてから、穏やかに微笑んだ。
「それでもいいよ。
今の紬に、少しでも“そのとき”を感じてもらえたなら、
それだけで十分だから」
私は静かに頷いた。
窓から差し込む光が、
どこか懐かしさを帯びたまま、ふたりを包んでいた。
──それは、思い出せないけれど、たしかに“心”が動いた時間だった。