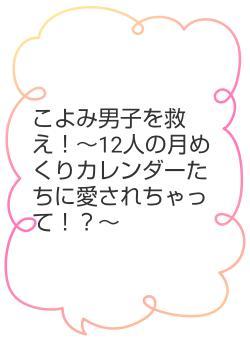三日月先輩が不服そうにドカッとソファーに座った。それを見て燎くんが紅茶の準備をし始めた。
「真涼が誰かにつけられてんのは確かだ」
燎くんにイスどうぞって出されたけど座る気になれなくて立ったまま聞いていた、足を組んで話す三日月先輩の言葉を。
「真涼を見てる視線を俺も感じた、だからこれは間違いない」
「あ、それはオレもある!でも特に誰とかわかんなかったんだよね~」
燎くんがケトルのお湯をティーポットに入れたから、ふわっと紅茶の香りが立ち込めた。
「ずっと気になってたんだ、梅雨祭りの日…真涼を見ている女がいたことを」
!?
あたしを見てた?あの時…
“祭りの日、誰かと約束してたか?”
「せーくん見てたの!?」
「でも顔を見たのはその1度きりで、遠かったから誰かはわからなかった」
燎くんが紅茶を持って来た。
静かに紅茶をひとくち飲んだ。ひとくち飲んで、真っ直ぐあたしを見る。
「だけど突然俺の前に現れた、わざわざ真涼の名前を出して俺に何か伝える仕草を見せて」
もう一度こくんっと紅茶を飲む、ふぅっと息を吐いて。
「そいつがあの時の女だろ、遠かったけど似てる」
「真涼が誰かにつけられてんのは確かだ」
燎くんにイスどうぞって出されたけど座る気になれなくて立ったまま聞いていた、足を組んで話す三日月先輩の言葉を。
「真涼を見てる視線を俺も感じた、だからこれは間違いない」
「あ、それはオレもある!でも特に誰とかわかんなかったんだよね~」
燎くんがケトルのお湯をティーポットに入れたから、ふわっと紅茶の香りが立ち込めた。
「ずっと気になってたんだ、梅雨祭りの日…真涼を見ている女がいたことを」
!?
あたしを見てた?あの時…
“祭りの日、誰かと約束してたか?”
「せーくん見てたの!?」
「でも顔を見たのはその1度きりで、遠かったから誰かはわからなかった」
燎くんが紅茶を持って来た。
静かに紅茶をひとくち飲んだ。ひとくち飲んで、真っ直ぐあたしを見る。
「だけど突然俺の前に現れた、わざわざ真涼の名前を出して俺に何か伝える仕草を見せて」
もう一度こくんっと紅茶を飲む、ふぅっと息を吐いて。
「そいつがあの時の女だろ、遠かったけど似てる」