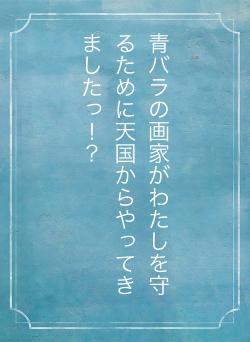店先の看板に『ごきゅうけい 十六夜堂』と書かれている。
古民家をリノベーションしたらしい、落ち着く外観の店だった。
「ほな、入り。みんな、待っとるで」
ガラッと引き戸を開け、さっさとなかへ入ってしまうモクレン。
わたしは、思わずレンゲを見あげた。
さっきから緊張で、心臓がバクバクとうるさいから。
すると、レンゲはやさしくほほ笑み、わたしの頭をそっと撫でてくれた。
大きな手のあたたかい温度が、じんわりと伝わってくる。
「大丈夫だ。おれがいる」
「レンゲの手、あったかい」
「そうか」
「レンゲの肉球、やわらかくて癒されるから、だいすき」
「……おれは今、猫じゃない」
なぜか、レンゲはふてくされたように、わたしの頭から手を下ろしてしまう。
そして今度は、わたしの手を握ってきた。
「入るぞ。いいか?」
「うん」
わたしたちはいっしょに、『十六夜堂』の入り口をくぐった。
古民家の外観とはうって変わって、内装はとてもオシャレだった。
洋風の家具だったり、和ダンスだったりとチグハグなのに、不思議とまとっていて、落ち着く空間になっている。
席はカウンターと、テーブル席が五つ用意されているようだった。
「メニューは、何があるんだろう……」
テーブルに置かれた、メニュー表をのぞいてみる。
【 本日のメニュー 】
天の川アクアリウムの星屑ゼリー
どんぐりと雨粒のクッキー
ポインセチアさんの自家製豆乳プリン
にじいろ入道雲わたあめ
シーグラスの金平糖
ホットミルク
低脂肪牛乳
雨水
ハワイの天然水
【 〜モーニングは、11時まで〜 】
「おいしそう! ドリンクに、特徴的なやつがあるけど……」
「チカナがよく飲んでいる、おかしな色の水は書いてないのか?」
「なにそれ。おかしな色の水なんて飲んでないよ」
「おかしいだろ。底に黒い玉がたくさん入ってる水なんて」
黒い玉がいっぱい入ってる、人間の飲み物……?
それって、まさか。
「タピオカドリンクのこと?」
「名前は覚えていないが、おいしそうに飲んでいたな。おれからしたら、飲みたいとは思わないが」
「飲んでみたら、おいしいかもしれないよ? 今度、いっしょに飲もう!」
すると、レンゲは少しだけ驚いた顔をしたあと、喜びを抑えきれないとばかりに、口元をゆるめた。
「しかし、雨水までメニューに入ってるなんて、ここはどういう店なんだ?」
「キノ・キランのレンゲでもそう思うんだ?」
すると、モクレンがわたしたちのあいだに乱入してきて、得意げに人差し指を立てた。
「雨水は、タダやろ。つまり、もうかるっちゅうわけや。値段も百円ポッキリ。十杯売ったら、千円のもうけ」
「ぼったくりじゃん!」
「早とちりすなや。そのまんま出すわけないやろ。ちゃんと、きれいに浄水したやつやで」
「そんなんで許されるの?」
「常連のハコベラっちゅうやつは、いつも雨水を注文するで。好みは、それぞれやろ」
たしかに。
わたしは、コンビニに行ってドリンクを買うとき、わざわざ水を買うくらいなら、めったに飲めないジュースを買う。
でも、水を買う人がいるから、コンビニに置いてあるんだよね。
好みは、人それぞれ。キノ・キランもそれぞれ、ってことか。
「あ、ナズナさま」
「え!」
モクレンの言葉に、わたしは飛びあがって、思わずレンゲの腕にしがみついた。
モクレンの見ているほうを、おそるおそる振り返る。
そこには、さらりと床まで伸びた、きれいな黒髪。
黒い長じゅばんに、あざやかな牡丹柄の道中着をだらりと着くずしている、女の人がいた。
まつ毛は夜の闇のように黒く、人間離れした長さで、毛というよりは、羽のようだ。
それに、長くするどい黒い爪。
パタパタとレースの扇子をあおぎながら、おだやかな笑みをたたえている。
「あ、あなたが、ナズナさま?」
「ええ。そうですー」
しゃべり方のイントネーションが、モクレンと似てる。
「モクレンと似た方言なんですね」
「カラスは、いたるとこで生息しとります。でも、わたくしは、もっぱら西の森がすきでした。ずうっと、そこに住んでましたわ。モクレンも近くに住んどったんやろ?」
「そうですー。ナズナさまのいうとおり」
何その、わたしたちのときとは違う態度。
わたしの空気を察したのか、モクレンがこっそりと耳うちをしてくる。
「ナズナさまを、ぜったいに怒らせたらあかんよ」
「なんで?」
「ナズナさまはな、かなり気難しいねん。機嫌をそこねたら一瞬で、ひげをぬかれる!」
「ひ、ひげ?」
「ナズナさまにかかれば、お前なんか、まばたきせんうちに消し炭やで」
そんなに怒るような人には見えないけどなあ。
「モクレン」
「はひっ」
ナズナさまの地を這うような低い声に、モクレンが顔を青ざめながら、ぴょんっ、と飛びあがった。
「あんた、また『花のでがらしショー』をしたんやて」
「なっ、なぜそれを知って……」
「修行せえ、ってあれほど口を酸っぱくして説教したのに、また逃げ出したんやね」
「い、いえ、その……ナズナさま、それは……」
しどろもどろのモクレンは、視線を泳がせ、どうにかいい訳を考えているようだ。
すると、ナズナさまの後ろから、ひょこっと誰かが出てきた。
「わるい子、だーれだ」
キノ・キランすがたの、シロツメだ。
あの日、夜の闇でよく見えなかったすがたが、今日はよく見える。
スポーツブランドのキャップから出ている三角耳に、白のオーバーサイズTシャツ、変形ストレッチパンツから出ているのは、シバイヌのしっぽ。
「しっ、シロツメええ!」
ギロリ、とシロツメをにらみつける、モクレン。
「きみがいったんやな! ナズナさまに! ぼくのショーのこと!」
「ダメだった」
「ダメに決まってるやろ!」
フシャーッ! と、敵意むき出しのモクレンに、いたずらっぽくニヤニヤしているシロツメ。
すると、ナズナさまが、シロツメの背中をトン、と叩いた。
「モクレンへのお仕置きは、また後で。シロツメ、モクレンを連れて、奥へ行ってな。キツネはコンコンしゃべって、うるさいから」
「はいはーい」
ナズナさまの手前、これ以上は逆らえないと、モクレンは早々に、抵抗することをあきらめたらしい。
シロツメにスーツのえりをつかまれ、ずるずると引きずられながら、おとなしく店の奥へと連れていかれてしまった。
「チカナ。やっと来たのか」
ふたりと入れ違いで、ヤクモがひょっこりと顔を出した。
「ナズナさま。なんか、モクレンが騒いでましたけど?」
「だいたい、察しはつくやろ。それより、ほれ。この子んらやろ、ヤクモ? あんたがいってたんは」
ヤクモが「はい」と、うなずいた。
「ふたりとも、店のメニューはもう見たのか? 注文は?」
「見たけど……雨水以外なら、何でもいいかな」
「じゃあ、ホットミルクだな。あとは……ポインセチアさんの自家製豆乳プリン。おれのおすすめだ。レンゲは?」
レンゲは、わたしをちらりと見たあと、ぼそりとつぶやいた。
「ハワイの天然水」
「オーケー」
ヤクモが、カウンターのなかに入っていく。
「ヤクモは働きもんやな。助かるわ」
ナズナさまが、「よっこらせ」とカウンターのイスに座る。
「あんたらも座り。疲れたやろ」
ナズナさまにすすめられるがまま、その隣に腰かけた。
レンゲも、わたしの隣の席におさまる。
「そんで? ここに来たってことは、うちの店の従業員になってくれるってことで、ええの?」
ナズナさまは、まっすぐにわたしを見つめて、返事を待っている。
わたしは、すぐには答えられなかった。
もちろん、十六夜堂がしていることは応援したいし、できることがあるなら手伝いたい。
でも、わたしはキノ・キランのことも、まだ知ったばかりの素人みたいなものだし。
まずは、わたしにどんなことができるのか、聞いてみたほうがいいよね。
なんて、ぐるぐると考えこんでいると、レンゲがカウンターに身を乗り出し、ナズナさまに向き合った。
「チカナに危ないことはさせられない。まずは、おまえたちがどんなことをしているのか、詳細に教えてもらおう」
レンゲのはっきりとした意見に、わたしはぽかんと口を開いてしまう。
このひと、ほんとうに、いつもうちのリビングで、でろーんとからだを伸ばしてお昼寝している、うちのメインクーン?
なんだか信じられなくて、まじまじと顔を見つめてしまう。
わたしの視線を戸惑いながら受け止めたあと、レンゲは気を取り直したように「コホン」と咳払いをした。
「存在もつかめていない、怪しい組織と戦うんだろう。ちゃんと対策は考えてあるんだろうな」
そのとき、わたしの前に、ほっこりとした湯気がたっているホットミルクが出てきた。
続けて、ポインセチアさんの自家製豆乳プリン。
可愛いお皿に乗せられており、ちょこんとクリームもそえられている。
レンゲが頼んだハワイの天然水は、おちゃれな琉球グラスに注がれていた。
注文の品を置きながら、ヤクモがレンゲの質問に答えてくれた。
「くわしい話か。まあ、したいのはやまやまだけど……」
ヤクモが、わたしたちの後ろを指差した。
振り返ると、丸い天窓があり、サッシに何かがとまっている。
カラスだ。
キノ・キランじゃない、ふつうの黒いカラス。
「ナズナさまの助手のセセリだ。一般のキノ・キランから、緊急通報が入ったみたいだな」
「ってことは」
「出動だな。……シロツメ!」
「ほい!」
ヤクモの呼びかけに、カウンターの奥から、シロツメがつむじ風のように現れた。
「わるい、チカナ。すぐ帰るから、プリン食べて待っててくれ」
「ううん。わたしも行く!」
イスから立ち上がり、わたしはホットミルクを一気に飲み干した。
「プリンは帰ってきてからのお楽しみにしておくよ」
「待て、チカナ。何、考えてる」
レンゲが、わたしの肩をつかんだ。
「おまえが、十六夜堂の協力をしたい気持ちはわかった。でも、それはどんな仕事があるのか、きちんと見定めてからだ。おれが話をつけるから……」
「誰かが困ってて、わたしに何か出来ることがあるなら、だまって座ってるなんて、できないよ! わたしのやりたいことって、それなの! レンゲなら、わかってくれるでしょ」
わたしの言葉に、レンゲは「はーっ」と息をついた。
長いあいだ、わたしたちはいっしょに暮してきたよね。
だから、わたしがどうしたいのかなんて、レンゲにはお見通しでしょ。
「おまえは頑固だ。こうなったら、おれのいうことは聞いてくれないだろうな」
額をおさえながら、レンゲはわたしをジッと見つめてくれる。
うん。好きにしろって、ことだね。
「ヤクモ、わたしたちも連れてって。いいいよね?」
「ああ。もちろん」
わたしたちのやりとりに、ナズナさまは、おだやかな笑みを浮かべた。
「チカナ、レンゲ。あんたら、ほんまにええ子やね。期待しとるで」
ナズナさまの前に、シーグラスの金平糖が散りばめられたホットミルクが置かれている。
金平糖が、ゆっくりと溶けていくのをナズナさまは、くるんと、かき混ぜた。
古民家をリノベーションしたらしい、落ち着く外観の店だった。
「ほな、入り。みんな、待っとるで」
ガラッと引き戸を開け、さっさとなかへ入ってしまうモクレン。
わたしは、思わずレンゲを見あげた。
さっきから緊張で、心臓がバクバクとうるさいから。
すると、レンゲはやさしくほほ笑み、わたしの頭をそっと撫でてくれた。
大きな手のあたたかい温度が、じんわりと伝わってくる。
「大丈夫だ。おれがいる」
「レンゲの手、あったかい」
「そうか」
「レンゲの肉球、やわらかくて癒されるから、だいすき」
「……おれは今、猫じゃない」
なぜか、レンゲはふてくされたように、わたしの頭から手を下ろしてしまう。
そして今度は、わたしの手を握ってきた。
「入るぞ。いいか?」
「うん」
わたしたちはいっしょに、『十六夜堂』の入り口をくぐった。
古民家の外観とはうって変わって、内装はとてもオシャレだった。
洋風の家具だったり、和ダンスだったりとチグハグなのに、不思議とまとっていて、落ち着く空間になっている。
席はカウンターと、テーブル席が五つ用意されているようだった。
「メニューは、何があるんだろう……」
テーブルに置かれた、メニュー表をのぞいてみる。
【 本日のメニュー 】
天の川アクアリウムの星屑ゼリー
どんぐりと雨粒のクッキー
ポインセチアさんの自家製豆乳プリン
にじいろ入道雲わたあめ
シーグラスの金平糖
ホットミルク
低脂肪牛乳
雨水
ハワイの天然水
【 〜モーニングは、11時まで〜 】
「おいしそう! ドリンクに、特徴的なやつがあるけど……」
「チカナがよく飲んでいる、おかしな色の水は書いてないのか?」
「なにそれ。おかしな色の水なんて飲んでないよ」
「おかしいだろ。底に黒い玉がたくさん入ってる水なんて」
黒い玉がいっぱい入ってる、人間の飲み物……?
それって、まさか。
「タピオカドリンクのこと?」
「名前は覚えていないが、おいしそうに飲んでいたな。おれからしたら、飲みたいとは思わないが」
「飲んでみたら、おいしいかもしれないよ? 今度、いっしょに飲もう!」
すると、レンゲは少しだけ驚いた顔をしたあと、喜びを抑えきれないとばかりに、口元をゆるめた。
「しかし、雨水までメニューに入ってるなんて、ここはどういう店なんだ?」
「キノ・キランのレンゲでもそう思うんだ?」
すると、モクレンがわたしたちのあいだに乱入してきて、得意げに人差し指を立てた。
「雨水は、タダやろ。つまり、もうかるっちゅうわけや。値段も百円ポッキリ。十杯売ったら、千円のもうけ」
「ぼったくりじゃん!」
「早とちりすなや。そのまんま出すわけないやろ。ちゃんと、きれいに浄水したやつやで」
「そんなんで許されるの?」
「常連のハコベラっちゅうやつは、いつも雨水を注文するで。好みは、それぞれやろ」
たしかに。
わたしは、コンビニに行ってドリンクを買うとき、わざわざ水を買うくらいなら、めったに飲めないジュースを買う。
でも、水を買う人がいるから、コンビニに置いてあるんだよね。
好みは、人それぞれ。キノ・キランもそれぞれ、ってことか。
「あ、ナズナさま」
「え!」
モクレンの言葉に、わたしは飛びあがって、思わずレンゲの腕にしがみついた。
モクレンの見ているほうを、おそるおそる振り返る。
そこには、さらりと床まで伸びた、きれいな黒髪。
黒い長じゅばんに、あざやかな牡丹柄の道中着をだらりと着くずしている、女の人がいた。
まつ毛は夜の闇のように黒く、人間離れした長さで、毛というよりは、羽のようだ。
それに、長くするどい黒い爪。
パタパタとレースの扇子をあおぎながら、おだやかな笑みをたたえている。
「あ、あなたが、ナズナさま?」
「ええ。そうですー」
しゃべり方のイントネーションが、モクレンと似てる。
「モクレンと似た方言なんですね」
「カラスは、いたるとこで生息しとります。でも、わたくしは、もっぱら西の森がすきでした。ずうっと、そこに住んでましたわ。モクレンも近くに住んどったんやろ?」
「そうですー。ナズナさまのいうとおり」
何その、わたしたちのときとは違う態度。
わたしの空気を察したのか、モクレンがこっそりと耳うちをしてくる。
「ナズナさまを、ぜったいに怒らせたらあかんよ」
「なんで?」
「ナズナさまはな、かなり気難しいねん。機嫌をそこねたら一瞬で、ひげをぬかれる!」
「ひ、ひげ?」
「ナズナさまにかかれば、お前なんか、まばたきせんうちに消し炭やで」
そんなに怒るような人には見えないけどなあ。
「モクレン」
「はひっ」
ナズナさまの地を這うような低い声に、モクレンが顔を青ざめながら、ぴょんっ、と飛びあがった。
「あんた、また『花のでがらしショー』をしたんやて」
「なっ、なぜそれを知って……」
「修行せえ、ってあれほど口を酸っぱくして説教したのに、また逃げ出したんやね」
「い、いえ、その……ナズナさま、それは……」
しどろもどろのモクレンは、視線を泳がせ、どうにかいい訳を考えているようだ。
すると、ナズナさまの後ろから、ひょこっと誰かが出てきた。
「わるい子、だーれだ」
キノ・キランすがたの、シロツメだ。
あの日、夜の闇でよく見えなかったすがたが、今日はよく見える。
スポーツブランドのキャップから出ている三角耳に、白のオーバーサイズTシャツ、変形ストレッチパンツから出ているのは、シバイヌのしっぽ。
「しっ、シロツメええ!」
ギロリ、とシロツメをにらみつける、モクレン。
「きみがいったんやな! ナズナさまに! ぼくのショーのこと!」
「ダメだった」
「ダメに決まってるやろ!」
フシャーッ! と、敵意むき出しのモクレンに、いたずらっぽくニヤニヤしているシロツメ。
すると、ナズナさまが、シロツメの背中をトン、と叩いた。
「モクレンへのお仕置きは、また後で。シロツメ、モクレンを連れて、奥へ行ってな。キツネはコンコンしゃべって、うるさいから」
「はいはーい」
ナズナさまの手前、これ以上は逆らえないと、モクレンは早々に、抵抗することをあきらめたらしい。
シロツメにスーツのえりをつかまれ、ずるずると引きずられながら、おとなしく店の奥へと連れていかれてしまった。
「チカナ。やっと来たのか」
ふたりと入れ違いで、ヤクモがひょっこりと顔を出した。
「ナズナさま。なんか、モクレンが騒いでましたけど?」
「だいたい、察しはつくやろ。それより、ほれ。この子んらやろ、ヤクモ? あんたがいってたんは」
ヤクモが「はい」と、うなずいた。
「ふたりとも、店のメニューはもう見たのか? 注文は?」
「見たけど……雨水以外なら、何でもいいかな」
「じゃあ、ホットミルクだな。あとは……ポインセチアさんの自家製豆乳プリン。おれのおすすめだ。レンゲは?」
レンゲは、わたしをちらりと見たあと、ぼそりとつぶやいた。
「ハワイの天然水」
「オーケー」
ヤクモが、カウンターのなかに入っていく。
「ヤクモは働きもんやな。助かるわ」
ナズナさまが、「よっこらせ」とカウンターのイスに座る。
「あんたらも座り。疲れたやろ」
ナズナさまにすすめられるがまま、その隣に腰かけた。
レンゲも、わたしの隣の席におさまる。
「そんで? ここに来たってことは、うちの店の従業員になってくれるってことで、ええの?」
ナズナさまは、まっすぐにわたしを見つめて、返事を待っている。
わたしは、すぐには答えられなかった。
もちろん、十六夜堂がしていることは応援したいし、できることがあるなら手伝いたい。
でも、わたしはキノ・キランのことも、まだ知ったばかりの素人みたいなものだし。
まずは、わたしにどんなことができるのか、聞いてみたほうがいいよね。
なんて、ぐるぐると考えこんでいると、レンゲがカウンターに身を乗り出し、ナズナさまに向き合った。
「チカナに危ないことはさせられない。まずは、おまえたちがどんなことをしているのか、詳細に教えてもらおう」
レンゲのはっきりとした意見に、わたしはぽかんと口を開いてしまう。
このひと、ほんとうに、いつもうちのリビングで、でろーんとからだを伸ばしてお昼寝している、うちのメインクーン?
なんだか信じられなくて、まじまじと顔を見つめてしまう。
わたしの視線を戸惑いながら受け止めたあと、レンゲは気を取り直したように「コホン」と咳払いをした。
「存在もつかめていない、怪しい組織と戦うんだろう。ちゃんと対策は考えてあるんだろうな」
そのとき、わたしの前に、ほっこりとした湯気がたっているホットミルクが出てきた。
続けて、ポインセチアさんの自家製豆乳プリン。
可愛いお皿に乗せられており、ちょこんとクリームもそえられている。
レンゲが頼んだハワイの天然水は、おちゃれな琉球グラスに注がれていた。
注文の品を置きながら、ヤクモがレンゲの質問に答えてくれた。
「くわしい話か。まあ、したいのはやまやまだけど……」
ヤクモが、わたしたちの後ろを指差した。
振り返ると、丸い天窓があり、サッシに何かがとまっている。
カラスだ。
キノ・キランじゃない、ふつうの黒いカラス。
「ナズナさまの助手のセセリだ。一般のキノ・キランから、緊急通報が入ったみたいだな」
「ってことは」
「出動だな。……シロツメ!」
「ほい!」
ヤクモの呼びかけに、カウンターの奥から、シロツメがつむじ風のように現れた。
「わるい、チカナ。すぐ帰るから、プリン食べて待っててくれ」
「ううん。わたしも行く!」
イスから立ち上がり、わたしはホットミルクを一気に飲み干した。
「プリンは帰ってきてからのお楽しみにしておくよ」
「待て、チカナ。何、考えてる」
レンゲが、わたしの肩をつかんだ。
「おまえが、十六夜堂の協力をしたい気持ちはわかった。でも、それはどんな仕事があるのか、きちんと見定めてからだ。おれが話をつけるから……」
「誰かが困ってて、わたしに何か出来ることがあるなら、だまって座ってるなんて、できないよ! わたしのやりたいことって、それなの! レンゲなら、わかってくれるでしょ」
わたしの言葉に、レンゲは「はーっ」と息をついた。
長いあいだ、わたしたちはいっしょに暮してきたよね。
だから、わたしがどうしたいのかなんて、レンゲにはお見通しでしょ。
「おまえは頑固だ。こうなったら、おれのいうことは聞いてくれないだろうな」
額をおさえながら、レンゲはわたしをジッと見つめてくれる。
うん。好きにしろって、ことだね。
「ヤクモ、わたしたちも連れてって。いいいよね?」
「ああ。もちろん」
わたしたちのやりとりに、ナズナさまは、おだやかな笑みを浮かべた。
「チカナ、レンゲ。あんたら、ほんまにええ子やね。期待しとるで」
ナズナさまの前に、シーグラスの金平糖が散りばめられたホットミルクが置かれている。
金平糖が、ゆっくりと溶けていくのをナズナさまは、くるんと、かき混ぜた。