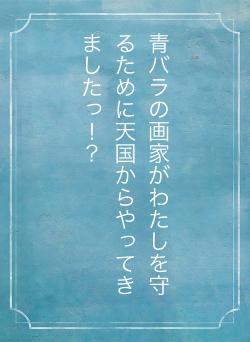■
レンゲのにおい付けも完了し、わたしたちはさっそく、十六夜堂へと向かった。
「それで、その店がどこにあるか、知ってるの?」
するとレンゲは、ニヤリと不敵な笑みを浮かべた。
「猫は、なんでも知っている。このへんの猫に聞けば、すぐにわかる」
「このへんの猫っていうと」
黙って歩き出したレンゲに、わたしは着いていく。
しばらくして、白壁にマリンブルーのラインが入った、シチリア風の三角屋根の家の前で立ち止まる。
ここには、おばあさんがひとりで住んでいて、アネモネっていう、ブリティッシュショートヘアの猫を飼っているんだ。
季節の花が植えられているベランダから、アネモネはいつも外をながめている。
「アネモネは、いつもここから、この町の動きを観察している。人間の行動、カラスのイタズラ、犬の散歩ルート、車の行き交い。全てを記憶している」
「す、すごい……」
感心していると、レンゲが「にゃあ」とアネモネに話しかけた。
アネモネも、「にゃあ?」と返す。
わたしはレンゲの横で、二人の会話を見届けることにした。
「にゃあにゃあ」「にゃごにゃご」と、猫語の会話が数分続いた。
「ふうん」
レンゲが、あごに手を添え、納得したようにうなった。
「どうだった?」
レンゲの話では、アネモネは、こういったらしい。
『十六夜堂?
ああ、カラスから小耳にはさんだことがありますわ。
十六夜堂とは、キノ・キラン専用のカフェです。
キノ・キランの保護活動を行うため、強いキノ・キランと、そのマスターたちを集めているそうですよ。
十六夜堂を作った、キノ・キラン最長老のナズナさまが中心となって活動しているそうですわ』
「ナズナさまも、キノ・キランなんだ。」
「アネモネによると、ナズナは、コローネ・キノ。ハシボソガラスのキノ・キランだとさ」
カラスにも、色んな種類があるんだなあ。
「それで、どこにあるの? 十六夜堂は」
「三日月通りの三番目の電柱と、赤いポストのあいだ。そこにある、細い裏道をぬけた先、といっていたな」
思わず、わたしは「え?」と、首を傾げた。
「三日月通りに、ポストなんかないよ」
「そうなのか?」
「うん。三日月通りに友達が住んでるから、よく通るけど。ポストなんて、見たことないな……」
レンゲは鼻先を指でいじりながら、考えこんだ。
猫が、顔を洗う仕草に似ているかも。
たしか、猫が顔を洗うのは『リラックス効果』のためなんだっけ。
考え事をしているから、ついやっちゃうのかも。
うーん。こうして、立ち止まっていても、仕方ないよね。
「レンゲ。とりあえず、行ってみよう。三日月通り」
「……そうだな」
三日月通りまでは、今いる道を、まっすぐだ。
そのとき、ブワッと生暖かい風が、わたしたちのあいだを拭きぬけた。
紫色の花びらが、風のなかをぐるぐると舞いながら、飛んでいく。
「うわ、すごい風」
「これは、紫陽花の花びら……」
レンゲが、ぎゅっと眉間にシワを浮かべ、わたしを抱き寄せた。
ばさり、と何かがレンゲのおしりから飛び出した。
腰に巻いていたストールが、しっぽの勢いのせいでズレてしまったみたいだ。
「ちょっと、レンゲ……しっぽが」
レンゲのしっぽの毛が、逆立っている。
これは猫が、攻撃態勢に入っているサイン。
「あれー? これって、猫のしっぽ?」
ま、まずい。
レンゲのしっぽを、誰かに見られた!
「……誰だ」
レンゲが、「フシャア……」と、牙を見せつけながら、うなり声をあげる。
「猫のしっぽ。いいねえ。人間は、ふわふわしたものが大すきなんでしょ?」
声がしたほうを振り返る。
真っ黒なスーツを着たお兄さんが電柱に肘をかけ、怪しい笑顔をたたえていた。
お兄さんは、シルバーのネックレスやブレスレット、ピアスやリングをつけていた。
風にゆれるたびに、アクセサリーがジャラジャラと音をたてている。
金色の瞳がまるで、獲物を狩るときの肉食獣みたいに見え、わたしはゾッと背筋を震わせた。
お兄さんは、黒く塗られた短い爪をいじりながら、くちびるの端を吊りあげた。
「ぼくはね、この爪をとても大事にしているんだ。だから、ネイルコーティングはかかせない。見て、きらきらしてるでしょう? 特別なエキスが入ったポリマーを使ってるんだ」
「は、はあ……」
「カラスはね、器用にクチバシを使う。クルミだって、コインだって、クチバシでくわえることができるんだ。クチバシを使って、人間のように道具を作ることだってできるんだよ」
「そうなの? すごい!」
すると、お兄さんは嬉しそうに、ほほ笑んだ。
「カラスのすごさがわかるだなんて、きみはとってもいい人間だね」
レンゲが、わたしをお兄さんから遠ざけるように、身を乗り出した。
お兄さんは、ギザギザした歯列を見せながら、空を指さす。
「見てごらん。ほら」
空に、黒いものが、ぶわりと飛び散っている。
これ――カラスの大群だ。
大量のカラスたちが、わたしたちの頭上に集まって来ていた。
「なんで、こんなにカラスが……!」
大量の紫陽花の花びらが、ひらひらと舞っている。
黒と、紫が、視界を飛び回っていて、まるで、ここだけ異次元みたいだ。
「すごいでしょ。ぼくのちから。褒めてくれていいんだよ」
「カラスの大群……。まさか、あなた……ナズナ?」
お兄さんは、恍惚とした表情で、まぶしそうに目を細め、パチンと指を鳴らした。
「ピンポーン。大正解」
すると、まばたきをした瞬間、カラスの大群と紫陽花の花びらたちは、消えてなくなってしまった。
「え、ええっ? 消えちゃった!」
「ああ! きみ、いい反応だなあ!」
いつのまに距離を詰められたのか、お兄さんが高揚したようすで、わたしの両手を取った。
ぶんぶんと手を振りながら、目を輝かせ、鼻先を擦りそうなほどに顔を近づけられる。
「ねえ! きみ、ぼくの専属のお客さんになってくれない?」
「お、お客さん? わたしが?」
「きみみたいな素直な子が、ぼくの成長には必要――ぐえっ!」
首を絞められたカラスみたいな声がした。
手が解放されたかと思うと、レンゲがお兄さんに、手刀をくらわせていた。
「いったあ。何すんねん!」
さっきまで、紳士的だったお兄さんのしゃべり方が、変わっている。
チョップされた頭をさすりながら、涙目でレンゲに抗議している。
「大正解だと? お前は、カラスじゃないだろう。つまり、ナズナじゃない」
「ええ! 違うの?」
びっくりしっぱなしのわたしに、お兄さんが苦笑いをした。
「お前、キノ・キランだな。それも、ルナール・キノ……アカギツネだ」
「げっ。嘘やろ。なんで、わかったんっ?」
動揺したようすで、お兄さんは、あわてふためく。
「相手に幻術をかけるとき、出しすぎた妖力のあまりが花びらとなって出てしまう、『花のでがらし』……幻術の失敗例だな。おれたちが、キノ・キランのことをよく知らないと思って、からかってやろうと思ったんだろうが、甘かったな。これくらいは、予習済みだ」
「ちっ、おもしろないやっちゃのお」
黒スーツのお兄さんは、ふてくされたようにその場に座りこみ、くちびるを尖らせた。
スーツジャケットの内側から、キセルを取り出し、ぷかぷかと吸いはじめる。
「おい。おれのマスターの前で、キセルを吸うとは。いい度胸だな?」
わたしに煙を嗅がせないよう手で仰ぎながら、ぴしゃり、とレンゲがいさめると、お兄さんは目をキツネのように吊あげた。
「これは、ヨモギや! 香りかいでみ」
レンゲは警戒するように、すんすんとキセルのにおいを嗅ぐ。
「……たしかに。なんで、ヨモギなんて吸っている?」
「ええ香りじゃろがい」
お兄さんは不満そうに、けむりを輪っかを吐き出した。
レンゲは腕を組み、しゃがんでいるお兄さんを見おろした。
「それで? 誰なんだ、おまえは」
「はあ~。偉そうやなあ、きみ。ぼくは……仲間には、モクレンなんて呼ばれとる。勝手によろしゅうしたってや」
のんびりとした口調でいう、モクレン。
「なんか、さっきと全然ちがう」
不服そうにいうわたしに、モクレンはへらへらと、キセルをふかす。
「さっきのはなあ、営業スマイルゆうんや。商売や、商売」
「商売……?」
「キノ・キランは、ほとんどが人間社会で生きとる。ぼくらキツネはな、幻術つこうて、ゼニかせぐんよ」
「人をだましてお金をかせいでるってこと?」
ジトッと、モクレンをねめつけると、モクレンは、あわてて首をふった。
「まてまて。幻術ゆうたやろ。つまりな、ショーってことや。きみらも、さっき見たやろ。あれが、ぼくのショーや」
「あれが……?」
ショーだっていわれると、そうなのかもしれないけど。
「つまり、おまえは未熟な証拠である『花のでがらし』をショーの一部に利用しているってことか。さすが、キツネ。小賢しいな」
レンゲの一言に、グッと息をつまらせるモクレン。
「あ、ああいうんでもなあ、キレイやっていうて、喜んでくれる人間もおるんよ!」
叫んだ拍子に、モクレンの頭のてっぺんから、ぴょこんと大きな三角耳が飛び出した。
そこから、ぱらりと紫色の花びらが散らばる。
「うおわ!」
あわてて頭をおさえた、モクレン。
とたん、キセルが足元を落としてしまい、カランと乾いた音が鳴った。
「レンゲ。あれって」
「そこにあるものを、ないように見せるのも、幻術のひとつだ。動揺して、幻術の効果がブレてしまったようだな」
わたしは、キセルを拾ってやり、モクレンにそっと差し出した。
「モクレンのショー、応援するよ。わたしのすきな花びらを出してくれたら、次も見に行ってあげる」
モクレンが、パッと顔をあげる。
「……花、なにがすきなん?」
「菜の花は、すきだよ。菜の花畑を見ると、元気が出るんだ~」
「……へえ」
そして、ニカッと笑うと、黒スーツに散っていた花びらをパッパッとはらう。
頭の上の三角耳が、ゆらっと揺らめいたかと思うと、幻のようにスウッと消えていく。
気づけば、モクレンは最初に出会ったときの、自信たっぷりの表情に戻っていた。
「きみの隣のやつも、キノ・キランなんやろ? 猫のしっぽ、生やしとるもんね」
やっぱり、モクレンにはバレてるよね。
モクレンもキノ・キランだったから、さっきの反応もうなずける。
「ふたり、ナズナさまのところに行きたいんやろ。案内したるわ」
「その気なら、あんなショーなんかしてないで、さっさと案内してくれればいいだろう」
レンゲのぶっきらぼうな言葉に、モクレンはハア、と息をついた。
「情緒のない猫やね。きみたち、名前なんちゅうの」
答えないレンゲに、わたしが代わりに答えた。
「えと、うちの猫のレンゲです」
「あんがとさん。きみの名前は?」
「わたしは、チカナ」
とたん、レンゲがまた、わたしをぐいっと抱きよせた。
また警戒態勢のレンゲに、わたしは飼い主としての立場を思い出す。
「レンゲ。だめだよ、そんな態度」
「飼い猫は、テリトリーにうるさいなあ」
「ごめんね。モクレン」
モクレンはへらっと笑うと、わたしたちの一歩前に立った。
「ナズナさまの店はこっちや」
モクレンが指差す先に、薄明かりが見えた。
「ナズナさまは、変わっとるからなあ。のんびりと構えとるとええよ」
レンゲがいってたよね。
ナズナさまは、変わり者で有名なんだって。
ハシボソガラスのキノ・キラン、コローネ・キノか。
どんなすがたなんだろう。
薄明かりが近くなるにつれ、わたしの胸がざわざわと騒ぎはじめた。
「きみたち、ナズナさまの店がなんか、知っとるか」
「えーと。表向きはキノ・キラン専用カフェ。でも、キノ・キランの保護もやってるんだよね。アネモネに聞いたよ」
「ああ、あのいけすかない猫な」
モクレンも、アネモネのこと知ってるんだ。
「まあ、その通りや。この町だけじゃない。遠くの町まで、キノ・キランを保護しに行っとるやつらもいる。そして、それをまとめとるのが、ナズナさまや」
「モクレンも、保護活動してるの?」
「まあな。まだまだやけどな〜」
モクレンが足を止めた。
三日月通りの、三番目の電柱。
そして、赤いポスト……いや。『赤いヤギ』が、裏道の入口に立っている。
「や、ヤギだ! しかも、赤いよ……!」
「シェーヴル・キノくんや。名前は……なんやったかな?」
モクレンが「はて?」と、のんきに首をかしげる。
すると、赤いヤギが、目をカッと開いたかとおもうと、ものすごい早口で、しゃべりはじめた。
「白ヤギさんからお手紙ついて、黒ヤギさんが読まずに食べる。そして、私は赤いヤギ。読まれることなく食べられる、二人の手紙をえんえんと届け続けた悲運のヤギ! それが、わたくし。赤ヤギのヤドリギ! 十六夜堂のポストマンです!」
しゃ、しゃべった。
つまり、このヤドリギっていうヤギさんは、キノ・キランなのかな。
すがたは、ヤギのままだけど。
「郵便配達イコール、ヤギって理由だけで、ナズナさまから十六夜堂への案内係に任命された、ハイテンションヤギくんや」
「ポストっていうのは、赤いのヤギさんのことだったんだね……」
「裏通りの入口に、このヤドリギがおらんと、十六夜堂はぜったい見つからんようになっとる。人間には、そもそもヤドリギのすがたすら見つからんように、ナズナさまの幻術がかかっとるしな」
「十六夜堂への客を、ナズナさまのもとまで届ける。それが、わたくしの役目です!」
ヤドリギが得意げに、くいっと長い首を持ち上げた。
「さあ、どうぞ。奥の細道へとおいでください! 十六夜堂で、ゆっくりとくつろいでいってくださいね」
さっきまで、暗がりでよく見えなかった十六夜堂への裏道が、ヤドリギの一言で、ぽうっと月の薄明かりに照らされた。
「ナズナさまとヤクモさんが……お待ちですよ!」
レンゲのにおい付けも完了し、わたしたちはさっそく、十六夜堂へと向かった。
「それで、その店がどこにあるか、知ってるの?」
するとレンゲは、ニヤリと不敵な笑みを浮かべた。
「猫は、なんでも知っている。このへんの猫に聞けば、すぐにわかる」
「このへんの猫っていうと」
黙って歩き出したレンゲに、わたしは着いていく。
しばらくして、白壁にマリンブルーのラインが入った、シチリア風の三角屋根の家の前で立ち止まる。
ここには、おばあさんがひとりで住んでいて、アネモネっていう、ブリティッシュショートヘアの猫を飼っているんだ。
季節の花が植えられているベランダから、アネモネはいつも外をながめている。
「アネモネは、いつもここから、この町の動きを観察している。人間の行動、カラスのイタズラ、犬の散歩ルート、車の行き交い。全てを記憶している」
「す、すごい……」
感心していると、レンゲが「にゃあ」とアネモネに話しかけた。
アネモネも、「にゃあ?」と返す。
わたしはレンゲの横で、二人の会話を見届けることにした。
「にゃあにゃあ」「にゃごにゃご」と、猫語の会話が数分続いた。
「ふうん」
レンゲが、あごに手を添え、納得したようにうなった。
「どうだった?」
レンゲの話では、アネモネは、こういったらしい。
『十六夜堂?
ああ、カラスから小耳にはさんだことがありますわ。
十六夜堂とは、キノ・キラン専用のカフェです。
キノ・キランの保護活動を行うため、強いキノ・キランと、そのマスターたちを集めているそうですよ。
十六夜堂を作った、キノ・キラン最長老のナズナさまが中心となって活動しているそうですわ』
「ナズナさまも、キノ・キランなんだ。」
「アネモネによると、ナズナは、コローネ・キノ。ハシボソガラスのキノ・キランだとさ」
カラスにも、色んな種類があるんだなあ。
「それで、どこにあるの? 十六夜堂は」
「三日月通りの三番目の電柱と、赤いポストのあいだ。そこにある、細い裏道をぬけた先、といっていたな」
思わず、わたしは「え?」と、首を傾げた。
「三日月通りに、ポストなんかないよ」
「そうなのか?」
「うん。三日月通りに友達が住んでるから、よく通るけど。ポストなんて、見たことないな……」
レンゲは鼻先を指でいじりながら、考えこんだ。
猫が、顔を洗う仕草に似ているかも。
たしか、猫が顔を洗うのは『リラックス効果』のためなんだっけ。
考え事をしているから、ついやっちゃうのかも。
うーん。こうして、立ち止まっていても、仕方ないよね。
「レンゲ。とりあえず、行ってみよう。三日月通り」
「……そうだな」
三日月通りまでは、今いる道を、まっすぐだ。
そのとき、ブワッと生暖かい風が、わたしたちのあいだを拭きぬけた。
紫色の花びらが、風のなかをぐるぐると舞いながら、飛んでいく。
「うわ、すごい風」
「これは、紫陽花の花びら……」
レンゲが、ぎゅっと眉間にシワを浮かべ、わたしを抱き寄せた。
ばさり、と何かがレンゲのおしりから飛び出した。
腰に巻いていたストールが、しっぽの勢いのせいでズレてしまったみたいだ。
「ちょっと、レンゲ……しっぽが」
レンゲのしっぽの毛が、逆立っている。
これは猫が、攻撃態勢に入っているサイン。
「あれー? これって、猫のしっぽ?」
ま、まずい。
レンゲのしっぽを、誰かに見られた!
「……誰だ」
レンゲが、「フシャア……」と、牙を見せつけながら、うなり声をあげる。
「猫のしっぽ。いいねえ。人間は、ふわふわしたものが大すきなんでしょ?」
声がしたほうを振り返る。
真っ黒なスーツを着たお兄さんが電柱に肘をかけ、怪しい笑顔をたたえていた。
お兄さんは、シルバーのネックレスやブレスレット、ピアスやリングをつけていた。
風にゆれるたびに、アクセサリーがジャラジャラと音をたてている。
金色の瞳がまるで、獲物を狩るときの肉食獣みたいに見え、わたしはゾッと背筋を震わせた。
お兄さんは、黒く塗られた短い爪をいじりながら、くちびるの端を吊りあげた。
「ぼくはね、この爪をとても大事にしているんだ。だから、ネイルコーティングはかかせない。見て、きらきらしてるでしょう? 特別なエキスが入ったポリマーを使ってるんだ」
「は、はあ……」
「カラスはね、器用にクチバシを使う。クルミだって、コインだって、クチバシでくわえることができるんだ。クチバシを使って、人間のように道具を作ることだってできるんだよ」
「そうなの? すごい!」
すると、お兄さんは嬉しそうに、ほほ笑んだ。
「カラスのすごさがわかるだなんて、きみはとってもいい人間だね」
レンゲが、わたしをお兄さんから遠ざけるように、身を乗り出した。
お兄さんは、ギザギザした歯列を見せながら、空を指さす。
「見てごらん。ほら」
空に、黒いものが、ぶわりと飛び散っている。
これ――カラスの大群だ。
大量のカラスたちが、わたしたちの頭上に集まって来ていた。
「なんで、こんなにカラスが……!」
大量の紫陽花の花びらが、ひらひらと舞っている。
黒と、紫が、視界を飛び回っていて、まるで、ここだけ異次元みたいだ。
「すごいでしょ。ぼくのちから。褒めてくれていいんだよ」
「カラスの大群……。まさか、あなた……ナズナ?」
お兄さんは、恍惚とした表情で、まぶしそうに目を細め、パチンと指を鳴らした。
「ピンポーン。大正解」
すると、まばたきをした瞬間、カラスの大群と紫陽花の花びらたちは、消えてなくなってしまった。
「え、ええっ? 消えちゃった!」
「ああ! きみ、いい反応だなあ!」
いつのまに距離を詰められたのか、お兄さんが高揚したようすで、わたしの両手を取った。
ぶんぶんと手を振りながら、目を輝かせ、鼻先を擦りそうなほどに顔を近づけられる。
「ねえ! きみ、ぼくの専属のお客さんになってくれない?」
「お、お客さん? わたしが?」
「きみみたいな素直な子が、ぼくの成長には必要――ぐえっ!」
首を絞められたカラスみたいな声がした。
手が解放されたかと思うと、レンゲがお兄さんに、手刀をくらわせていた。
「いったあ。何すんねん!」
さっきまで、紳士的だったお兄さんのしゃべり方が、変わっている。
チョップされた頭をさすりながら、涙目でレンゲに抗議している。
「大正解だと? お前は、カラスじゃないだろう。つまり、ナズナじゃない」
「ええ! 違うの?」
びっくりしっぱなしのわたしに、お兄さんが苦笑いをした。
「お前、キノ・キランだな。それも、ルナール・キノ……アカギツネだ」
「げっ。嘘やろ。なんで、わかったんっ?」
動揺したようすで、お兄さんは、あわてふためく。
「相手に幻術をかけるとき、出しすぎた妖力のあまりが花びらとなって出てしまう、『花のでがらし』……幻術の失敗例だな。おれたちが、キノ・キランのことをよく知らないと思って、からかってやろうと思ったんだろうが、甘かったな。これくらいは、予習済みだ」
「ちっ、おもしろないやっちゃのお」
黒スーツのお兄さんは、ふてくされたようにその場に座りこみ、くちびるを尖らせた。
スーツジャケットの内側から、キセルを取り出し、ぷかぷかと吸いはじめる。
「おい。おれのマスターの前で、キセルを吸うとは。いい度胸だな?」
わたしに煙を嗅がせないよう手で仰ぎながら、ぴしゃり、とレンゲがいさめると、お兄さんは目をキツネのように吊あげた。
「これは、ヨモギや! 香りかいでみ」
レンゲは警戒するように、すんすんとキセルのにおいを嗅ぐ。
「……たしかに。なんで、ヨモギなんて吸っている?」
「ええ香りじゃろがい」
お兄さんは不満そうに、けむりを輪っかを吐き出した。
レンゲは腕を組み、しゃがんでいるお兄さんを見おろした。
「それで? 誰なんだ、おまえは」
「はあ~。偉そうやなあ、きみ。ぼくは……仲間には、モクレンなんて呼ばれとる。勝手によろしゅうしたってや」
のんびりとした口調でいう、モクレン。
「なんか、さっきと全然ちがう」
不服そうにいうわたしに、モクレンはへらへらと、キセルをふかす。
「さっきのはなあ、営業スマイルゆうんや。商売や、商売」
「商売……?」
「キノ・キランは、ほとんどが人間社会で生きとる。ぼくらキツネはな、幻術つこうて、ゼニかせぐんよ」
「人をだましてお金をかせいでるってこと?」
ジトッと、モクレンをねめつけると、モクレンは、あわてて首をふった。
「まてまて。幻術ゆうたやろ。つまりな、ショーってことや。きみらも、さっき見たやろ。あれが、ぼくのショーや」
「あれが……?」
ショーだっていわれると、そうなのかもしれないけど。
「つまり、おまえは未熟な証拠である『花のでがらし』をショーの一部に利用しているってことか。さすが、キツネ。小賢しいな」
レンゲの一言に、グッと息をつまらせるモクレン。
「あ、ああいうんでもなあ、キレイやっていうて、喜んでくれる人間もおるんよ!」
叫んだ拍子に、モクレンの頭のてっぺんから、ぴょこんと大きな三角耳が飛び出した。
そこから、ぱらりと紫色の花びらが散らばる。
「うおわ!」
あわてて頭をおさえた、モクレン。
とたん、キセルが足元を落としてしまい、カランと乾いた音が鳴った。
「レンゲ。あれって」
「そこにあるものを、ないように見せるのも、幻術のひとつだ。動揺して、幻術の効果がブレてしまったようだな」
わたしは、キセルを拾ってやり、モクレンにそっと差し出した。
「モクレンのショー、応援するよ。わたしのすきな花びらを出してくれたら、次も見に行ってあげる」
モクレンが、パッと顔をあげる。
「……花、なにがすきなん?」
「菜の花は、すきだよ。菜の花畑を見ると、元気が出るんだ~」
「……へえ」
そして、ニカッと笑うと、黒スーツに散っていた花びらをパッパッとはらう。
頭の上の三角耳が、ゆらっと揺らめいたかと思うと、幻のようにスウッと消えていく。
気づけば、モクレンは最初に出会ったときの、自信たっぷりの表情に戻っていた。
「きみの隣のやつも、キノ・キランなんやろ? 猫のしっぽ、生やしとるもんね」
やっぱり、モクレンにはバレてるよね。
モクレンもキノ・キランだったから、さっきの反応もうなずける。
「ふたり、ナズナさまのところに行きたいんやろ。案内したるわ」
「その気なら、あんなショーなんかしてないで、さっさと案内してくれればいいだろう」
レンゲのぶっきらぼうな言葉に、モクレンはハア、と息をついた。
「情緒のない猫やね。きみたち、名前なんちゅうの」
答えないレンゲに、わたしが代わりに答えた。
「えと、うちの猫のレンゲです」
「あんがとさん。きみの名前は?」
「わたしは、チカナ」
とたん、レンゲがまた、わたしをぐいっと抱きよせた。
また警戒態勢のレンゲに、わたしは飼い主としての立場を思い出す。
「レンゲ。だめだよ、そんな態度」
「飼い猫は、テリトリーにうるさいなあ」
「ごめんね。モクレン」
モクレンはへらっと笑うと、わたしたちの一歩前に立った。
「ナズナさまの店はこっちや」
モクレンが指差す先に、薄明かりが見えた。
「ナズナさまは、変わっとるからなあ。のんびりと構えとるとええよ」
レンゲがいってたよね。
ナズナさまは、変わり者で有名なんだって。
ハシボソガラスのキノ・キラン、コローネ・キノか。
どんなすがたなんだろう。
薄明かりが近くなるにつれ、わたしの胸がざわざわと騒ぎはじめた。
「きみたち、ナズナさまの店がなんか、知っとるか」
「えーと。表向きはキノ・キラン専用カフェ。でも、キノ・キランの保護もやってるんだよね。アネモネに聞いたよ」
「ああ、あのいけすかない猫な」
モクレンも、アネモネのこと知ってるんだ。
「まあ、その通りや。この町だけじゃない。遠くの町まで、キノ・キランを保護しに行っとるやつらもいる。そして、それをまとめとるのが、ナズナさまや」
「モクレンも、保護活動してるの?」
「まあな。まだまだやけどな〜」
モクレンが足を止めた。
三日月通りの、三番目の電柱。
そして、赤いポスト……いや。『赤いヤギ』が、裏道の入口に立っている。
「や、ヤギだ! しかも、赤いよ……!」
「シェーヴル・キノくんや。名前は……なんやったかな?」
モクレンが「はて?」と、のんきに首をかしげる。
すると、赤いヤギが、目をカッと開いたかとおもうと、ものすごい早口で、しゃべりはじめた。
「白ヤギさんからお手紙ついて、黒ヤギさんが読まずに食べる。そして、私は赤いヤギ。読まれることなく食べられる、二人の手紙をえんえんと届け続けた悲運のヤギ! それが、わたくし。赤ヤギのヤドリギ! 十六夜堂のポストマンです!」
しゃ、しゃべった。
つまり、このヤドリギっていうヤギさんは、キノ・キランなのかな。
すがたは、ヤギのままだけど。
「郵便配達イコール、ヤギって理由だけで、ナズナさまから十六夜堂への案内係に任命された、ハイテンションヤギくんや」
「ポストっていうのは、赤いのヤギさんのことだったんだね……」
「裏通りの入口に、このヤドリギがおらんと、十六夜堂はぜったい見つからんようになっとる。人間には、そもそもヤドリギのすがたすら見つからんように、ナズナさまの幻術がかかっとるしな」
「十六夜堂への客を、ナズナさまのもとまで届ける。それが、わたくしの役目です!」
ヤドリギが得意げに、くいっと長い首を持ち上げた。
「さあ、どうぞ。奥の細道へとおいでください! 十六夜堂で、ゆっくりとくつろいでいってくださいね」
さっきまで、暗がりでよく見えなかった十六夜堂への裏道が、ヤドリギの一言で、ぽうっと月の薄明かりに照らされた。
「ナズナさまとヤクモさんが……お待ちですよ!」