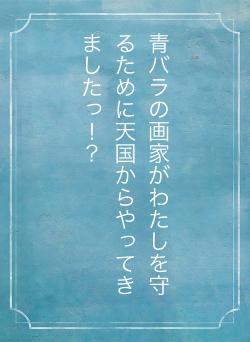■
朝。夢だったのかな、なんて思いながら、夢のなかから覚めた。
でも、昨夜のことは、鮮明に思い出せた。
ヤクモとシロツメ。キノ・キラン。十六夜堂。
悶々としながら、わたしはパジャマから、洋服に着替えた。
のそのそと、一階のリビングまで行くと、レンゲのお気に入りのクッションが見えた。
ふつうの猫よりも大きいレンゲの巨体が、クッションの上で、ふんわりと丸くなっている。
クッションの上に、クッションが乗っているみたいだと思って、わたしはつい、ニヤニヤしてしまう。
いつもどおりに、身をかがめて、レンゲの顔を覗きこんだ。
「おはようっ」
「くるるるるる」
メインクーン特有の鳴き声での、あいさつ。
こうやって見ると、やっぱり昨夜のは夢で、レンゲはキノ・キランじゃなくて、普通の猫だった――
「なにを、ニヤニヤしてる?」
「っへ?」
あたらめて聞くと、レンゲの声は、同級生に比べて、低い。
楽器のチェロみたいな、きれいな音色だと思った。
メインクーンの大きなからだに似合う、堂々とした口調に、心臓がドキンと跳ねた。
「や、やっぱり、レンゲ……しゃべれるようになったんだね」
「昨日さんざん、いっしょにしゃべっただろうが。寝ぼけたのか。ニヤニヤしているのは、そのせいか?」
「ち、違うよ! もう……顔洗ってくる!」
洗面所で、ヘアバンドをつけ、洗顔しながらも、心臓はバクバクとうるさかった。
夢じゃない。
レンゲと話してる。
「うちの猫と、おしゃべりできるようになったんだ! やばい、最高すぎる――!」
あまりの嬉しさに、朝の支度の時間は、あっという間に過ぎてしまった。
走らないと、STに間にあわない。
ダッシュするハメになってしまったわたしは、朝ごはんを急いでたいらげ、玄関から飛び出した。
自分の席である、窓際の一番後ろへと駆けこむ。
まだ、先生は来ていなかったようで、喉につまった息を長く吐き出した。
隣にいたヤクモが、いじわるそうに見あげてくる。
「チーカナ。おはよう」
「ヤクモ……おはよ」
昨夜のことを気にしているのは、わたしだけらしく、ヤクモはいつも通りだ。
リュックからペンケースやらノートを出していると、ヤクモが近づいてきて、声をひそめた。
「今日、忘れるなよ」
「え?」
「十六夜堂で、待ってる」
一気に、昨日の光景がフラッシュバックする。
耳を抑えながら、目を見開くわたしに、ヤクモは気にする素振りもなく、再び席に着いた。
なんだか、わたしばっかり振り回されてない?
早く帰って、レンゲのブラッシングしたいなあ。
窓の外、いつもと変わらない速度で流れている雲が、うらやましくおもえた。
■
家に帰ると、レンゲは猫のすがたのまま、朝とまったく同じ位置でゴロゴロしていた。
わたしはもう我慢できないとばかりに、さっそく、ふわふわの雲みたいな毛をブラッシングしはじめた。
はあ~! 癒される。この時間だけが、生きがいだよ。
「レンゲ。どう? かゆいところとか、ない?」
「毎回、その質問をしてくるが、なんなんだ? 必要なのか、それ」
ありゃ、そっか。美容室に行ったことがないレンゲには、このやりとり、まったく伝わっていなかったんだ。
これも、愛猫とおしゃべりができるようにから、わかったことだよね。
わたしって、幸せ者だなあ。
でも……と、今朝のヤクモの言葉を思い出す。
「ねえ、今日……十六夜堂に行くんだよね。レンゲ、なにか知ってる?」
「ああ……あそこか」
レンゲ、なんだか気乗りかんじ? どうしたんだろう。
「キノ・キランになる前から、知ってる。なぜなら、キノ・キランじゃない動物たちのあいだでも、十六夜堂は有名だからな」
「そうなんだ? 何の店なの?」
ブラシについた、ふわふわの毛をとりのぞく。
「さあな。だが、店主がキノ・キランのなかでも変わり者で有名らしい」
「変わり者って、どんなふうなの?」
「そこまでは、知らないな。十六夜堂、気になるのか?」
「うん。ヤクモがいっていたこと、気になってるんだよね。キノ・キランを保護してるって話」
わたしは、ブラッシングする手を止めることなく、いった。
レンゲは、黙って聞いてくれている。
「わたしたちで役に立てること、ないかな? せっかく、こうしてレンゲと話が出来るようになったんだもん」
「……はあ。なるほどな」
ぶん、と長いシッポを振って、レンゲは深く息をついた。
「――わかった。おまえを十六夜堂に連れていけばいいんだろう」
「あれ。レンゲ、怒ってる?」
「チカナには、怒っていない」
「じゃあ、何に怒ってるの……?」
「さあな」
そっぽを向いてしまった、レンゲ。
猫の気まぐれは、キノ・キランになっても、変わらないみたい。
「ブラッシングが終わったら、十六夜堂に連れていく。人のすがたでな」
「えっ?」
「なんだ。不満か」
「だって、あのすがたは目立つもん! ダメだよ」
猫耳に、さらに大きなしっぽも付いているキノ・キランのすがた。
外を歩けば、注目の的になること、間違いなしだよ。
「おれは、メインクーンだ。目立つのは慣れてる」
「そういう問題じゃないよ!」
「人間の服でうまく隠せばいいだろう。おまえがよく頭に乗せてる、ごはんのうつわみたいなやつもいるな」
「えーと、帽子のこと……?」
たしかに、耳は帽子で隠れるかも。
「そういえば、昨夜、レンゲが来ていた服って、どうしたの? 夜だったからよく見えなかったけど、真っ黒い服を着てたよね」
「あれは、あの部屋にあったものだ。由奈が誠二に、ふざけて買ってあげてたやつだな。着てないから、借りてもいいだろうと思った」
レンゲがしっぽで指示したのは、一階の納戸だ。
由奈は、わたしのお母さんで、誠二はわたしのお父さんのこと。
そっか。今年のお正月に、お母さんが買った、メンズ服の福袋。
あまりにも、お父さんの好みに合わなかったから、納戸の奥に封印されたんだっけ。
「じゃあ、今日もあれを着てみようか。しっぽと、耳をうまく隠せるかどうか、確かめないとね。服は、どうしたの?」
「同じ場所に、置いてある」
ブラッシンクが終わったので、さっそくレンゲと納戸に行った。
奥にしまわれた福袋をレンゲが、フンフンとにおいをかぎはじめる。
すると、ポンと煙のようなものが弾け、気づけばレンゲは、キノ・キランのすがたになっていた。
明るいところで、このすがたを見るのは初めてだ。
あらためて見てみても、雑誌や動画サイトで見るどんなイケメンよりも、レンゲはカッコよかった。
飼い主フィルターがかかってるのかな?
「あれ。レンゲ、いつのまに服着たの?」
英語ロゴの黒Tシャツに、黒のベルトパンツをまとったレンゲは、平然としたようすで、服のにおいをかいでいる。
「裸で、おまえの前に出るわけないだろう」
「……あっ」
「人間のすがたになりきる前に、ちゃんと服を着たんだ」
どんだけ超スピード着替え?
「なんで、猫のくせに服の着方を知ってるの?」
「毎日、おまえを見ていれば、着方くらい覚える」
なるほど。さすがの観察眼……。
そうとわかれば、猫耳としっぽを隠す方法を考えなくちゃ。
わたしは、レンゲが差し出した、福袋のなかから、使えそうなものを探した。
チェックの厚手のストールがあったので、レンゲの腰に巻いて、まずはシッポを隠した。
次に、黒のバゲットハットで、猫耳を隠す。
「うん。こんなもんかな」
わたしは、さらにカッコよくなったレンゲに大満足。
だけど、レンゲは、しきりに自分のにおいをかいでいた。
「レンゲ。におい、気になる?」
「……おれじゃないにおいがする。落ち着かない?」
すると、レンゲは突然、ぎゅうっとわたしに抱き着いてきた。
大きい猫、ではなくて、自分よりも背の高い男子にハグされて、カチンコチンに固まってしまう。
「どどど、どうしたの。レンゲ!」
「この服に、チカナのにおいをつければ、多少は落ち着くだろう。ちょっと待て」
「は……はい……」
「おまえは、おれのマスターだ。おれのにおいをしっかりさせてくれないと、困る」
しばらく、レンゲにぎゅうぎゅうと抱き着かれ、わたしはにおい付けの作業に集中することにした。
これも、うちの猫のためだ。
なぜか、心臓はうるさいぐらいに鳴っているけれど……。
朝。夢だったのかな、なんて思いながら、夢のなかから覚めた。
でも、昨夜のことは、鮮明に思い出せた。
ヤクモとシロツメ。キノ・キラン。十六夜堂。
悶々としながら、わたしはパジャマから、洋服に着替えた。
のそのそと、一階のリビングまで行くと、レンゲのお気に入りのクッションが見えた。
ふつうの猫よりも大きいレンゲの巨体が、クッションの上で、ふんわりと丸くなっている。
クッションの上に、クッションが乗っているみたいだと思って、わたしはつい、ニヤニヤしてしまう。
いつもどおりに、身をかがめて、レンゲの顔を覗きこんだ。
「おはようっ」
「くるるるるる」
メインクーン特有の鳴き声での、あいさつ。
こうやって見ると、やっぱり昨夜のは夢で、レンゲはキノ・キランじゃなくて、普通の猫だった――
「なにを、ニヤニヤしてる?」
「っへ?」
あたらめて聞くと、レンゲの声は、同級生に比べて、低い。
楽器のチェロみたいな、きれいな音色だと思った。
メインクーンの大きなからだに似合う、堂々とした口調に、心臓がドキンと跳ねた。
「や、やっぱり、レンゲ……しゃべれるようになったんだね」
「昨日さんざん、いっしょにしゃべっただろうが。寝ぼけたのか。ニヤニヤしているのは、そのせいか?」
「ち、違うよ! もう……顔洗ってくる!」
洗面所で、ヘアバンドをつけ、洗顔しながらも、心臓はバクバクとうるさかった。
夢じゃない。
レンゲと話してる。
「うちの猫と、おしゃべりできるようになったんだ! やばい、最高すぎる――!」
あまりの嬉しさに、朝の支度の時間は、あっという間に過ぎてしまった。
走らないと、STに間にあわない。
ダッシュするハメになってしまったわたしは、朝ごはんを急いでたいらげ、玄関から飛び出した。
自分の席である、窓際の一番後ろへと駆けこむ。
まだ、先生は来ていなかったようで、喉につまった息を長く吐き出した。
隣にいたヤクモが、いじわるそうに見あげてくる。
「チーカナ。おはよう」
「ヤクモ……おはよ」
昨夜のことを気にしているのは、わたしだけらしく、ヤクモはいつも通りだ。
リュックからペンケースやらノートを出していると、ヤクモが近づいてきて、声をひそめた。
「今日、忘れるなよ」
「え?」
「十六夜堂で、待ってる」
一気に、昨日の光景がフラッシュバックする。
耳を抑えながら、目を見開くわたしに、ヤクモは気にする素振りもなく、再び席に着いた。
なんだか、わたしばっかり振り回されてない?
早く帰って、レンゲのブラッシングしたいなあ。
窓の外、いつもと変わらない速度で流れている雲が、うらやましくおもえた。
■
家に帰ると、レンゲは猫のすがたのまま、朝とまったく同じ位置でゴロゴロしていた。
わたしはもう我慢できないとばかりに、さっそく、ふわふわの雲みたいな毛をブラッシングしはじめた。
はあ~! 癒される。この時間だけが、生きがいだよ。
「レンゲ。どう? かゆいところとか、ない?」
「毎回、その質問をしてくるが、なんなんだ? 必要なのか、それ」
ありゃ、そっか。美容室に行ったことがないレンゲには、このやりとり、まったく伝わっていなかったんだ。
これも、愛猫とおしゃべりができるようにから、わかったことだよね。
わたしって、幸せ者だなあ。
でも……と、今朝のヤクモの言葉を思い出す。
「ねえ、今日……十六夜堂に行くんだよね。レンゲ、なにか知ってる?」
「ああ……あそこか」
レンゲ、なんだか気乗りかんじ? どうしたんだろう。
「キノ・キランになる前から、知ってる。なぜなら、キノ・キランじゃない動物たちのあいだでも、十六夜堂は有名だからな」
「そうなんだ? 何の店なの?」
ブラシについた、ふわふわの毛をとりのぞく。
「さあな。だが、店主がキノ・キランのなかでも変わり者で有名らしい」
「変わり者って、どんなふうなの?」
「そこまでは、知らないな。十六夜堂、気になるのか?」
「うん。ヤクモがいっていたこと、気になってるんだよね。キノ・キランを保護してるって話」
わたしは、ブラッシングする手を止めることなく、いった。
レンゲは、黙って聞いてくれている。
「わたしたちで役に立てること、ないかな? せっかく、こうしてレンゲと話が出来るようになったんだもん」
「……はあ。なるほどな」
ぶん、と長いシッポを振って、レンゲは深く息をついた。
「――わかった。おまえを十六夜堂に連れていけばいいんだろう」
「あれ。レンゲ、怒ってる?」
「チカナには、怒っていない」
「じゃあ、何に怒ってるの……?」
「さあな」
そっぽを向いてしまった、レンゲ。
猫の気まぐれは、キノ・キランになっても、変わらないみたい。
「ブラッシングが終わったら、十六夜堂に連れていく。人のすがたでな」
「えっ?」
「なんだ。不満か」
「だって、あのすがたは目立つもん! ダメだよ」
猫耳に、さらに大きなしっぽも付いているキノ・キランのすがた。
外を歩けば、注目の的になること、間違いなしだよ。
「おれは、メインクーンだ。目立つのは慣れてる」
「そういう問題じゃないよ!」
「人間の服でうまく隠せばいいだろう。おまえがよく頭に乗せてる、ごはんのうつわみたいなやつもいるな」
「えーと、帽子のこと……?」
たしかに、耳は帽子で隠れるかも。
「そういえば、昨夜、レンゲが来ていた服って、どうしたの? 夜だったからよく見えなかったけど、真っ黒い服を着てたよね」
「あれは、あの部屋にあったものだ。由奈が誠二に、ふざけて買ってあげてたやつだな。着てないから、借りてもいいだろうと思った」
レンゲがしっぽで指示したのは、一階の納戸だ。
由奈は、わたしのお母さんで、誠二はわたしのお父さんのこと。
そっか。今年のお正月に、お母さんが買った、メンズ服の福袋。
あまりにも、お父さんの好みに合わなかったから、納戸の奥に封印されたんだっけ。
「じゃあ、今日もあれを着てみようか。しっぽと、耳をうまく隠せるかどうか、確かめないとね。服は、どうしたの?」
「同じ場所に、置いてある」
ブラッシンクが終わったので、さっそくレンゲと納戸に行った。
奥にしまわれた福袋をレンゲが、フンフンとにおいをかぎはじめる。
すると、ポンと煙のようなものが弾け、気づけばレンゲは、キノ・キランのすがたになっていた。
明るいところで、このすがたを見るのは初めてだ。
あらためて見てみても、雑誌や動画サイトで見るどんなイケメンよりも、レンゲはカッコよかった。
飼い主フィルターがかかってるのかな?
「あれ。レンゲ、いつのまに服着たの?」
英語ロゴの黒Tシャツに、黒のベルトパンツをまとったレンゲは、平然としたようすで、服のにおいをかいでいる。
「裸で、おまえの前に出るわけないだろう」
「……あっ」
「人間のすがたになりきる前に、ちゃんと服を着たんだ」
どんだけ超スピード着替え?
「なんで、猫のくせに服の着方を知ってるの?」
「毎日、おまえを見ていれば、着方くらい覚える」
なるほど。さすがの観察眼……。
そうとわかれば、猫耳としっぽを隠す方法を考えなくちゃ。
わたしは、レンゲが差し出した、福袋のなかから、使えそうなものを探した。
チェックの厚手のストールがあったので、レンゲの腰に巻いて、まずはシッポを隠した。
次に、黒のバゲットハットで、猫耳を隠す。
「うん。こんなもんかな」
わたしは、さらにカッコよくなったレンゲに大満足。
だけど、レンゲは、しきりに自分のにおいをかいでいた。
「レンゲ。におい、気になる?」
「……おれじゃないにおいがする。落ち着かない?」
すると、レンゲは突然、ぎゅうっとわたしに抱き着いてきた。
大きい猫、ではなくて、自分よりも背の高い男子にハグされて、カチンコチンに固まってしまう。
「どどど、どうしたの。レンゲ!」
「この服に、チカナのにおいをつければ、多少は落ち着くだろう。ちょっと待て」
「は……はい……」
「おまえは、おれのマスターだ。おれのにおいをしっかりさせてくれないと、困る」
しばらく、レンゲにぎゅうぎゅうと抱き着かれ、わたしはにおい付けの作業に集中することにした。
これも、うちの猫のためだ。
なぜか、心臓はうるさいぐらいに鳴っているけれど……。