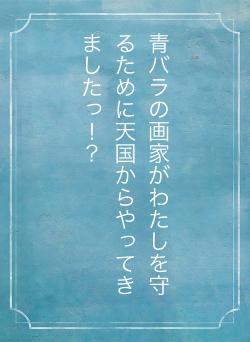ある日、十六夜堂の引き戸が開けられた――たったの数センチだけ。
「みゃーお」
小さな、鳴き声。
すりすりと、わたしの足元に頭をこすりつけてきているのは、黒い子猫だった。
ここは、キノ・キラン専用カフェ・十六夜堂。
ヤドリギさんに案内されない限り、ここにはキノ・キランしか来られない。
「あなた、キノ・キランなの?」
――ガラッ
ゆっくりと戸を開けたのは、ハコベラさんだった。
「ハコベラさん、こんにちは」
「こんにちは。ゲンブのちからが、ようやく返ってきました」
嬉しそうに微笑むハコベラさんの腕のなかには、もう一匹の子猫がいた。
その子猫が、ハコベラさんの腕の中から飛び降り、黒猫とじゃれあいはじめた。
とっても、仲がいいみたいだ。
「この子たち、生まれながらにして、キノ・キランだったんです。お互いの絆があればきっと、すばらしいキノ・キランになれるはずだって、月が祝福を授けてくれたんでしょうね」
おわり
「みゃーお」
小さな、鳴き声。
すりすりと、わたしの足元に頭をこすりつけてきているのは、黒い子猫だった。
ここは、キノ・キラン専用カフェ・十六夜堂。
ヤドリギさんに案内されない限り、ここにはキノ・キランしか来られない。
「あなた、キノ・キランなの?」
――ガラッ
ゆっくりと戸を開けたのは、ハコベラさんだった。
「ハコベラさん、こんにちは」
「こんにちは。ゲンブのちからが、ようやく返ってきました」
嬉しそうに微笑むハコベラさんの腕のなかには、もう一匹の子猫がいた。
その子猫が、ハコベラさんの腕の中から飛び降り、黒猫とじゃれあいはじめた。
とっても、仲がいいみたいだ。
「この子たち、生まれながらにして、キノ・キランだったんです。お互いの絆があればきっと、すばらしいキノ・キランになれるはずだって、月が祝福を授けてくれたんでしょうね」
おわり