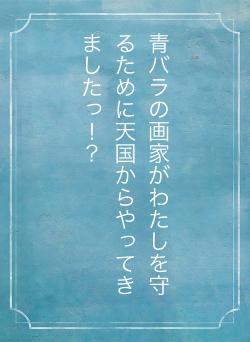掛け軸のあった部屋を出ると、あたりはすっかり、ウキネさまの降らせた雪でおおわれていた。
幽霊に取り憑かれたキノ・キランたちも、いつのまにかすがたを消している。
でも、ウキネさまがあのキノ・キランたちを傷つけることはないはず。
わたしたちとにかく、霜月の宿を飛び出し、解決策を考えることにした。
宿を出ると、ハコベラさんが近くの草影に隠れ、わたしたちを待ってくれていた。
掛け軸を見つけ、そこに書かれていたことまでを説明し、ハコベラさんには先に逃げてもらう。
もう、後戻りできないところまで来ているんだと、あらためて感じる――。
「ウキネさま……アネモネ」
いつのまにふたりが、霜月の宿の前で、わたしたちを見すえていた。
「わがままな人間だった幽霊たちを使い、この世は霜月の宿が支配する。完全なるキノ・キランたちのためだけの世界を作るため、邪魔だてすることは許さん」
ウキネさまは……人間がきらいなんだ。
だから人間だった幽霊をお金で釣って、キノ・キランたちを集めていた。
「そんなこと……間違ってる。どっちかが、どっちかを支配するなんて世界、かなしいよ!」
「うるさい!」
ウキネさまが、アネモネを走らせる。
「わたしが――封印されたのは、わたしの仲間を守ろうとしただけ! あのとき、病から治らない動物たちはたしかにいた。それを人間たちは……食糧難だからって、捨てようとした! だからわたしは――!」
わたしを守るため、レンゲが飛び出した。
するどい爪がアネモネに届く前に、レンゲは空間を削る。
レンゲが裂いた空間が、ウキネさまの正面の空間をジッパーのように裂き、メインクーンの爪が線を描く。
意表をつかれたウキネは、その白い肌に、一筋の血をツーっと垂らしていた。
「よくも、ウキネさまにキズを!」
アネモネの紫の瞳が、あやしく光る。
「ですが、まだです。あなたの能力はもう見切りました。もうその爪をウキネさまのもとへは……」
「誰が、もう一度ウキネを引っかくって?」
今度はシロツメが、アネモネの頭上を飛び越え、ウキネさまへと飛びかかる。
「っく! ちょこまかと……」
アネモネがしぼり出すような声で叫んだ。
シロツメが走りながら、ウキネさまに向かって、あるものを投げつけた。
飛んできたそれを受け取ったウキネさまは、開いた手のひらにそったものを見て、悲鳴をあげる。
「ひいいいいっ! これは――!」
ウキネさまに投げつけたもの、それは一粒の柿の実のタネだった。
掛け軸の裏の戸に、隠されていたものの正体だ。
掛け軸には、ウキネさまは柿の木の下に封印されたと書いてあった。
おそらくこれは、その柿の木の実のタネだ。
「あの部屋には宿の結界以外に、もう一枚よけいに結界を張っていたはずじゃ……。誰が解いたというんじゃ! お前か、アネモネ!」
「ち、違います、ウキネさま。わたくしが、そのようなことをするはずがありません!」
「よけいな結界……? じゃあ、それをやったのは、わたしかもしれませんね」
二人の言い争いに入ったのは、さっき逃げてもらったはずの、庭師のハコベラさんだった。
ハコベラさんは、その手に大きなシャベルを持っていた。
「どういうことですか?」
わたしがたずねると、ハコベラさんはシャベルを地面にサクッと突き立てた。
「この建物の『ある一角』を三角形で結ぶかたちで、霊力の高い菊の花が植えられていたんです。だから、別の場所に植え替えちゃいました」
「そそそ、それは貴重品の存在を隠すための結界じゃ! だから、こやつらに掛け軸を見つけられてしまったんじゃ! 庭師の分際でなんてことを」
ハコベラさんの話にウキネさまは、わなわなと怒りで肩を震わせている。
そのとき、ウキネさまがにぎっていた柿のタネが、ぐぐぐっと大きくなる。
一気にふくれあがったかと思うと、そのままウキネさまのからだに巻きついていく。
アネモネが、「ウキネさま!」と悲鳴のように叫ぶ。
「ななな、今度はなんじゃ!」
「わるい子だーれだ」
イタズラが成功した子どものように、ニヤニヤするシロツメ。
「ぼくの植物を成長させるちからも、成長しているんだ。だから、こんな使い方もできるようになったんだよ~」
「この……やめろ、やめんか!」
一気に成長していく柿は、芽からシュルシュルと背を伸ばし、すでに若い木になっている。
思い切り身をよじり、逃げようとするウキネ。
しかし、柿の成長は止まらない。
アネモネが、シロツメに飛びかかった。
「おやめ! この不敬者が!」
瞬間、シロツメの前に黒い影が飛んでくる。
アネモネの爪を止めたのは、モクレンのキセルだった。
「もう、やめえ。アネモネ」
「できそこないのルナールが! 出がらししか散らさない、不完全なアカギツネ !」
「おまえは上品なくせに、昔からわるぐちが達者やな」
ふわりと、モクレンのキセルから香ばしいにおいが漂う。
アネモネはハッとして、鼻をひくつかせた。
「これ……!」
においに気づいたウキネも、きょろきょろとあたりを見渡している。
モクレンはゆっくりと、煙が流れるように答えた。
「どんぐりの実に柿の皮を巻いたもの、おまえのマスターが好きなやつや」
アネモネの息をのむ音が、鮮明に聞こえた。
「皮肉なもんやな。柿の木に封印されていたのに、好きなにおいがこれとは」
スキが生まれたウキネさまを、レンゲの爪が狙っている。
柿の木に捕らわれたウキネさまに、もう逃げ場はなかった。
「ウキネさまっ! 逃げてっ」
「――アネモネ。まだ、心配してくれるか……こんな、わたしを」
あたりに、また極寒の雪が吹きすさぶ。
これほどまでの寒さでは、これ以上柿の木が成長することは出来ない。
シロツメの息も、乱れはじめている。
「あー、ダメだ。こんな若い木じゃあ、これ以上捕まえておくことはできないよ」
そんな、ここまで来たのに……。
もう、あきらめるしかないのかな?
ゴオオオオオ……。
その音は、一面の雪を溶かす炎だった。
目の前が真っ白から、鮮やかな赤に変わる。
しかし、その炎は熱くない、あたたかな炎だった。
命を育むような、優しい炎。
「やっと、来よったか」
モクレンがホッとしたように、息をついた。
「ナズナさま――!」
ナズナさまは背中の黒い羽をはばたかせ、ゆっくりと空から降りてきた。
背中に穴を開けた羽専用の着物が、炎で照らされ鮮やかに彩られている。
「モクレン。みんな、よう頑張った。ハコベラの準備も整った。返すときが来たようじゃ」
「ハコベラさん……?」
首を傾げるわたしに、ハコベラさんが憂いを帯びた表情をする。
「ゲンブのちからは、もともとは、わたしのものなんですよ」
それを聞いて、ヤクモは「なるほど」と、うなった。
「『三日月祭のはじまりの猫』がウキネなら、ゲンブのちからを持っているのは不自然だ。だが、それがもともと、ハコベラさんのものだったというのなら、納得できるよな」
ナズナさまはカラスのキノ・キランだから、ヤタガラスのちから 。
ハコベラさんはカメのキノ・キランだから、ゲンブのちからを持てた。
「じゃあ、どうやってウキネはゲンブのチカラを?」
「奪われたのです」
わたしの質問に、ハコベラさんはうつむいた。
「ゲンブのちからには、命を生みだす能力があります。ウキネは、わたしからゲンブのちからを奪い取り、自分の魂を受け継ぐものを次々に生み出していきました」
「アネモネもそのひとり、なんだね」
わたしがいうと、ハコベラさんが続けた。
「ほんとうのウキネは、ただ『黒猫』のキノ・キランなのです」
「ウキネが、黒猫……」
「大らかで、甘えんぼう。人懐っこい、とても愛らしい猫でした」
「ハコベラさん、まるで見てきたみたいにいうんですね」
「ええ。わたしも、長生きですから……」
そのとき、シロツメが声をあげた。
「ヤクモ! ナズナさまの炎で、柿の木が成長しきった。これなら、封印できるよ!」
「おーい。こっちも限界近いでー」
アネモネとの戦いで、モクレンのキセルはボロボロになっていた。
「チカナ。ウキネはもう、吹雪を出すちからは残っていない」
柿の木の上から、レンゲが叫ぶ。
過去、ウキネさまを封じたときの呪文が書かれた和紙を広げる。
モクレンが、柿のタネといっしょに、手のひらに掴んでいたんだ。
わたしはそれを、一字一字噛みしめるように唱えた。
『おやすみなさい わたしたちの月の黒猫』
ぐぐぐ、と柿の木の幹が、ウキネを丸く包みこんだ。
布団のように柔らかく、そのからだを沈めていく。
ウキネの瞳が月の光に反射して、キラッと輝いた。
美しい紫色だった。
ウキネの瞳が眠りにつこうと、スウッと閉じていく。
「行かないでくださいまし! ウキネさま!」
アネモネが、柿の木のウキネのもとへと飛びあがった。
「わたくしもともに眠ります……。おやすみなさい、ウキネさま……」
ウキネの隣に寄り添う、アネモネ。
いっしょに眠るウキネとアネモネのすがたは、なかよくくっついて眠る、親子の猫のようにしか見えなかった。
柿の木はウキネとアネモネを包みこむと、金色の光を放った。
その光に思わず、目をつむる。
目を開いた時には、ウキネもアネモネも、柿の木もなくなっていた。
なんと、霜月の宿さえ影も、かたちもなくなっていた。
まわりに、幽霊に憑りつかれていたキノ・キランのみんなが倒れている。
次々に、目を覚ますキノ・キランたちは、何が起こったのかわからないとふしぎそうにいているけれど、とりあえず元気そうだ。
でも、なんとなく胸の奥がモヤっとする。
ウキネのことが、頭から離れない。
「チカナ。むずかしい顔をしているな」
「レンゲ。ありがとうね、戦ってくれて……」
「当たり前だ。いっただろう? おまえを守るのは、おれだと……」
すると、レンゲがわたしの頭を、そっと撫でてくれる。
「ふふ、いつもと違うね。いつもは、わたしが撫でてるから……あれ?」
ぽろぽろと、目から涙がこぼれてくる。
「な、何で……?」
「大丈夫だ。がんばったからだ」
わたしはしばらく、レンゲの胸で声を出さずに泣いた。
レンゲはいつまでもいつまでも、わたしの頭を撫でてくれていた。
「おまえががんばったから、涙が出るんだ」
幽霊に取り憑かれたキノ・キランたちも、いつのまにかすがたを消している。
でも、ウキネさまがあのキノ・キランたちを傷つけることはないはず。
わたしたちとにかく、霜月の宿を飛び出し、解決策を考えることにした。
宿を出ると、ハコベラさんが近くの草影に隠れ、わたしたちを待ってくれていた。
掛け軸を見つけ、そこに書かれていたことまでを説明し、ハコベラさんには先に逃げてもらう。
もう、後戻りできないところまで来ているんだと、あらためて感じる――。
「ウキネさま……アネモネ」
いつのまにふたりが、霜月の宿の前で、わたしたちを見すえていた。
「わがままな人間だった幽霊たちを使い、この世は霜月の宿が支配する。完全なるキノ・キランたちのためだけの世界を作るため、邪魔だてすることは許さん」
ウキネさまは……人間がきらいなんだ。
だから人間だった幽霊をお金で釣って、キノ・キランたちを集めていた。
「そんなこと……間違ってる。どっちかが、どっちかを支配するなんて世界、かなしいよ!」
「うるさい!」
ウキネさまが、アネモネを走らせる。
「わたしが――封印されたのは、わたしの仲間を守ろうとしただけ! あのとき、病から治らない動物たちはたしかにいた。それを人間たちは……食糧難だからって、捨てようとした! だからわたしは――!」
わたしを守るため、レンゲが飛び出した。
するどい爪がアネモネに届く前に、レンゲは空間を削る。
レンゲが裂いた空間が、ウキネさまの正面の空間をジッパーのように裂き、メインクーンの爪が線を描く。
意表をつかれたウキネは、その白い肌に、一筋の血をツーっと垂らしていた。
「よくも、ウキネさまにキズを!」
アネモネの紫の瞳が、あやしく光る。
「ですが、まだです。あなたの能力はもう見切りました。もうその爪をウキネさまのもとへは……」
「誰が、もう一度ウキネを引っかくって?」
今度はシロツメが、アネモネの頭上を飛び越え、ウキネさまへと飛びかかる。
「っく! ちょこまかと……」
アネモネがしぼり出すような声で叫んだ。
シロツメが走りながら、ウキネさまに向かって、あるものを投げつけた。
飛んできたそれを受け取ったウキネさまは、開いた手のひらにそったものを見て、悲鳴をあげる。
「ひいいいいっ! これは――!」
ウキネさまに投げつけたもの、それは一粒の柿の実のタネだった。
掛け軸の裏の戸に、隠されていたものの正体だ。
掛け軸には、ウキネさまは柿の木の下に封印されたと書いてあった。
おそらくこれは、その柿の木の実のタネだ。
「あの部屋には宿の結界以外に、もう一枚よけいに結界を張っていたはずじゃ……。誰が解いたというんじゃ! お前か、アネモネ!」
「ち、違います、ウキネさま。わたくしが、そのようなことをするはずがありません!」
「よけいな結界……? じゃあ、それをやったのは、わたしかもしれませんね」
二人の言い争いに入ったのは、さっき逃げてもらったはずの、庭師のハコベラさんだった。
ハコベラさんは、その手に大きなシャベルを持っていた。
「どういうことですか?」
わたしがたずねると、ハコベラさんはシャベルを地面にサクッと突き立てた。
「この建物の『ある一角』を三角形で結ぶかたちで、霊力の高い菊の花が植えられていたんです。だから、別の場所に植え替えちゃいました」
「そそそ、それは貴重品の存在を隠すための結界じゃ! だから、こやつらに掛け軸を見つけられてしまったんじゃ! 庭師の分際でなんてことを」
ハコベラさんの話にウキネさまは、わなわなと怒りで肩を震わせている。
そのとき、ウキネさまがにぎっていた柿のタネが、ぐぐぐっと大きくなる。
一気にふくれあがったかと思うと、そのままウキネさまのからだに巻きついていく。
アネモネが、「ウキネさま!」と悲鳴のように叫ぶ。
「ななな、今度はなんじゃ!」
「わるい子だーれだ」
イタズラが成功した子どものように、ニヤニヤするシロツメ。
「ぼくの植物を成長させるちからも、成長しているんだ。だから、こんな使い方もできるようになったんだよ~」
「この……やめろ、やめんか!」
一気に成長していく柿は、芽からシュルシュルと背を伸ばし、すでに若い木になっている。
思い切り身をよじり、逃げようとするウキネ。
しかし、柿の成長は止まらない。
アネモネが、シロツメに飛びかかった。
「おやめ! この不敬者が!」
瞬間、シロツメの前に黒い影が飛んでくる。
アネモネの爪を止めたのは、モクレンのキセルだった。
「もう、やめえ。アネモネ」
「できそこないのルナールが! 出がらししか散らさない、不完全なアカギツネ !」
「おまえは上品なくせに、昔からわるぐちが達者やな」
ふわりと、モクレンのキセルから香ばしいにおいが漂う。
アネモネはハッとして、鼻をひくつかせた。
「これ……!」
においに気づいたウキネも、きょろきょろとあたりを見渡している。
モクレンはゆっくりと、煙が流れるように答えた。
「どんぐりの実に柿の皮を巻いたもの、おまえのマスターが好きなやつや」
アネモネの息をのむ音が、鮮明に聞こえた。
「皮肉なもんやな。柿の木に封印されていたのに、好きなにおいがこれとは」
スキが生まれたウキネさまを、レンゲの爪が狙っている。
柿の木に捕らわれたウキネさまに、もう逃げ場はなかった。
「ウキネさまっ! 逃げてっ」
「――アネモネ。まだ、心配してくれるか……こんな、わたしを」
あたりに、また極寒の雪が吹きすさぶ。
これほどまでの寒さでは、これ以上柿の木が成長することは出来ない。
シロツメの息も、乱れはじめている。
「あー、ダメだ。こんな若い木じゃあ、これ以上捕まえておくことはできないよ」
そんな、ここまで来たのに……。
もう、あきらめるしかないのかな?
ゴオオオオオ……。
その音は、一面の雪を溶かす炎だった。
目の前が真っ白から、鮮やかな赤に変わる。
しかし、その炎は熱くない、あたたかな炎だった。
命を育むような、優しい炎。
「やっと、来よったか」
モクレンがホッとしたように、息をついた。
「ナズナさま――!」
ナズナさまは背中の黒い羽をはばたかせ、ゆっくりと空から降りてきた。
背中に穴を開けた羽専用の着物が、炎で照らされ鮮やかに彩られている。
「モクレン。みんな、よう頑張った。ハコベラの準備も整った。返すときが来たようじゃ」
「ハコベラさん……?」
首を傾げるわたしに、ハコベラさんが憂いを帯びた表情をする。
「ゲンブのちからは、もともとは、わたしのものなんですよ」
それを聞いて、ヤクモは「なるほど」と、うなった。
「『三日月祭のはじまりの猫』がウキネなら、ゲンブのちからを持っているのは不自然だ。だが、それがもともと、ハコベラさんのものだったというのなら、納得できるよな」
ナズナさまはカラスのキノ・キランだから、ヤタガラスのちから 。
ハコベラさんはカメのキノ・キランだから、ゲンブのちからを持てた。
「じゃあ、どうやってウキネはゲンブのチカラを?」
「奪われたのです」
わたしの質問に、ハコベラさんはうつむいた。
「ゲンブのちからには、命を生みだす能力があります。ウキネは、わたしからゲンブのちからを奪い取り、自分の魂を受け継ぐものを次々に生み出していきました」
「アネモネもそのひとり、なんだね」
わたしがいうと、ハコベラさんが続けた。
「ほんとうのウキネは、ただ『黒猫』のキノ・キランなのです」
「ウキネが、黒猫……」
「大らかで、甘えんぼう。人懐っこい、とても愛らしい猫でした」
「ハコベラさん、まるで見てきたみたいにいうんですね」
「ええ。わたしも、長生きですから……」
そのとき、シロツメが声をあげた。
「ヤクモ! ナズナさまの炎で、柿の木が成長しきった。これなら、封印できるよ!」
「おーい。こっちも限界近いでー」
アネモネとの戦いで、モクレンのキセルはボロボロになっていた。
「チカナ。ウキネはもう、吹雪を出すちからは残っていない」
柿の木の上から、レンゲが叫ぶ。
過去、ウキネさまを封じたときの呪文が書かれた和紙を広げる。
モクレンが、柿のタネといっしょに、手のひらに掴んでいたんだ。
わたしはそれを、一字一字噛みしめるように唱えた。
『おやすみなさい わたしたちの月の黒猫』
ぐぐぐ、と柿の木の幹が、ウキネを丸く包みこんだ。
布団のように柔らかく、そのからだを沈めていく。
ウキネの瞳が月の光に反射して、キラッと輝いた。
美しい紫色だった。
ウキネの瞳が眠りにつこうと、スウッと閉じていく。
「行かないでくださいまし! ウキネさま!」
アネモネが、柿の木のウキネのもとへと飛びあがった。
「わたくしもともに眠ります……。おやすみなさい、ウキネさま……」
ウキネの隣に寄り添う、アネモネ。
いっしょに眠るウキネとアネモネのすがたは、なかよくくっついて眠る、親子の猫のようにしか見えなかった。
柿の木はウキネとアネモネを包みこむと、金色の光を放った。
その光に思わず、目をつむる。
目を開いた時には、ウキネもアネモネも、柿の木もなくなっていた。
なんと、霜月の宿さえ影も、かたちもなくなっていた。
まわりに、幽霊に憑りつかれていたキノ・キランのみんなが倒れている。
次々に、目を覚ますキノ・キランたちは、何が起こったのかわからないとふしぎそうにいているけれど、とりあえず元気そうだ。
でも、なんとなく胸の奥がモヤっとする。
ウキネのことが、頭から離れない。
「チカナ。むずかしい顔をしているな」
「レンゲ。ありがとうね、戦ってくれて……」
「当たり前だ。いっただろう? おまえを守るのは、おれだと……」
すると、レンゲがわたしの頭を、そっと撫でてくれる。
「ふふ、いつもと違うね。いつもは、わたしが撫でてるから……あれ?」
ぽろぽろと、目から涙がこぼれてくる。
「な、何で……?」
「大丈夫だ。がんばったからだ」
わたしはしばらく、レンゲの胸で声を出さずに泣いた。
レンゲはいつまでもいつまでも、わたしの頭を撫でてくれていた。
「おまえががんばったから、涙が出るんだ」