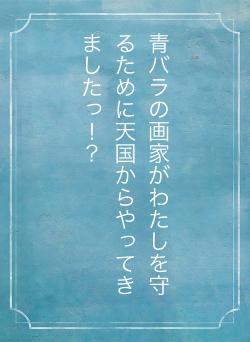この声……アネモネ?
アネモネは、持っていた箸を箸置きに置くと、わたしたちを通り越していく。
フリルたっぷりのゴスロリスカートをひるがえし、ウキネさまの前にそっと盾のごとく立った。
そして、ギロリと、わたしたちをナイフのごとく、睨みつけてくる。
「人間の世界には、理不尽ばかりがあふれている。病院での毎年の予防注射、辛かったですわ」
「それは! アネモネが病気にならないように、飼い主さんが……」
「それは人間が、世界を汚すからですわ。ウキネさまだけが、清浄な空気の世界を作ってくださるの」
アネモネは、花が咲くように艶やかに笑う。
「このキノ・キランたち、ようすがおかしい。こんなにおれたちが騒いでいるのに、誰もこっちを見ない」
ヤクモが、ぶきみだといわんばかりに、ヤクモは広間をぐるりと見渡す。
たしかに誰も、わたしたちのことを見ていない。
まるで、ここだけの世界で生きているみたいに、みんな目の前のことだけを楽しんでいる。
ウキネさまが、すべてを見下すように、目を細めた。
「いまなら、許してやらんこともない。きみんらのキノ・キランを渡してくれたら、どこへなりとも逃げるがええわ」
「ふざけないでっ――レンゲ!」
わたしの号令に、レンゲの瞳が閃光のように軌跡を描く。
爪をむき出しにし、ウキネさまに飛びかかった。
しかし、その爪の先にアネモネが立ちふさがる。
アネモネの爪が凶器として、レンゲの眉間の中心を捕えた。
レンゲのするどい爪も、アネモネの眉間寸前でピタリと止まっている。
どちかが動けば、その爪は相手をつらぬく。
「レンゲ!」
ウキネが、ニヤリと笑う。
「くふふ、素晴らしい余興じゃ。この町が滅ぶ日に、ふさわしい」
後ろでは相変わらず、キノ・キランたちのドンチャン騒ぎが続いている。
町では、三日月祭のにぎわいで、みんなが笑顔で月を見あげている。
わたしは手のひらをギュッ、と握りしめた。
「もう……もうこんなこと、止めてよ! みんなで、いっしょに生きることはできないの?」
必死に叫ぶわたしに、アネモネは不快だ、といわんばかりに顔を歪めた。
「不敬ですわね」
「ふ、ふけいって……どういうこと」
「ウキネさまは、わたくしたちの神なのです」
アネモネはうっとりと、ウキネさまに寄り添った。
「ウキネさまは、太陽と相反する、太陰の神。ゲンブのちからを持つおかた」
ゲンブって、聞いたことがある。
スマホのゲームで見たときは、亀とヘビが合体した、霊獣――って、書いてあった気がする。
「ゲンブは季節においては、冬の象徴。ウキネさまは、その神のちからを幽霊たちにわけあたえ、キノ・キランたちの情報を集めさせていました」
だから、ツララさんは、氷の剣の能力を使えたんだね……。
「いまウキネさまの神のちからで、キノ・キランたちに、幽霊をちょくせつ乗り移らせています。これにより、キノ・キランの心ごと支配できているのですよ。素晴らしいでしょう? ここでドンチャン騒ぎしている彼らは、永遠に幸せですわ」
「ひどい。ひどすぎるよ……」
わたしがうめくようにいうと、アネモネは得意げに鼻で笑った。
「ウキネさま。こんな小さな町、さっさと滅ぼしてしまいましょう」
「アネモネは、ほんまに可愛ええなあ。なら、そうしよか」
ウキネさまが、人さし指をくいっと動かすと、広間に、廊下に、霜月の宿に、激しい吹雪が起こった。
わたしたちは、息もたえだえに、その場から逃げ出し、宿の廊下を走りぬける。
すると、ある部屋の前で、モクレンが立ち止まった。
「ここは……」
「どうしたの、モクレン」
「この部屋、なんかくさいで」
「もう。こんなときに、ヨモギの吸いすぎは……」
呆れていうと、モクレンはムッとしながら、吹雪に負けないよう大声でいう。
「あほ! ほんまに、気になんねん」
「なんでそんな急に……?」
「キツネはな、周囲の位置情報を正確に把握できるっちゅう能力があんねん。ここは、建物の中心。こういう部屋は、建物の心臓部分っていう心理が働いて、貴重なもんをしまいがちなんよ。ちょっと、入ってみるわ!」
モクレンが、部屋の引き戸を思いっきり引いた。
パァンという、戸枠の破裂音が、吹雪に吸いこまれていく。
部屋は暗くて、よく見えない。
「レンゲ、何か見える?」
「ああ、おれたちには『夜目』があるからな」
「やめ?」
「猫や犬は、暗闇でも物を見ることが出来るんだ。キツネもな。ほら――あそこを見てみろ」
レンゲが指さした先には、猫が描かれた掛け軸が、飾られていた。
隣にも、同じような掛け軸がぶらさがっているのだけど、そっちには文字しか書かれていない。
しかも、達筆すぎて、わたしには読むことが出来なかった。
「三日月祭の伝説が書かれとるようやな」
モクレンが、じいっと掛け軸を覗きこんでいる。
「えっ。ほんとうに、貴重なものがあったじゃん! すごいよ! しかも、読めるの?」
「ナズナさまに、仕こまれただけや。そない、騒ぐことちゃう……」
照れたように、モクレンは解読をはじめてくれた。
『村中の動物 流行病にかかり まふ(もう)治らぬと
村中いかがにか助からなゐ(い)かと 毎晩 美しき月に願ゐて
ある猫 面妖(めんよう)なちからにて 病をこくふく
さすれば 村中の動物たちの病は ほらのごとく 消ゑ(え)た
されど はじめ 病直りし猫 両眼(りょうがん)紫色になりもうし
その猫 名を 浮き音(ウキネ)
不老不死のちからをえし 玄武
浮き音 亀姫(かめひめ)になりはて おぞましきちからにて 村を凍らせた
村人 浮き音を柿の木下に封印し まふ二度と
かのようなことが 起こらなゐやうにと
三日月祭を するぞようになりもうし』
「ねえ、ウキネって……あのウキネのこと、なのかな」
「信じられへんけどな。不老不死。つまりウキネは、奇跡が起きたあの日からいままで、生き続けとることになる。子孫を作りながらな。そんで、その末裔が、あのアネモネってか」
モクレンの声も、はりつめている。
なんてことを知っちゃったんだろう。
「ウキネが玄武の力で、村を凍らせたため、村人たちはウキネを柿の木の下に封印した。もう村で、二度とこんなことが起こらないようにと、人々は三日月祭をするようになった――ってことか。でも、伝わっている伝説とぜんぜん違うな」
ヤクモが動揺をかくせないようすで、くり返す。
わたしの心臓も、バクバクと飛び跳ねて、口から飛び出しそうだった。
「長い時間がたつうちに間違って伝って、いつのまにか月に感謝するお祭りになったのかな……」
シロツメが、掛け軸の下でしっぽを揺らしながら、指をさす。
「ヤクモ。このへんから、へんなにおいがする」
モクレンとレンゲも、いわれた場所でクンクンと鼻を動かす。
「たしかに、気になるにおいがするな」
「でも、かけ軸以外、何もないけど……」
わたしがいうと、ヤクモがおもむろに、掛け軸をパッとめくった。
「わっ。かけ軸の裏に、小さな戸が……! 時代劇みたいな隠しかただ。なにこれ?」
「戸なんだから、開けてみればわかる」
ヤクモは、まるでゲームの新しいダンジョンが現れたときのような、わくわくした表情をしている。
シュ、とかすかな音を立てながら、小さな戸が開けられる。
わたしたちは顔を寄せ合って、そこをのぞきこんだ。
「何も見えないな。生きてるもののにおいはしないが」
レンゲがいうと、モクレンが「ふふん」と得意げに笑う。
「わかった。ちょっと、ぼくに任せてみ」
いうと、モクレンは躊躇することなく、小さな空間に腕を突っこんだ。
「も、モクレン! 大丈夫なの?」
「おん。森んなかを駆けまわっとったアカギツネの鼻に狂いはないで。こんなかにお宝が眠っとるんは間違いない」
そういって、手のなかに掴んだものをモクレンは、不敵な笑顔で見せてくれる。
それを見て、わたしたちは顔を見せあった。
「これは――!」
アネモネは、持っていた箸を箸置きに置くと、わたしたちを通り越していく。
フリルたっぷりのゴスロリスカートをひるがえし、ウキネさまの前にそっと盾のごとく立った。
そして、ギロリと、わたしたちをナイフのごとく、睨みつけてくる。
「人間の世界には、理不尽ばかりがあふれている。病院での毎年の予防注射、辛かったですわ」
「それは! アネモネが病気にならないように、飼い主さんが……」
「それは人間が、世界を汚すからですわ。ウキネさまだけが、清浄な空気の世界を作ってくださるの」
アネモネは、花が咲くように艶やかに笑う。
「このキノ・キランたち、ようすがおかしい。こんなにおれたちが騒いでいるのに、誰もこっちを見ない」
ヤクモが、ぶきみだといわんばかりに、ヤクモは広間をぐるりと見渡す。
たしかに誰も、わたしたちのことを見ていない。
まるで、ここだけの世界で生きているみたいに、みんな目の前のことだけを楽しんでいる。
ウキネさまが、すべてを見下すように、目を細めた。
「いまなら、許してやらんこともない。きみんらのキノ・キランを渡してくれたら、どこへなりとも逃げるがええわ」
「ふざけないでっ――レンゲ!」
わたしの号令に、レンゲの瞳が閃光のように軌跡を描く。
爪をむき出しにし、ウキネさまに飛びかかった。
しかし、その爪の先にアネモネが立ちふさがる。
アネモネの爪が凶器として、レンゲの眉間の中心を捕えた。
レンゲのするどい爪も、アネモネの眉間寸前でピタリと止まっている。
どちかが動けば、その爪は相手をつらぬく。
「レンゲ!」
ウキネが、ニヤリと笑う。
「くふふ、素晴らしい余興じゃ。この町が滅ぶ日に、ふさわしい」
後ろでは相変わらず、キノ・キランたちのドンチャン騒ぎが続いている。
町では、三日月祭のにぎわいで、みんなが笑顔で月を見あげている。
わたしは手のひらをギュッ、と握りしめた。
「もう……もうこんなこと、止めてよ! みんなで、いっしょに生きることはできないの?」
必死に叫ぶわたしに、アネモネは不快だ、といわんばかりに顔を歪めた。
「不敬ですわね」
「ふ、ふけいって……どういうこと」
「ウキネさまは、わたくしたちの神なのです」
アネモネはうっとりと、ウキネさまに寄り添った。
「ウキネさまは、太陽と相反する、太陰の神。ゲンブのちからを持つおかた」
ゲンブって、聞いたことがある。
スマホのゲームで見たときは、亀とヘビが合体した、霊獣――って、書いてあった気がする。
「ゲンブは季節においては、冬の象徴。ウキネさまは、その神のちからを幽霊たちにわけあたえ、キノ・キランたちの情報を集めさせていました」
だから、ツララさんは、氷の剣の能力を使えたんだね……。
「いまウキネさまの神のちからで、キノ・キランたちに、幽霊をちょくせつ乗り移らせています。これにより、キノ・キランの心ごと支配できているのですよ。素晴らしいでしょう? ここでドンチャン騒ぎしている彼らは、永遠に幸せですわ」
「ひどい。ひどすぎるよ……」
わたしがうめくようにいうと、アネモネは得意げに鼻で笑った。
「ウキネさま。こんな小さな町、さっさと滅ぼしてしまいましょう」
「アネモネは、ほんまに可愛ええなあ。なら、そうしよか」
ウキネさまが、人さし指をくいっと動かすと、広間に、廊下に、霜月の宿に、激しい吹雪が起こった。
わたしたちは、息もたえだえに、その場から逃げ出し、宿の廊下を走りぬける。
すると、ある部屋の前で、モクレンが立ち止まった。
「ここは……」
「どうしたの、モクレン」
「この部屋、なんかくさいで」
「もう。こんなときに、ヨモギの吸いすぎは……」
呆れていうと、モクレンはムッとしながら、吹雪に負けないよう大声でいう。
「あほ! ほんまに、気になんねん」
「なんでそんな急に……?」
「キツネはな、周囲の位置情報を正確に把握できるっちゅう能力があんねん。ここは、建物の中心。こういう部屋は、建物の心臓部分っていう心理が働いて、貴重なもんをしまいがちなんよ。ちょっと、入ってみるわ!」
モクレンが、部屋の引き戸を思いっきり引いた。
パァンという、戸枠の破裂音が、吹雪に吸いこまれていく。
部屋は暗くて、よく見えない。
「レンゲ、何か見える?」
「ああ、おれたちには『夜目』があるからな」
「やめ?」
「猫や犬は、暗闇でも物を見ることが出来るんだ。キツネもな。ほら――あそこを見てみろ」
レンゲが指さした先には、猫が描かれた掛け軸が、飾られていた。
隣にも、同じような掛け軸がぶらさがっているのだけど、そっちには文字しか書かれていない。
しかも、達筆すぎて、わたしには読むことが出来なかった。
「三日月祭の伝説が書かれとるようやな」
モクレンが、じいっと掛け軸を覗きこんでいる。
「えっ。ほんとうに、貴重なものがあったじゃん! すごいよ! しかも、読めるの?」
「ナズナさまに、仕こまれただけや。そない、騒ぐことちゃう……」
照れたように、モクレンは解読をはじめてくれた。
『村中の動物 流行病にかかり まふ(もう)治らぬと
村中いかがにか助からなゐ(い)かと 毎晩 美しき月に願ゐて
ある猫 面妖(めんよう)なちからにて 病をこくふく
さすれば 村中の動物たちの病は ほらのごとく 消ゑ(え)た
されど はじめ 病直りし猫 両眼(りょうがん)紫色になりもうし
その猫 名を 浮き音(ウキネ)
不老不死のちからをえし 玄武
浮き音 亀姫(かめひめ)になりはて おぞましきちからにて 村を凍らせた
村人 浮き音を柿の木下に封印し まふ二度と
かのようなことが 起こらなゐやうにと
三日月祭を するぞようになりもうし』
「ねえ、ウキネって……あのウキネのこと、なのかな」
「信じられへんけどな。不老不死。つまりウキネは、奇跡が起きたあの日からいままで、生き続けとることになる。子孫を作りながらな。そんで、その末裔が、あのアネモネってか」
モクレンの声も、はりつめている。
なんてことを知っちゃったんだろう。
「ウキネが玄武の力で、村を凍らせたため、村人たちはウキネを柿の木の下に封印した。もう村で、二度とこんなことが起こらないようにと、人々は三日月祭をするようになった――ってことか。でも、伝わっている伝説とぜんぜん違うな」
ヤクモが動揺をかくせないようすで、くり返す。
わたしの心臓も、バクバクと飛び跳ねて、口から飛び出しそうだった。
「長い時間がたつうちに間違って伝って、いつのまにか月に感謝するお祭りになったのかな……」
シロツメが、掛け軸の下でしっぽを揺らしながら、指をさす。
「ヤクモ。このへんから、へんなにおいがする」
モクレンとレンゲも、いわれた場所でクンクンと鼻を動かす。
「たしかに、気になるにおいがするな」
「でも、かけ軸以外、何もないけど……」
わたしがいうと、ヤクモがおもむろに、掛け軸をパッとめくった。
「わっ。かけ軸の裏に、小さな戸が……! 時代劇みたいな隠しかただ。なにこれ?」
「戸なんだから、開けてみればわかる」
ヤクモは、まるでゲームの新しいダンジョンが現れたときのような、わくわくした表情をしている。
シュ、とかすかな音を立てながら、小さな戸が開けられる。
わたしたちは顔を寄せ合って、そこをのぞきこんだ。
「何も見えないな。生きてるもののにおいはしないが」
レンゲがいうと、モクレンが「ふふん」と得意げに笑う。
「わかった。ちょっと、ぼくに任せてみ」
いうと、モクレンは躊躇することなく、小さな空間に腕を突っこんだ。
「も、モクレン! 大丈夫なの?」
「おん。森んなかを駆けまわっとったアカギツネの鼻に狂いはないで。こんなかにお宝が眠っとるんは間違いない」
そういって、手のなかに掴んだものをモクレンは、不敵な笑顔で見せてくれる。
それを見て、わたしたちは顔を見せあった。
「これは――!」