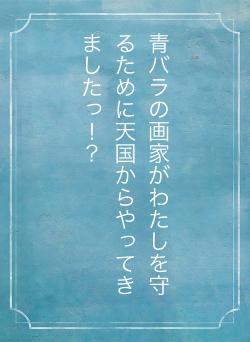前に出ようとするわたしの腰を、レンゲが抑えこんだ。
炎が、大きな冷たい風によって、ナズナさまの周りに閉じこめられている。
風に、氷の粒がまとわりついている。
氷の風だ。
タンポポのまわりにも、同様の風が吹いている。
よかった。タンポポは無事みたい。
「あの氷……ヤタガラスの炎でも、溶かしきれんとはな」
モクレンが、驚いてる。
ナズナさまは、さらに炎を吹きあげる。
そのたびに、氷の風に炎を押しこめられてしまう。
炎と氷がぶつかり合うたびに、あたりに氷の粒が飛び散り、火花が舞った。
しかし、確実にナズナさまの炎の勢いが、じょじょに弱まっていく。
やがて、ナズナさまは肩で息をするほどに疲弊し、ついに攻撃を止めた。
「ヤタガラスのちからを使いすぎたんや」
モクレンは、安心したかのように、ホッと肩をおろした。
レンゲも、やっとわたしの腰から腕を放してくれる。
でも、あの氷を出したのは一体――?
「どんぐりの実に柿の皮を巻いたフレーバー、持って来てやったぞ」
ハッと、モクレンが顔を上げた。
聞き覚えのある声に、わたしもその声を追う。
見覚えのあるお姉さんが、モクレンのスーツジャケットのポケットに、むりやりそのフレーバーを突っこんだ。
お姉さんの顔は笑顔だけれど、その目は笑っていない。
ただよってくる空気が、異常に冷たい。
まるで、氷のそばにずっといたかのように。
「あなたが、タンポポを……助けてくれたんですか……?」
自然と、聞いていた。
するとお姉さんは、わたしの質問ににっこり笑った。
「それは違うなあ」
「え?」
「どちらかというと、あのいけ好かんカラスを氷漬けにしにきたんよ」
瞬間、お姉さんは後ろを振り返り、腕を伸ばした。
ビュオオオという冷風音が、森のなかにこだまする。
ナズナさまのからだが、みるみるうちに凍っていく。
モクレンが、叫んだ。
「何しとんねん、ワレッ――!」
モクレンは、お姉さんの胸倉に掴みかかろうとする。
しかし、モクレンの手は、空を切る。
お姉さんのすがたは、もうそこにはなかった。
「――ウキネさまっ」
タンポポが……違う、タルヒさんが歓喜たっぷりに叫んだ。
タルヒさんに憑りつかれたタンポポのそばに、お姉さんがたたずんでいた。
いま、タルヒさんはお姉さんのことをなんて呼んでた?
「ウキネさま。おれを助けに来てくれたんですか!」
「ん~。そうじゃの~」
ウキネさまの返事に、タルヒさんはとっても嬉しそうだ。
「おれ、ウキネさまのために、キノ・キランをたくさん捕まえますからっ。おれの願い、叶えてくれるんですよね!」
タンポポのからだで、タルヒさんは大手を振って、お姉さんにアピールしている。
あのお姉さんが、ウキネさま――。
間違い、ないのかな。
必死に訴えるタルヒさんに、ウキネさまはゆったりと、くちびるを緩めた。
「そうやねえ。でも……」
ウキネさまが、右手を軽く挙げた。
すると、白い粉のようなものが、タルヒさんに降り注ぐ。
「えっ? これは……」
目を丸くするタルヒさんに、ウキネさまがいじわるくニヤリと笑う。
「海氷の雪じゃ。除霊には海水百パーセントの塩が効くというじゃろ。特に、おぬしみたいな低級霊にはなあ」
タンポポが、苦しそうに呻きはじめた。
いや、憑りついているタルヒさんが、苦しんでいるのだ。
「やりやがったな! キノ・キラン! バケモノがあああああ」
「……自分の欲望のためなら、どんなことでも犠牲にする。おぬしのほうが、よっぽどバケモンじゃろ」
「くそおおおおおおお」
タルヒさんの絶叫が、こだまする。
瞬間、タンポポのからだが、ぐらりと揺れる。
「タンポポ!」
わたしは急いでタンポポに駆け寄り、その小さなふわふわを抱きとめた。
レンゲが、ふわりとわたしのそばに降り立った。
「レンゲ?」
「……おれのそばから、離れるな」
いい終わったレンゲは、なぜかタンポポを抱きしめるわたしを、遠くに突き飛ばした。
「――え?」
とたん、レンゲが氷のつぶてに襲われた。
そばの巨木に背中を打ちつけ、ずるずると地面にしゃがみこんでしまう。
「レンゲッ!」
急いでレンゲに駆け寄る。
けれど、目を覚まさない。
そのまま、気を失ってしまったみたいだ。
どうしよう、このまま目を覚まさなかったら……。
「大変じゃろうなあ。こんな役立たずの飼い主のキノ・キランは……」
ドキン、と心臓が跳ねる。
耳もとで、ウキネさまの声が、呪いの言葉のように響いた。
「このコチカ・キノの実力を引き出してやれんなら、飼い主を辞めてやったほうがええんじゃないか」
「そんな……」
「心配せんでもええ。そうなれば、霜月の宿で、コチカ・キノを大事に引き取ってやる」
「レンゲを霜月の宿に――?」
「こんな傷だらけになって……いま、コチカ・キノは幸せなんか?」
ウキネさまは、闇夜にとろけるような音色で、わたしの心に語りかける。
「レンゲは……わたしのそばにいないほうが、幸せなのかな……」
「人間に、動物は救えないんじゃ」
そうなんだ。
そのほうが、レンゲのためになるなら。
レンゲは、わたしといないほうが幸せなら……そうするしか……。
「――チカナッ! しっかりしろ!」
わたしを呼ぶ声に、わたしは夢から覚めるように、現実に引き戻された。
ぼーっとする頭、ぼんやりする視界のなか、レンゲがいた。
さっきの声、レンゲだ。
戦いながら、わたしを呼んでくれてたんだ。
猫の瞬発力で、しなやかにからだを反らし、レンゲは氷のつぶてをよけ続けている。
「チカナ。大丈夫か」
ヤクモが、心配そうに駆け寄ってくれる。
「幻術にかかっていたんだ。レンゲがウキネに攻撃をしかけて、幻術の強度を崩したから、すぐに解くことができた。だが……」
「だ、だがって……?」
「猫はそんなに持久力のある種族じゃない。シロツメがナズナさまの氷をなんとかしようとしてくれているが、これも長期戦になりそうだ。もう限界……かもな」
「そんな……」
絶望しかけたとき、その場にパッと、紫陽花の花びらが舞いはじめた。
「花のでがらし――モクレン?」
「未熟なキノ・キランでもなあ、見せ所くらいは理解してんねんぞ!」
さらに激しく、紫陽花の花びらが舞う。
まるで、嵐のように。
「モクレン! これって――」
「ウキネに幻術かけとんねん! 集中しとるから、話しかけんな!」
モクレンが苦しそうに叫ぶ。
「くそっ。たぶん、十秒が限界や! おまえら、とにかく走れ!」
レンゲが、タンポポをごと、わたしを抱きあげ、走り出す。
シロツメも、氷漬けのナズナさまを脇にかかえた。
他のみんなも、転がるようにその場から逃げ出す。
しかし、すぐに後ろから、氷の風が、冷たく背中をなでた。
もう、モクレンの幻術が溶けた――?
文字通り、背筋がゾゾッと凍りつきそうになったけれど、それ以上、ウキネさまは追いかけてくる気配はなかった。
見逃して、くれたのかな……。
森の外に出ると、息を切らしながら、シロツメがいった。
「――今夜は、三日月祭だね」
まるで、別世界の話みたいだ、とわたしはつい、笑ってしまう。
だけど、空を見上げると、やっぱりきれいな月が輝いていて、こんなときでも「きれいだ」とおもってしまった。
炎が、大きな冷たい風によって、ナズナさまの周りに閉じこめられている。
風に、氷の粒がまとわりついている。
氷の風だ。
タンポポのまわりにも、同様の風が吹いている。
よかった。タンポポは無事みたい。
「あの氷……ヤタガラスの炎でも、溶かしきれんとはな」
モクレンが、驚いてる。
ナズナさまは、さらに炎を吹きあげる。
そのたびに、氷の風に炎を押しこめられてしまう。
炎と氷がぶつかり合うたびに、あたりに氷の粒が飛び散り、火花が舞った。
しかし、確実にナズナさまの炎の勢いが、じょじょに弱まっていく。
やがて、ナズナさまは肩で息をするほどに疲弊し、ついに攻撃を止めた。
「ヤタガラスのちからを使いすぎたんや」
モクレンは、安心したかのように、ホッと肩をおろした。
レンゲも、やっとわたしの腰から腕を放してくれる。
でも、あの氷を出したのは一体――?
「どんぐりの実に柿の皮を巻いたフレーバー、持って来てやったぞ」
ハッと、モクレンが顔を上げた。
聞き覚えのある声に、わたしもその声を追う。
見覚えのあるお姉さんが、モクレンのスーツジャケットのポケットに、むりやりそのフレーバーを突っこんだ。
お姉さんの顔は笑顔だけれど、その目は笑っていない。
ただよってくる空気が、異常に冷たい。
まるで、氷のそばにずっといたかのように。
「あなたが、タンポポを……助けてくれたんですか……?」
自然と、聞いていた。
するとお姉さんは、わたしの質問ににっこり笑った。
「それは違うなあ」
「え?」
「どちらかというと、あのいけ好かんカラスを氷漬けにしにきたんよ」
瞬間、お姉さんは後ろを振り返り、腕を伸ばした。
ビュオオオという冷風音が、森のなかにこだまする。
ナズナさまのからだが、みるみるうちに凍っていく。
モクレンが、叫んだ。
「何しとんねん、ワレッ――!」
モクレンは、お姉さんの胸倉に掴みかかろうとする。
しかし、モクレンの手は、空を切る。
お姉さんのすがたは、もうそこにはなかった。
「――ウキネさまっ」
タンポポが……違う、タルヒさんが歓喜たっぷりに叫んだ。
タルヒさんに憑りつかれたタンポポのそばに、お姉さんがたたずんでいた。
いま、タルヒさんはお姉さんのことをなんて呼んでた?
「ウキネさま。おれを助けに来てくれたんですか!」
「ん~。そうじゃの~」
ウキネさまの返事に、タルヒさんはとっても嬉しそうだ。
「おれ、ウキネさまのために、キノ・キランをたくさん捕まえますからっ。おれの願い、叶えてくれるんですよね!」
タンポポのからだで、タルヒさんは大手を振って、お姉さんにアピールしている。
あのお姉さんが、ウキネさま――。
間違い、ないのかな。
必死に訴えるタルヒさんに、ウキネさまはゆったりと、くちびるを緩めた。
「そうやねえ。でも……」
ウキネさまが、右手を軽く挙げた。
すると、白い粉のようなものが、タルヒさんに降り注ぐ。
「えっ? これは……」
目を丸くするタルヒさんに、ウキネさまがいじわるくニヤリと笑う。
「海氷の雪じゃ。除霊には海水百パーセントの塩が効くというじゃろ。特に、おぬしみたいな低級霊にはなあ」
タンポポが、苦しそうに呻きはじめた。
いや、憑りついているタルヒさんが、苦しんでいるのだ。
「やりやがったな! キノ・キラン! バケモノがあああああ」
「……自分の欲望のためなら、どんなことでも犠牲にする。おぬしのほうが、よっぽどバケモンじゃろ」
「くそおおおおおおお」
タルヒさんの絶叫が、こだまする。
瞬間、タンポポのからだが、ぐらりと揺れる。
「タンポポ!」
わたしは急いでタンポポに駆け寄り、その小さなふわふわを抱きとめた。
レンゲが、ふわりとわたしのそばに降り立った。
「レンゲ?」
「……おれのそばから、離れるな」
いい終わったレンゲは、なぜかタンポポを抱きしめるわたしを、遠くに突き飛ばした。
「――え?」
とたん、レンゲが氷のつぶてに襲われた。
そばの巨木に背中を打ちつけ、ずるずると地面にしゃがみこんでしまう。
「レンゲッ!」
急いでレンゲに駆け寄る。
けれど、目を覚まさない。
そのまま、気を失ってしまったみたいだ。
どうしよう、このまま目を覚まさなかったら……。
「大変じゃろうなあ。こんな役立たずの飼い主のキノ・キランは……」
ドキン、と心臓が跳ねる。
耳もとで、ウキネさまの声が、呪いの言葉のように響いた。
「このコチカ・キノの実力を引き出してやれんなら、飼い主を辞めてやったほうがええんじゃないか」
「そんな……」
「心配せんでもええ。そうなれば、霜月の宿で、コチカ・キノを大事に引き取ってやる」
「レンゲを霜月の宿に――?」
「こんな傷だらけになって……いま、コチカ・キノは幸せなんか?」
ウキネさまは、闇夜にとろけるような音色で、わたしの心に語りかける。
「レンゲは……わたしのそばにいないほうが、幸せなのかな……」
「人間に、動物は救えないんじゃ」
そうなんだ。
そのほうが、レンゲのためになるなら。
レンゲは、わたしといないほうが幸せなら……そうするしか……。
「――チカナッ! しっかりしろ!」
わたしを呼ぶ声に、わたしは夢から覚めるように、現実に引き戻された。
ぼーっとする頭、ぼんやりする視界のなか、レンゲがいた。
さっきの声、レンゲだ。
戦いながら、わたしを呼んでくれてたんだ。
猫の瞬発力で、しなやかにからだを反らし、レンゲは氷のつぶてをよけ続けている。
「チカナ。大丈夫か」
ヤクモが、心配そうに駆け寄ってくれる。
「幻術にかかっていたんだ。レンゲがウキネに攻撃をしかけて、幻術の強度を崩したから、すぐに解くことができた。だが……」
「だ、だがって……?」
「猫はそんなに持久力のある種族じゃない。シロツメがナズナさまの氷をなんとかしようとしてくれているが、これも長期戦になりそうだ。もう限界……かもな」
「そんな……」
絶望しかけたとき、その場にパッと、紫陽花の花びらが舞いはじめた。
「花のでがらし――モクレン?」
「未熟なキノ・キランでもなあ、見せ所くらいは理解してんねんぞ!」
さらに激しく、紫陽花の花びらが舞う。
まるで、嵐のように。
「モクレン! これって――」
「ウキネに幻術かけとんねん! 集中しとるから、話しかけんな!」
モクレンが苦しそうに叫ぶ。
「くそっ。たぶん、十秒が限界や! おまえら、とにかく走れ!」
レンゲが、タンポポをごと、わたしを抱きあげ、走り出す。
シロツメも、氷漬けのナズナさまを脇にかかえた。
他のみんなも、転がるようにその場から逃げ出す。
しかし、すぐに後ろから、氷の風が、冷たく背中をなでた。
もう、モクレンの幻術が溶けた――?
文字通り、背筋がゾゾッと凍りつきそうになったけれど、それ以上、ウキネさまは追いかけてくる気配はなかった。
見逃して、くれたのかな……。
森の外に出ると、息を切らしながら、シロツメがいった。
「――今夜は、三日月祭だね」
まるで、別世界の話みたいだ、とわたしはつい、笑ってしまう。
だけど、空を見上げると、やっぱりきれいな月が輝いていて、こんなときでも「きれいだ」とおもってしまった。