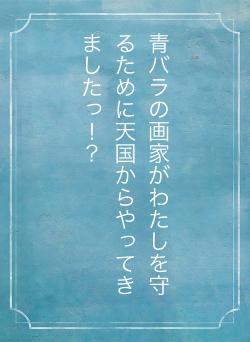モクレンの歩き方は、いつものふらふらとしたものではなく、けもの道を歩き慣れた、一定ペースの早歩きになっていた。
わたしはけもの道を歩くのに、すぐにバテはじめていた。
昔は遊びながら歩いていたから、ひたすら森のなかを歩き続けるのには、慣れていないんだ。
わたしのようすに、すぐに気づいたレンゲが、モクレンを呼び止める。
「待て、アカギツネ」
「んあ? どうかしたんか」
「チカナを休憩させてやりたい」
いいながら、レンゲがわたしを横抱きにする。
「ちょ、ちょっと、レンゲ! わたしなら大丈夫だから!」
「これで、休憩できるな。急ごう」
「……チカナちゃんの忠実なしもべ。かなわんなあ。ほな、はよ行こか」
わたしの反応にかまわず、レンゲとモクレンは一直線に走り出す。
すごいスピードで、森の景色が通り過ぎて行く。
わたしは、思わずレンゲの服を握りしめた。
「……こわいか? 目をつむっていろ」
「うん……」
大人しく、目をつむる。
なんだか、心臓がどきどきしている。
わたしが、ジェットコースターを苦手だからかな。
「アカギツネ」
「どうしたん」
「何か、聞こえるな」
「ほんまや。さすが、コチカ・キノ。耳がええなあ」
わたしには、何も聞こえない。
やっぱり、レンゲとモクレンは、人間よりも耳がいいんだ。
「蓮の花のにおいがする。この先に、やつがいる」
「見つけたんだね。レンゲ」
「でも、よくない気配もする」
レンゲが、表情をくもらせた。
「それって……?」
「さっき、アカギツネのキセルを拾った……あいつだ」
「あの女の人……?」
緑がうっそうと茂った森のなか、見覚えのある後ろ姿を見つけた。
「……ヤクモ!」
隣には、シロツメもいる。
振り返ったヤクモがわたしを見て、駆け寄ってきてくれる。
「チカナ、どうした? ケガでもしたのか」
レンゲに抱きあげられたままのわたしを、ヤクモが心配そうに見つめる。
「そ、そうだった。ごめん、レンゲ。もう降ろしてくれていいよ」
「もう、回復したのか」
「うん」
そっと降ろしてくれるレンゲに、わたしはお礼をいう。
すると、ヤクモが自分よりも背の高いレンゲを、冷ややかに見あげた。
「チカナが疲れたからって、抱きあげて運んでやるのは、甘やかしすぎなんじゃないか。レンゲ」
「おれの主人はチカナだ。チカナの命令じゃないことに耳を傾ける必要はない」
「……まったく」
ひそひそと、ふたりでいいあってるけど、声が小さすぎて、わたしには聞こえない。
いつのまに仲良しになったんだろう、ふたりとも。
モクレンが、きょろきょろとあたりを見渡している。
「ヤクモくん、ナズナさまは……?」
「怒り狂ってるよ」
「ですかー……」
「タルヒさんが、タンポポを放さないんだ――『憑りついてしまって』て」
「え……」
「そのせいで、ナズナさまがちからを使いはじめちゃったんだ」
「……まーじか」
あきらかに動揺しはじめたモクレンが、キセルを吸いはじめる。
ヨモギのにおいをくゆらせながら、ぷかりと白い煙をはいた。
「ねえ、ナズナさま……大丈夫なの?」
あたりに、ヨモギのいいにおいが漂いはじめると、モクレンも少し落ち着きを取り戻したようだ。
「ナズナさまは……コローネ・キノ、ハシボソカラスのキノ・キランや。それでいて、キノ・キランの最長老。チカナちゃんは、ハシボソガラスの寿命、知っとる?」
「寿命は、知らないけど……」
ヤクモがわたしの隣に立ち、代わりに答えてくれる。
「よくいって、十年から二十年。長く生きるカラスでも、二十年といわれている。でも、カラスより長生きなキノ・キランは、たくさんいるよ。ホッキョククジラは約二百年、ガラパゴスゾウガメは約百七十年。クラゲなんかは、不老不死だっていわれている種類もいるくらいだ」
「え……? でも、ナズナさまって、キノ・キランの最長老なんだよね?」
「ああ。それは、ナズナさまが『ヤタガラス』のチカラを持っているからだ」
「ヤタガラス……?」
首をかしげるわたしに、今度はシロツメが説明してくれる。
「ヤタガラスっていうのはね、三本足のカラスのこと。日本の神話に出てくる、太陽の化身なんだってさ」
「つまり、ヤタガラスは、神さまの使いみたいなものってこと? だから、最長老なんだ?」
話が終わったタイミングで、モクレンがぐしゃぐしゃと髪の毛をかき混ぜた。
「ヤタガラスの炎は、すべてを焼き尽くすんや。だから、あんまり暴走させたない……ったく。ナズナさまは、どこに行ったんや!」
しびれを切らしたモクレンが、キセルをにぎりしめ叫び出す。
「落ち着け、アカギツネ」
たしなめるように、レンゲがいう。
「シロツメ。蓮の花のにおいは、どないしたんや」
「それなんだよね……」
シロツメが自分の鼻を突きながら、くちびるを尖らせる。
「ここに来たとたん、鼻がいうことを効かなくなったんだ。だから、ここで立ち往生してたってわけ〜」
がっくりとうなだれる、モクレン。
「くそっ。ナズナさまが取り返しのつかんことする前に、なんとかせな……」
そのとき、レンゲとシロツメが顔を上げた。
「なんだか……コゲくさいにおいがしないか?」
レンゲがあたりを見渡すと、シロツメが、パッと顔をあげた。
「そっか。それのせいで、蓮の花のにおいが判別つかなくなっていたんだ」
「この先からや!」
とたん、走り出すモクレン。
「おれたちも行くぞ。シロツメ!」
「うん」
ヤクモとシロツメも、モクレンを追っていってしまう。
すると、レンゲが当然のようにわたしを抱きあげた。
たしかに、わたしはレンゲより走るのが遅いけど。
「じ、自分で走れるよ」
「こうさせてくれたほうが、おまえのすがたを確認できて、おれは安心できる。いいだろう? おれのマスター」
レンゲが、ジッとわたしを見つめる。
そんなふうにいわれちゃったら、黙って抱きあげられるしかないよ。
何もいわないわたしを、肯定を受け取ったのか、レンゲもみんなを追いかけて走り出した。
しばらく行くと、わたしにも判るほどのコゲくさいにおいが漂ってきた。
少し行った先に、開けた空間があり、中央に真っ黒い長じゅばんを身にまとった、ナズナさまが立っていた。
じゅばんをまとったそのすがたに、ゆらゆらと燃える赤い炎をまとっている。
これが、ヤタガラスのキノ・キラン――。
木の葉が、ふぶきみたいに舞い散り、ナズナさまの炎に焼かれ、焦げていく。
「ナズナさま!」
モクレンが叫んだ。
だけど、ナズナさまには聞こえていないみたい。
「くそ。ああなると、誰の声も届かへん……!」
羽のようなまつげからのぞく黒水晶のような瞳が、怒りの感情に染まっている。
その視線の先には、タンポポがいた。
ようすがおかしい。
目がすわっているし、顔色がわるい。
タルヒさんに、憑りつかれているんだ。
「タンポポ……」
「チカナ。これ以上、近づくな」
レンゲの腕から降りようとしたけれど、再び抱きなおされてしまう。
でも、このままここで見ているだけなんてできないよ。
「タンポポを助けよう、レンゲ!」
すると、レンゲは操られているタンポポを視界に捉え、気難しそうに眉をひそめた。
これは、レンゲが「それはできない」というときに見せるときの表情だ。
ずっといっしょにいたから、わかってしまい、胸が締めつけられる。
ヤクモが、静かに言葉をつむぐ。
「ヤタガラスは、太陽の化身。怒らせれば、ますます炎を強めさせてしまう。ナズナさまを怒られてしまったら、彼女の気が収まるまで、何もすることはできない……」
ヤクモがいい終わると同時に、ナズナさまの炎がタンポポめがけて襲いかかった。
あたりに強い炎が渦巻く、轟音が響き渡る。
わたしは、必死に叫んだ。
「だめ! ナズナさま!」
わたしはけもの道を歩くのに、すぐにバテはじめていた。
昔は遊びながら歩いていたから、ひたすら森のなかを歩き続けるのには、慣れていないんだ。
わたしのようすに、すぐに気づいたレンゲが、モクレンを呼び止める。
「待て、アカギツネ」
「んあ? どうかしたんか」
「チカナを休憩させてやりたい」
いいながら、レンゲがわたしを横抱きにする。
「ちょ、ちょっと、レンゲ! わたしなら大丈夫だから!」
「これで、休憩できるな。急ごう」
「……チカナちゃんの忠実なしもべ。かなわんなあ。ほな、はよ行こか」
わたしの反応にかまわず、レンゲとモクレンは一直線に走り出す。
すごいスピードで、森の景色が通り過ぎて行く。
わたしは、思わずレンゲの服を握りしめた。
「……こわいか? 目をつむっていろ」
「うん……」
大人しく、目をつむる。
なんだか、心臓がどきどきしている。
わたしが、ジェットコースターを苦手だからかな。
「アカギツネ」
「どうしたん」
「何か、聞こえるな」
「ほんまや。さすが、コチカ・キノ。耳がええなあ」
わたしには、何も聞こえない。
やっぱり、レンゲとモクレンは、人間よりも耳がいいんだ。
「蓮の花のにおいがする。この先に、やつがいる」
「見つけたんだね。レンゲ」
「でも、よくない気配もする」
レンゲが、表情をくもらせた。
「それって……?」
「さっき、アカギツネのキセルを拾った……あいつだ」
「あの女の人……?」
緑がうっそうと茂った森のなか、見覚えのある後ろ姿を見つけた。
「……ヤクモ!」
隣には、シロツメもいる。
振り返ったヤクモがわたしを見て、駆け寄ってきてくれる。
「チカナ、どうした? ケガでもしたのか」
レンゲに抱きあげられたままのわたしを、ヤクモが心配そうに見つめる。
「そ、そうだった。ごめん、レンゲ。もう降ろしてくれていいよ」
「もう、回復したのか」
「うん」
そっと降ろしてくれるレンゲに、わたしはお礼をいう。
すると、ヤクモが自分よりも背の高いレンゲを、冷ややかに見あげた。
「チカナが疲れたからって、抱きあげて運んでやるのは、甘やかしすぎなんじゃないか。レンゲ」
「おれの主人はチカナだ。チカナの命令じゃないことに耳を傾ける必要はない」
「……まったく」
ひそひそと、ふたりでいいあってるけど、声が小さすぎて、わたしには聞こえない。
いつのまに仲良しになったんだろう、ふたりとも。
モクレンが、きょろきょろとあたりを見渡している。
「ヤクモくん、ナズナさまは……?」
「怒り狂ってるよ」
「ですかー……」
「タルヒさんが、タンポポを放さないんだ――『憑りついてしまって』て」
「え……」
「そのせいで、ナズナさまがちからを使いはじめちゃったんだ」
「……まーじか」
あきらかに動揺しはじめたモクレンが、キセルを吸いはじめる。
ヨモギのにおいをくゆらせながら、ぷかりと白い煙をはいた。
「ねえ、ナズナさま……大丈夫なの?」
あたりに、ヨモギのいいにおいが漂いはじめると、モクレンも少し落ち着きを取り戻したようだ。
「ナズナさまは……コローネ・キノ、ハシボソカラスのキノ・キランや。それでいて、キノ・キランの最長老。チカナちゃんは、ハシボソガラスの寿命、知っとる?」
「寿命は、知らないけど……」
ヤクモがわたしの隣に立ち、代わりに答えてくれる。
「よくいって、十年から二十年。長く生きるカラスでも、二十年といわれている。でも、カラスより長生きなキノ・キランは、たくさんいるよ。ホッキョククジラは約二百年、ガラパゴスゾウガメは約百七十年。クラゲなんかは、不老不死だっていわれている種類もいるくらいだ」
「え……? でも、ナズナさまって、キノ・キランの最長老なんだよね?」
「ああ。それは、ナズナさまが『ヤタガラス』のチカラを持っているからだ」
「ヤタガラス……?」
首をかしげるわたしに、今度はシロツメが説明してくれる。
「ヤタガラスっていうのはね、三本足のカラスのこと。日本の神話に出てくる、太陽の化身なんだってさ」
「つまり、ヤタガラスは、神さまの使いみたいなものってこと? だから、最長老なんだ?」
話が終わったタイミングで、モクレンがぐしゃぐしゃと髪の毛をかき混ぜた。
「ヤタガラスの炎は、すべてを焼き尽くすんや。だから、あんまり暴走させたない……ったく。ナズナさまは、どこに行ったんや!」
しびれを切らしたモクレンが、キセルをにぎりしめ叫び出す。
「落ち着け、アカギツネ」
たしなめるように、レンゲがいう。
「シロツメ。蓮の花のにおいは、どないしたんや」
「それなんだよね……」
シロツメが自分の鼻を突きながら、くちびるを尖らせる。
「ここに来たとたん、鼻がいうことを効かなくなったんだ。だから、ここで立ち往生してたってわけ〜」
がっくりとうなだれる、モクレン。
「くそっ。ナズナさまが取り返しのつかんことする前に、なんとかせな……」
そのとき、レンゲとシロツメが顔を上げた。
「なんだか……コゲくさいにおいがしないか?」
レンゲがあたりを見渡すと、シロツメが、パッと顔をあげた。
「そっか。それのせいで、蓮の花のにおいが判別つかなくなっていたんだ」
「この先からや!」
とたん、走り出すモクレン。
「おれたちも行くぞ。シロツメ!」
「うん」
ヤクモとシロツメも、モクレンを追っていってしまう。
すると、レンゲが当然のようにわたしを抱きあげた。
たしかに、わたしはレンゲより走るのが遅いけど。
「じ、自分で走れるよ」
「こうさせてくれたほうが、おまえのすがたを確認できて、おれは安心できる。いいだろう? おれのマスター」
レンゲが、ジッとわたしを見つめる。
そんなふうにいわれちゃったら、黙って抱きあげられるしかないよ。
何もいわないわたしを、肯定を受け取ったのか、レンゲもみんなを追いかけて走り出した。
しばらく行くと、わたしにも判るほどのコゲくさいにおいが漂ってきた。
少し行った先に、開けた空間があり、中央に真っ黒い長じゅばんを身にまとった、ナズナさまが立っていた。
じゅばんをまとったそのすがたに、ゆらゆらと燃える赤い炎をまとっている。
これが、ヤタガラスのキノ・キラン――。
木の葉が、ふぶきみたいに舞い散り、ナズナさまの炎に焼かれ、焦げていく。
「ナズナさま!」
モクレンが叫んだ。
だけど、ナズナさまには聞こえていないみたい。
「くそ。ああなると、誰の声も届かへん……!」
羽のようなまつげからのぞく黒水晶のような瞳が、怒りの感情に染まっている。
その視線の先には、タンポポがいた。
ようすがおかしい。
目がすわっているし、顔色がわるい。
タルヒさんに、憑りつかれているんだ。
「タンポポ……」
「チカナ。これ以上、近づくな」
レンゲの腕から降りようとしたけれど、再び抱きなおされてしまう。
でも、このままここで見ているだけなんてできないよ。
「タンポポを助けよう、レンゲ!」
すると、レンゲは操られているタンポポを視界に捉え、気難しそうに眉をひそめた。
これは、レンゲが「それはできない」というときに見せるときの表情だ。
ずっといっしょにいたから、わかってしまい、胸が締めつけられる。
ヤクモが、静かに言葉をつむぐ。
「ヤタガラスは、太陽の化身。怒らせれば、ますます炎を強めさせてしまう。ナズナさまを怒られてしまったら、彼女の気が収まるまで、何もすることはできない……」
ヤクモがいい終わると同時に、ナズナさまの炎がタンポポめがけて襲いかかった。
あたりに強い炎が渦巻く、轟音が響き渡る。
わたしは、必死に叫んだ。
「だめ! ナズナさま!」