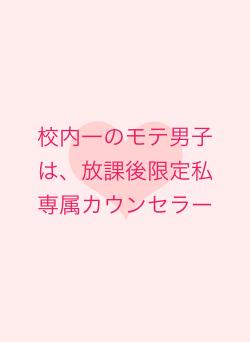「紗都」
私の名を呼ぶ目の前の男。
「あの日、久しぶりに客が来たんだと思ったんだ」
何の話を始めているのか分からない。
「どうせ俺のうわさを聞いてからかいに来たやつか、馬鹿にしに来たやつだと思った」
「でも、目の前の少女は楽しそうに読書を始めたんだ。コロコロと表情を変えながら、心底楽しそうに物語に入り込んで」
「俺が出て行ったら怖がって店を出ていくかもしれない。それでも、本を楽しそうに読む少女を見ているのが楽しくて、目で追っているうちに少女はウトウトと眠りについた。やっと怖がらせずに済むと思って近づいたんだ」
「少女が起きるのを待っているうちに、俺もつい眠ってしまった。そして夢の中で少女の声が聞こえたんだ」
「恋愛小説のヒーローみたい」
「なぁ、紗都。お前には俺が本の中の登場人物のようにきらめいて見えたのか? あんなにお前が楽しそうに読んでいる本の登場人物と俺が同じだと言ったのか?」
そう話す柊斗の声は今まで一番優しくて。
私の名を呼ぶ目の前の男。
「あの日、久しぶりに客が来たんだと思ったんだ」
何の話を始めているのか分からない。
「どうせ俺のうわさを聞いてからかいに来たやつか、馬鹿にしに来たやつだと思った」
「でも、目の前の少女は楽しそうに読書を始めたんだ。コロコロと表情を変えながら、心底楽しそうに物語に入り込んで」
「俺が出て行ったら怖がって店を出ていくかもしれない。それでも、本を楽しそうに読む少女を見ているのが楽しくて、目で追っているうちに少女はウトウトと眠りについた。やっと怖がらせずに済むと思って近づいたんだ」
「少女が起きるのを待っているうちに、俺もつい眠ってしまった。そして夢の中で少女の声が聞こえたんだ」
「恋愛小説のヒーローみたい」
「なぁ、紗都。お前には俺が本の中の登場人物のようにきらめいて見えたのか? あんなにお前が楽しそうに読んでいる本の登場人物と俺が同じだと言ったのか?」
そう話す柊斗の声は今まで一番優しくて。