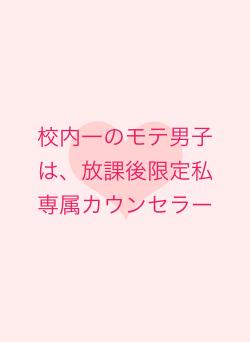「紗都」
私の名を呼んで、その男が一歩、また一歩と近づいてくる。
「なんで俺が執着していると思う?」
「昨日言ってたでしょ。私の膝の上で寝れたのが珍しかったって」
「違う」
柊斗が私の髪に触れた。
雨に濡れて顔に引っ付いている髪を掬うように持ち上げる。
「紗都、俺のこと怖い?」
「……怖い時もあるけれど、いつも怖いわけじゃない」
「そういうとこ。それと……」
柊斗が私の濡れた髪にキスを落とす。
訳がわからないのに、勝手に顔に熱が集まっていく。
「強がっているのに、顔だけ真っ赤になるところも好物。昨日も顔が赤くなっていたの気づいていた?」
知らない。
だって自分の顔なんて鏡でもないと分かるはずない。
本の匂いと濡れた雨の匂いが混じるような空間。
私の名を呼んで、その男が一歩、また一歩と近づいてくる。
「なんで俺が執着していると思う?」
「昨日言ってたでしょ。私の膝の上で寝れたのが珍しかったって」
「違う」
柊斗が私の髪に触れた。
雨に濡れて顔に引っ付いている髪を掬うように持ち上げる。
「紗都、俺のこと怖い?」
「……怖い時もあるけれど、いつも怖いわけじゃない」
「そういうとこ。それと……」
柊斗が私の濡れた髪にキスを落とす。
訳がわからないのに、勝手に顔に熱が集まっていく。
「強がっているのに、顔だけ真っ赤になるところも好物。昨日も顔が赤くなっていたの気づいていた?」
知らない。
だって自分の顔なんて鏡でもないと分かるはずない。
本の匂いと濡れた雨の匂いが混じるような空間。