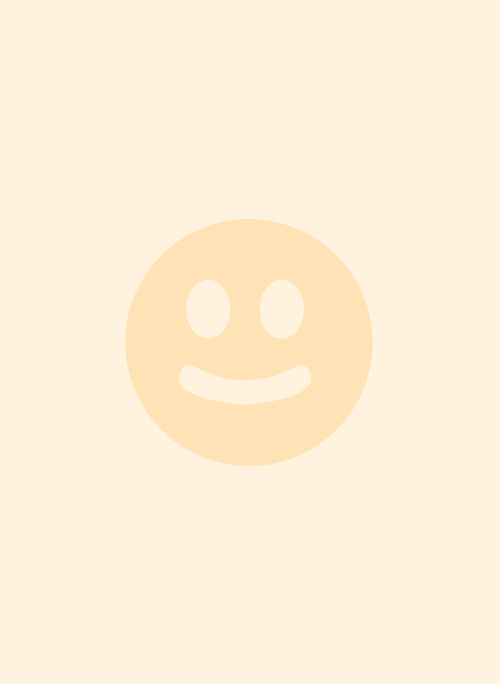朝焼けの光は、まだ眠る街の輪郭を静かになぞっていた。
皇居外苑──広大な緑に囲まれたこの場所は、都心にあってなお、時間の流れがどこか別の場所のように緩やかだった。
芝生の上には朝露がきらめき、石畳には清掃員のホウキの音だけが響いている。
美里は、ひとりベンチに腰かけていた。
手には温かいコーヒー、足元には小さなリュック。
泰雅に誘われた“早朝のジョギング”には、まだ信じがたい気持ちでいた。
──まさか、彼がジョギングをする人だったなんて。
想像とは違って、泰雅は意外にも“朝の時間”をとても大切にしていた。
深夜に音楽スタジオで過ごし、数時間だけ仮眠を取って──今また、美里を誘ってこの場所に現れた。
「待たせた?」
声とともに振り向くと、そこにいたのは、スポーツウェア姿の泰雅だった。
夜のスーツ姿とはまったく異なる彼の印象に、美里は思わず息を呑んだ。
髪はラフに撫でつけられ、無駄のない動きに身体のラインが浮かぶ。
けれど何より、彼の瞳が、朝の光に照らされてやわらかく輝いていた。
「……似合いますね。こういう格好も。」
「嬉しいよ、そう言ってもらえると。」
笑いながら隣に腰を下ろし、泰雅はペットボトルの水をひと口含む。
「美里も、朝の空気が好きそうだ。」
「はい。……子どもの頃、よく父と朝の散歩をしてました。空が明るくなるのを見るのが、好きでした。」
「それ、俺も同じだ。」
ふたりは同時に空を仰いだ。
朝焼けのグラデーションが、濃紺から紫、そしてやがて金色へと変わりゆく。
──言葉がいらない、静けさ。
──この人といる時間のすべてが、満たされている。
そんな感覚に包まれながら、美里はゆっくりと立ち上がる。
「走ってみます?」
「もちろん。」
ふたりはゆっくりと、皇居の周囲を走り出した。
最初はぎこちなかったペースも、次第に呼吸が合い、まるで見えないリズムに導かれるように自然と並んでいた。
ふと、風の中に何か違和感が混じる。
──キン……キィン……という、微細な金属音。
美里が足を止めた瞬間、頭の中にふわりと“声”が響いた。
《あぶない、しゃがんで! 右、今すぐ右へ!》
──えっ?
誰の声か、思考する間もなく身体が勝手に動いた。
咄嗟に右手で泰雅の腕を引き、横に跳ねるように身をかわす。
次の瞬間、轟音。
頭上から突如、黒い影が落ちてきた。
それは、人の顔ほどもあるドローンだった。
パーツの一部が折れ、火花を散らしながら、ふたりがさっきまでいた場所に激突する。
「……!」
泰雅は、美里を抱きかかえるようにして地面に倒れ込んでいた。
衝撃の直後、辺りは静まり返る。
ただ、コンクリートにぶつかってひしゃげたドローンの機体だけが、異様な存在感を放っていた。
「大丈夫か!?」
泰雅の声が頭上で響く。
美里は、小刻みに震えながらも頷いた。
「……はい……たぶん……」
「どうしてわかったんだ、あれが落ちてくるって……?」
その問いに、美里はすぐには答えられなかった。
けれど、耳の奥にまだ残る“妖精の声”が、確かに警告をくれたと分かっていた。
「声が、したんです。危ないって……」
「声?」
泰雅は目を細め、美里の頬に手を添えた。
震える身体をそのまま抱き寄せ、彼はその耳元で囁いた。
「……君がいてくれて、本当によかった。」
その低い声に、美里の心は一気にほどけた。
身体の芯まで染み込んだ恐怖が、彼の言葉ひとつで溶けていく。
──私が、この人を守った。
その事実が、信じられなかった。
そして、次の瞬間。
泰雅の唇が、そっと美里の額に触れた。
「ありがとう。」
それは、キスと呼ぶにはあまりにも優しく、けれど魂を震わせるほど深かった。
彼の体温、息遣い、そして声が、美里のすべてを包み込んでくる。
ふたりを取り巻く空気が変わった。
まるで、朝焼けの中でふたりだけの世界が開いたような錯覚。
そのとき、美里ははっきりと理解した。
──もう、引き返せない。
──私はこの人に、恋をしている。
救急車のサイレンが遠くで響いていたが、美里の耳には、何ひとつ届いていなかった。
朝の空気はすっかり黄金色に染まり、皇居外苑は荘厳な静けさに包まれていた。
泰雅の腕の中、彼の心音が、ゆっくりとしたリズムで伝わってくる。
その音が、美里の胸に、まだ鳴り止まない“恐怖”と“感動”の波紋を優しく吸い取っていた。
「ありがとう、本当に。あのままだったら……俺、君の前からいなくなってたかもしれない。」
「やめてください、そんなこと……」
美里は顔を上げ、思わず泣きそうな表情で彼を見た。
泰雅はその頬にふわりと触れると、いたずらっぽく微笑んだ。
「でも、助かった。君がいてくれたから。」
「……それは、私じゃなくて、妖精が……」
「いや、君が“聞いた”から助かったんだ。君じゃなきゃ、できなかったことだ。」
その言葉の重さに、美里の胸がまたきゅっと縮まる。
そして、彼の中で“自分”が、少しずつ“必要な存在”として根を張り始めているのだと、初めて実感した。
「今日は、このままどこか行こうか。」
唐突に提案された言葉に、美里は目を丸くした。
「え?」
「日が昇ってるのに、何もせず解散なんて、もったいない。」
そう言って彼は、スマートフォンを取り出し、何かに連絡を取り始める。
手際は滑らかで、けれどどこか楽しげだ。
「君が好きそうな場所、思い浮かんでる。」
「好きそうな……?」
「秘密。」
ふわっと笑ったその顔に、美里はまたしても心を奪われる。
ドローン事故という非常事態のあとなのに、彼といると不思議と緊張がほどけていく。
「着いたよ。」
移動した車が止まった先は、赤坂の小高い丘の上にある、都心では珍しい隠れ家カフェだった。
全面ガラス張りのテラス席からは、東京タワーと朝陽が交差するように見える。
さっきまでいた場所とはまるで違う、穏やかな別世界。
席に案内され、ふたりが向かい合って座ると、泰雅はふっと視線を外した。
「実は、俺……高いところが苦手なんだ。」
「え?」
「でも、君と一緒なら、どんな景色も好きになれる気がする。」
恥ずかしそうに言いながらも、真っすぐな目を逸らさず、彼は続けた。
「さっき、君が俺を引っ張ってくれたとき、頭が真っ白になった。でも……君の手のぬくもりだけは、ちゃんと覚えてる。」
「……私も、あなたを守りたいって、心から思いました。」
「じゃあ、これから先、ずっと一緒にいてくれる?」
美里は、その一言の重みに戸惑った。
でも、うなずきたくなる自分がいる。
まだ“付き合ってください”という言葉はない。
けれど、それよりも真っ直ぐで、強い何かがその中に込められている気がした。
「私でいいんですか?」
「“私でいい”じゃなく、“君がいい”。」
言葉が、真っすぐに心に届く。
そして次の瞬間──
泰雅の手が、美里の手をそっと握った。
「この先、どんな未来が待っているとしても、君となら越えていける気がする。」
その言葉に、目の奥が熱くなる。
「……私も、あなたとなら。」
その小さな“約束”のようなやりとりが、朝焼けに染まる光景の中でゆっくりと重なった。
カフェを出たふたりは、再び車に乗り込んだ。
けれど、美里は思い切って言った。
「……もう少し、歩いてもいいですか?」
「もちろん。」
手を繋いで歩く道。
行き交う人々はまだ少なく、世界がふたりだけに許された空間に見えた。
皇居の外堀へ戻るころには、太陽は完全に登っていた。
水面に映る光が踊り、風がふたりの髪をふわりと撫でる。
「朝って、好きです。」
「俺も。新しい何かが始まる気がするから。」
「始まる……ですか?」
「うん。君と俺の物語も、今日から本当に始まる。」
そう言って、泰雅は再び、美里の額にキスをした。
今度は、確信を込めて。
そのぬくもりは、もう一瞬ではなかった。
ふたりの間にある“想い”が、確かなものへと変わっていく予感があった。
言葉を超えた音、奇跡のような出会い、そして──
朝焼けの中で交わした、ふたりだけの“最初のキス”。
それは、美里の世界をまるごと変える、運命の証だった。
【第5章『運命に導かれた一瞬の奇跡』 終】
皇居外苑──広大な緑に囲まれたこの場所は、都心にあってなお、時間の流れがどこか別の場所のように緩やかだった。
芝生の上には朝露がきらめき、石畳には清掃員のホウキの音だけが響いている。
美里は、ひとりベンチに腰かけていた。
手には温かいコーヒー、足元には小さなリュック。
泰雅に誘われた“早朝のジョギング”には、まだ信じがたい気持ちでいた。
──まさか、彼がジョギングをする人だったなんて。
想像とは違って、泰雅は意外にも“朝の時間”をとても大切にしていた。
深夜に音楽スタジオで過ごし、数時間だけ仮眠を取って──今また、美里を誘ってこの場所に現れた。
「待たせた?」
声とともに振り向くと、そこにいたのは、スポーツウェア姿の泰雅だった。
夜のスーツ姿とはまったく異なる彼の印象に、美里は思わず息を呑んだ。
髪はラフに撫でつけられ、無駄のない動きに身体のラインが浮かぶ。
けれど何より、彼の瞳が、朝の光に照らされてやわらかく輝いていた。
「……似合いますね。こういう格好も。」
「嬉しいよ、そう言ってもらえると。」
笑いながら隣に腰を下ろし、泰雅はペットボトルの水をひと口含む。
「美里も、朝の空気が好きそうだ。」
「はい。……子どもの頃、よく父と朝の散歩をしてました。空が明るくなるのを見るのが、好きでした。」
「それ、俺も同じだ。」
ふたりは同時に空を仰いだ。
朝焼けのグラデーションが、濃紺から紫、そしてやがて金色へと変わりゆく。
──言葉がいらない、静けさ。
──この人といる時間のすべてが、満たされている。
そんな感覚に包まれながら、美里はゆっくりと立ち上がる。
「走ってみます?」
「もちろん。」
ふたりはゆっくりと、皇居の周囲を走り出した。
最初はぎこちなかったペースも、次第に呼吸が合い、まるで見えないリズムに導かれるように自然と並んでいた。
ふと、風の中に何か違和感が混じる。
──キン……キィン……という、微細な金属音。
美里が足を止めた瞬間、頭の中にふわりと“声”が響いた。
《あぶない、しゃがんで! 右、今すぐ右へ!》
──えっ?
誰の声か、思考する間もなく身体が勝手に動いた。
咄嗟に右手で泰雅の腕を引き、横に跳ねるように身をかわす。
次の瞬間、轟音。
頭上から突如、黒い影が落ちてきた。
それは、人の顔ほどもあるドローンだった。
パーツの一部が折れ、火花を散らしながら、ふたりがさっきまでいた場所に激突する。
「……!」
泰雅は、美里を抱きかかえるようにして地面に倒れ込んでいた。
衝撃の直後、辺りは静まり返る。
ただ、コンクリートにぶつかってひしゃげたドローンの機体だけが、異様な存在感を放っていた。
「大丈夫か!?」
泰雅の声が頭上で響く。
美里は、小刻みに震えながらも頷いた。
「……はい……たぶん……」
「どうしてわかったんだ、あれが落ちてくるって……?」
その問いに、美里はすぐには答えられなかった。
けれど、耳の奥にまだ残る“妖精の声”が、確かに警告をくれたと分かっていた。
「声が、したんです。危ないって……」
「声?」
泰雅は目を細め、美里の頬に手を添えた。
震える身体をそのまま抱き寄せ、彼はその耳元で囁いた。
「……君がいてくれて、本当によかった。」
その低い声に、美里の心は一気にほどけた。
身体の芯まで染み込んだ恐怖が、彼の言葉ひとつで溶けていく。
──私が、この人を守った。
その事実が、信じられなかった。
そして、次の瞬間。
泰雅の唇が、そっと美里の額に触れた。
「ありがとう。」
それは、キスと呼ぶにはあまりにも優しく、けれど魂を震わせるほど深かった。
彼の体温、息遣い、そして声が、美里のすべてを包み込んでくる。
ふたりを取り巻く空気が変わった。
まるで、朝焼けの中でふたりだけの世界が開いたような錯覚。
そのとき、美里ははっきりと理解した。
──もう、引き返せない。
──私はこの人に、恋をしている。
救急車のサイレンが遠くで響いていたが、美里の耳には、何ひとつ届いていなかった。
朝の空気はすっかり黄金色に染まり、皇居外苑は荘厳な静けさに包まれていた。
泰雅の腕の中、彼の心音が、ゆっくりとしたリズムで伝わってくる。
その音が、美里の胸に、まだ鳴り止まない“恐怖”と“感動”の波紋を優しく吸い取っていた。
「ありがとう、本当に。あのままだったら……俺、君の前からいなくなってたかもしれない。」
「やめてください、そんなこと……」
美里は顔を上げ、思わず泣きそうな表情で彼を見た。
泰雅はその頬にふわりと触れると、いたずらっぽく微笑んだ。
「でも、助かった。君がいてくれたから。」
「……それは、私じゃなくて、妖精が……」
「いや、君が“聞いた”から助かったんだ。君じゃなきゃ、できなかったことだ。」
その言葉の重さに、美里の胸がまたきゅっと縮まる。
そして、彼の中で“自分”が、少しずつ“必要な存在”として根を張り始めているのだと、初めて実感した。
「今日は、このままどこか行こうか。」
唐突に提案された言葉に、美里は目を丸くした。
「え?」
「日が昇ってるのに、何もせず解散なんて、もったいない。」
そう言って彼は、スマートフォンを取り出し、何かに連絡を取り始める。
手際は滑らかで、けれどどこか楽しげだ。
「君が好きそうな場所、思い浮かんでる。」
「好きそうな……?」
「秘密。」
ふわっと笑ったその顔に、美里はまたしても心を奪われる。
ドローン事故という非常事態のあとなのに、彼といると不思議と緊張がほどけていく。
「着いたよ。」
移動した車が止まった先は、赤坂の小高い丘の上にある、都心では珍しい隠れ家カフェだった。
全面ガラス張りのテラス席からは、東京タワーと朝陽が交差するように見える。
さっきまでいた場所とはまるで違う、穏やかな別世界。
席に案内され、ふたりが向かい合って座ると、泰雅はふっと視線を外した。
「実は、俺……高いところが苦手なんだ。」
「え?」
「でも、君と一緒なら、どんな景色も好きになれる気がする。」
恥ずかしそうに言いながらも、真っすぐな目を逸らさず、彼は続けた。
「さっき、君が俺を引っ張ってくれたとき、頭が真っ白になった。でも……君の手のぬくもりだけは、ちゃんと覚えてる。」
「……私も、あなたを守りたいって、心から思いました。」
「じゃあ、これから先、ずっと一緒にいてくれる?」
美里は、その一言の重みに戸惑った。
でも、うなずきたくなる自分がいる。
まだ“付き合ってください”という言葉はない。
けれど、それよりも真っ直ぐで、強い何かがその中に込められている気がした。
「私でいいんですか?」
「“私でいい”じゃなく、“君がいい”。」
言葉が、真っすぐに心に届く。
そして次の瞬間──
泰雅の手が、美里の手をそっと握った。
「この先、どんな未来が待っているとしても、君となら越えていける気がする。」
その言葉に、目の奥が熱くなる。
「……私も、あなたとなら。」
その小さな“約束”のようなやりとりが、朝焼けに染まる光景の中でゆっくりと重なった。
カフェを出たふたりは、再び車に乗り込んだ。
けれど、美里は思い切って言った。
「……もう少し、歩いてもいいですか?」
「もちろん。」
手を繋いで歩く道。
行き交う人々はまだ少なく、世界がふたりだけに許された空間に見えた。
皇居の外堀へ戻るころには、太陽は完全に登っていた。
水面に映る光が踊り、風がふたりの髪をふわりと撫でる。
「朝って、好きです。」
「俺も。新しい何かが始まる気がするから。」
「始まる……ですか?」
「うん。君と俺の物語も、今日から本当に始まる。」
そう言って、泰雅は再び、美里の額にキスをした。
今度は、確信を込めて。
そのぬくもりは、もう一瞬ではなかった。
ふたりの間にある“想い”が、確かなものへと変わっていく予感があった。
言葉を超えた音、奇跡のような出会い、そして──
朝焼けの中で交わした、ふたりだけの“最初のキス”。
それは、美里の世界をまるごと変える、運命の証だった。
【第5章『運命に導かれた一瞬の奇跡』 終】