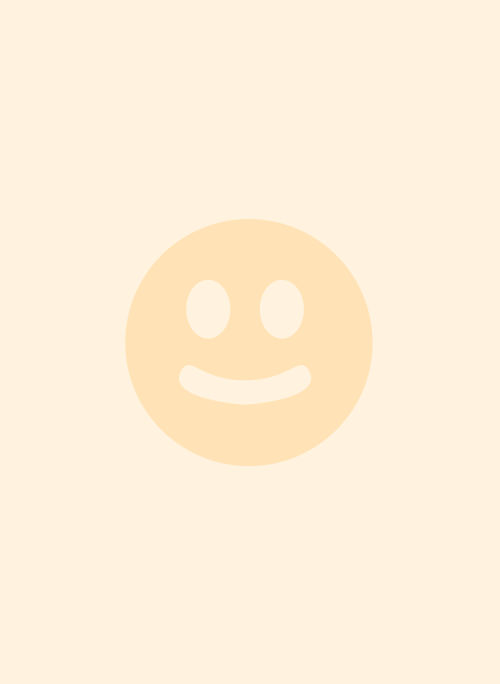5月5日、こどもの日。
銀座の朝は、いつもよりも静かだった。
だがその静寂は、まるで何かが“始まる予感”を含んでいるように、鼓動のような熱を帯びていた。
「……んっ、……っ」
美里は、額に汗を滲ませながら、ベッドの縁に手を添えていた。
陣痛。
予兆は、夜明けと同時にやってきた。
最初は鈍い痛み、やがて波のように規則的な痙攣となって、確実に彼女の身体の内側から“命の扉”を叩いていた。
「……きた、今度こそ本格的に……」
スマートフォンを手に取り、画面を開く。
【タイガ】
わずかな迷いもなく、彼にコールする。
「……美里?」
電話の向こう、眠そうな声が一瞬で鋭くなる。
「……いま、来て、お願い……」
その一言で、彼はすべてを理解した。
わずか数分後、銀座上空にヘリのプロペラ音が響いた。
ヘリの扉が開くと、泰雅が全速力で駆け寄ってきた。
額には汗、手には母子手帳と緊急キット、そしてその表情には、ただひたすらな焦りと愛しさが滲んでいた。
「美里、乗って。もう準備は全部整ってるから」
「……うん……っ」
彼女を両腕で抱き上げ、ヘリに乗り込むと、すぐに扉が閉まり、プロペラの風が銀座の空を舞い上げた。
機内では、美里の手を強く握ったまま、泰雅が何度も呼吸を整えさせてくれる。
「吸って、吐いて。……そう、それでいい。大丈夫。俺がそばにいる」
視界が霞む中、彼の声だけが、美里の意識を支えていた。
やがて、産院の屋上に到着すると、医師団が待ち受けていた。
そのなかには、かつて泰雅が会長の手術を任せた外科医もいた。
「安全にお預かりします。ご主人、立ち会いも可能です」
「……当然だ」
病室の天井の白さが、まるで光の世界へ導くゲートのように感じられる。
そして──
産声。
「おぎゃあ、……おぎゃあ!」
その瞬間、時間が止まった。
医師が赤ん坊を高く抱き上げ、「男児です」と告げる。
そしてその目を開いた赤ん坊が、美里の胸に抱かれると──ふわりと、小さく笑ったように見えた。
「……この子、“光”みたいな子だね」
美里が呟いたその声に、泰雅はそっと頷く。
「名前は、もう決めてある。“光希(こうき)”。光に、希望の“希”。君が運んできてくれたすべてに、感謝して」
彼の声に、光希はまるで応えるように、小さく指を動かした。
【第39章『あの日の笑顔を超えて』 終】
銀座の朝は、いつもよりも静かだった。
だがその静寂は、まるで何かが“始まる予感”を含んでいるように、鼓動のような熱を帯びていた。
「……んっ、……っ」
美里は、額に汗を滲ませながら、ベッドの縁に手を添えていた。
陣痛。
予兆は、夜明けと同時にやってきた。
最初は鈍い痛み、やがて波のように規則的な痙攣となって、確実に彼女の身体の内側から“命の扉”を叩いていた。
「……きた、今度こそ本格的に……」
スマートフォンを手に取り、画面を開く。
【タイガ】
わずかな迷いもなく、彼にコールする。
「……美里?」
電話の向こう、眠そうな声が一瞬で鋭くなる。
「……いま、来て、お願い……」
その一言で、彼はすべてを理解した。
わずか数分後、銀座上空にヘリのプロペラ音が響いた。
ヘリの扉が開くと、泰雅が全速力で駆け寄ってきた。
額には汗、手には母子手帳と緊急キット、そしてその表情には、ただひたすらな焦りと愛しさが滲んでいた。
「美里、乗って。もう準備は全部整ってるから」
「……うん……っ」
彼女を両腕で抱き上げ、ヘリに乗り込むと、すぐに扉が閉まり、プロペラの風が銀座の空を舞い上げた。
機内では、美里の手を強く握ったまま、泰雅が何度も呼吸を整えさせてくれる。
「吸って、吐いて。……そう、それでいい。大丈夫。俺がそばにいる」
視界が霞む中、彼の声だけが、美里の意識を支えていた。
やがて、産院の屋上に到着すると、医師団が待ち受けていた。
そのなかには、かつて泰雅が会長の手術を任せた外科医もいた。
「安全にお預かりします。ご主人、立ち会いも可能です」
「……当然だ」
病室の天井の白さが、まるで光の世界へ導くゲートのように感じられる。
そして──
産声。
「おぎゃあ、……おぎゃあ!」
その瞬間、時間が止まった。
医師が赤ん坊を高く抱き上げ、「男児です」と告げる。
そしてその目を開いた赤ん坊が、美里の胸に抱かれると──ふわりと、小さく笑ったように見えた。
「……この子、“光”みたいな子だね」
美里が呟いたその声に、泰雅はそっと頷く。
「名前は、もう決めてある。“光希(こうき)”。光に、希望の“希”。君が運んできてくれたすべてに、感謝して」
彼の声に、光希はまるで応えるように、小さく指を動かした。
【第39章『あの日の笑顔を超えて』 終】