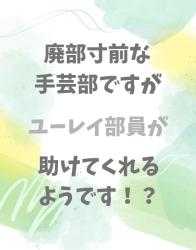「わ……っ」
びゅう、と、突風。
細い枝がしなって葉がひとひらふたひらと枝から離れて飛んでいく。
煽られた葉が渦を巻いてこちらへ一直線に向かってくるのを見て、とっさに腕をクロスさせて顔を覆った。
腕に冷たいものがぱたりと落ちる。
雨だ。
「うそ……っ」
ぽつ、ぽつ、ぽつり。
間隔をどんどん狭めながら、空から涙が降ってくる。
待って。まだ時雨さんと鳴神がいない。
ぐるぐると視線ばかりさまよわせて目が回る。
どうしよう。
このまま暗くなったらますます見つけにくくなる。
雨に打たれて黒ずんで、ぼろぼろになったてるてる坊主なんて、他の誰かが見つけたところで保護してくれやしない。
もう無理なの?
やっぱりあの時、彼らを追いかけて私も窓から落ちてれば良かった。
そうすれば離れ離れにならずに、ずっと――
「った!」
一瞬、痛いのかなんなのかわからなかった。
額に何かがぶつかった衝撃で息が止まる。
おそるおそる触れてみると前髪がびっしょり濡れていた。
大きな雨粒が当たったらしい。
「……時雨さん?」
そっと視線を上げていく。
そうだ、時雨さんは皆の中でもひと際背が高くて、話す時には見上げていたっけ。
時雨さんの落ち着いた物腰を思い出す。
こんな時、彼ならどうするだろう。闇雲に探し回ったりはしないはず。
足が自然と、トイレの真下の木に向かっていた。
そうだ、ポーチはここに落ちていた。
チャックが開いていたからみんなバラバラになって、晴人くんは車の屋根に落ちて八雲くんは車の下まで転がっていた。
それなら時雨さんは――
生い茂る木にぐっと目を凝らす。
暗くなってきたならなおのこと、白いティッシュは目立つはず。大丈夫。
ぴちょん、と音がした。そちらに目を向ければ、しなる枝の先に大きな葉がついている。
そこで受けた雨粒の重みに耐えかねて、時折跳ね返すように枝がしなっていた。
弾力のあるししおどしみたいだ。
ぴちょん。
アーチを描いた枝が雨を弾き返す。反動で葉が数枚跳ねた。
その奥に白いものが見えて――ジャンプして枝に飛びついて掻き分けた。
「時雨さん!」
葉から弾けた雨粒が顔にかかる。それでも負けずに手を伸ばす。
地面に足がつくと同時に、それは手の中に舞い降りてきた。
「……時雨さん……!」
ネイビーブルーのてるてる坊主が雨粒にぐっしょり濡れている。
ハンカチを押し当ててそっと水気を吸い取った。
「ありがとう、時雨さん……」
葉や枝に擦れた上に雨に濡れて、今にもぽろぽろと崩れそうな繊維が痛々しい。
そのままハンカチに包んでから上着のポケットにしまった。
びゅう、と、突風。
細い枝がしなって葉がひとひらふたひらと枝から離れて飛んでいく。
煽られた葉が渦を巻いてこちらへ一直線に向かってくるのを見て、とっさに腕をクロスさせて顔を覆った。
腕に冷たいものがぱたりと落ちる。
雨だ。
「うそ……っ」
ぽつ、ぽつ、ぽつり。
間隔をどんどん狭めながら、空から涙が降ってくる。
待って。まだ時雨さんと鳴神がいない。
ぐるぐると視線ばかりさまよわせて目が回る。
どうしよう。
このまま暗くなったらますます見つけにくくなる。
雨に打たれて黒ずんで、ぼろぼろになったてるてる坊主なんて、他の誰かが見つけたところで保護してくれやしない。
もう無理なの?
やっぱりあの時、彼らを追いかけて私も窓から落ちてれば良かった。
そうすれば離れ離れにならずに、ずっと――
「った!」
一瞬、痛いのかなんなのかわからなかった。
額に何かがぶつかった衝撃で息が止まる。
おそるおそる触れてみると前髪がびっしょり濡れていた。
大きな雨粒が当たったらしい。
「……時雨さん?」
そっと視線を上げていく。
そうだ、時雨さんは皆の中でもひと際背が高くて、話す時には見上げていたっけ。
時雨さんの落ち着いた物腰を思い出す。
こんな時、彼ならどうするだろう。闇雲に探し回ったりはしないはず。
足が自然と、トイレの真下の木に向かっていた。
そうだ、ポーチはここに落ちていた。
チャックが開いていたからみんなバラバラになって、晴人くんは車の屋根に落ちて八雲くんは車の下まで転がっていた。
それなら時雨さんは――
生い茂る木にぐっと目を凝らす。
暗くなってきたならなおのこと、白いティッシュは目立つはず。大丈夫。
ぴちょん、と音がした。そちらに目を向ければ、しなる枝の先に大きな葉がついている。
そこで受けた雨粒の重みに耐えかねて、時折跳ね返すように枝がしなっていた。
弾力のあるししおどしみたいだ。
ぴちょん。
アーチを描いた枝が雨を弾き返す。反動で葉が数枚跳ねた。
その奥に白いものが見えて――ジャンプして枝に飛びついて掻き分けた。
「時雨さん!」
葉から弾けた雨粒が顔にかかる。それでも負けずに手を伸ばす。
地面に足がつくと同時に、それは手の中に舞い降りてきた。
「……時雨さん……!」
ネイビーブルーのてるてる坊主が雨粒にぐっしょり濡れている。
ハンカチを押し当ててそっと水気を吸い取った。
「ありがとう、時雨さん……」
葉や枝に擦れた上に雨に濡れて、今にもぽろぽろと崩れそうな繊維が痛々しい。
そのままハンカチに包んでから上着のポケットにしまった。