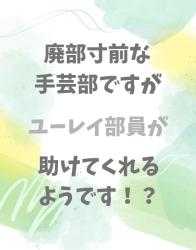「な、るかみ」
喉で固まった声が掠れていた。
でも、鳴神の注意を引きたくて語りかける。
「わ、たしなら、大丈夫だから。千結ちゃんも来てくれたし、あとは先生に話して……」
「は、何言ってんの!?」
私を引っぱたいた女子が目を剥く勢いで睨みつけてくる。
「元はと言えばあんたが出しゃばるからじゃない」
「っ、まだそんなこと言うの!?」
この状況でそれは火に油でしかない。
何のために私が鳴神を抑えようとしてるのか、何も伝わってない。
鳴神の目がその子を捉えた。
爪先が静かにそちらを向く。
チカチカと視界が明滅した。トイレの照明が不規則に瞬いて――ふっと消えた。
まだ夕方だから真っ暗にはならないけれど、このシチュエーションで薄暗い舞台装置はお誂え向きすぎた。
その瞬間、呪縛から解かれたように他の子たちがかたかたと震え出す。
「し、知らない! 私、その子に言われて来ただけだもの。御空なんてどうでもいいし!」
「わ、わたしも」
「関係ないでしょ、あたし、ただトイレにいただけだもん!」
ひとりがわめくと堰を切ったように二人目、三人目と騒ぎ出す。
千結ちゃんのスマホに収められた証拠写真があるから、その言い訳がどこまで通用するかわからないけれど、彼女たちは我先に逃げ出そうとトイレの入口に殺到した。
「ちょっとあんたたち、何いい子ぶってんの! そっちがやろうって言ったんじゃん!」
「知らない! 知らないってば!」
引き留めようとするリーダー格の女子を振り切った子が、入口にいた千結ちゃんを突き飛ばした。
「きゃあっ」
「千結ちゃ……、あ、ポーチ!」
今の子がポーチを持ったままなのに気がついて慌てて追いかける。
尻もちをつきかけた千結ちゃんは、時雨さんに抱き止められていた。
「待って!」
とっさに腕を掴むとものすごい勢いで振り払われる。
「こっち来ないで!」
ポーチさえ返してくれれば用はないのに。
パニックになっているのかちっとも話が通じない。
もう、埒が明かない!
「ポーチ、私の! 返してよっ」
上がった息が戻らないまま、途切れ途切れに怒鳴ると、その子はようやく自分が何を手にしているのか思い出したみたいだ。
「あ……」
呆然と見下ろすそれはジッパーが半端なところで下ろされたままだ。
「返して」
「いや! わたし何もしてない!」
興奮状態に陥っている彼女を刺激しないように、なるべく落ち着いて話しかけたつもりだったけど、その子には通じなかった。
手を伸ばすより先に、彼女の腕が勢いよく空を切る。
その放物線の先に、開けっ放しの窓が待ち構えているなんて出来すぎのシチュエーションだ。
放り出されたポーチからばら撒かれる中身は、まるで誕生日パーティのクラッカーみたいに色とりどりで。
目の覚めるようなレモンイエローが尾を描く。
太陽を集めたオレンジがきらめいて
空に灰色が溶け込んで
ネイビーブルーは涙のように一直線に――
「いやああっ!!」
4つのてるてる坊主が真っ逆さまに窓の外に落ちていく。
間に合うわけなんてないのに、追いかけて落ちていけば受け止められそうな気がして窓枠に飛びついて身を乗り出す。
一瞬、胃がひっくり返るような浮遊感で視界が歪んだ。
喉で固まった声が掠れていた。
でも、鳴神の注意を引きたくて語りかける。
「わ、たしなら、大丈夫だから。千結ちゃんも来てくれたし、あとは先生に話して……」
「は、何言ってんの!?」
私を引っぱたいた女子が目を剥く勢いで睨みつけてくる。
「元はと言えばあんたが出しゃばるからじゃない」
「っ、まだそんなこと言うの!?」
この状況でそれは火に油でしかない。
何のために私が鳴神を抑えようとしてるのか、何も伝わってない。
鳴神の目がその子を捉えた。
爪先が静かにそちらを向く。
チカチカと視界が明滅した。トイレの照明が不規則に瞬いて――ふっと消えた。
まだ夕方だから真っ暗にはならないけれど、このシチュエーションで薄暗い舞台装置はお誂え向きすぎた。
その瞬間、呪縛から解かれたように他の子たちがかたかたと震え出す。
「し、知らない! 私、その子に言われて来ただけだもの。御空なんてどうでもいいし!」
「わ、わたしも」
「関係ないでしょ、あたし、ただトイレにいただけだもん!」
ひとりがわめくと堰を切ったように二人目、三人目と騒ぎ出す。
千結ちゃんのスマホに収められた証拠写真があるから、その言い訳がどこまで通用するかわからないけれど、彼女たちは我先に逃げ出そうとトイレの入口に殺到した。
「ちょっとあんたたち、何いい子ぶってんの! そっちがやろうって言ったんじゃん!」
「知らない! 知らないってば!」
引き留めようとするリーダー格の女子を振り切った子が、入口にいた千結ちゃんを突き飛ばした。
「きゃあっ」
「千結ちゃ……、あ、ポーチ!」
今の子がポーチを持ったままなのに気がついて慌てて追いかける。
尻もちをつきかけた千結ちゃんは、時雨さんに抱き止められていた。
「待って!」
とっさに腕を掴むとものすごい勢いで振り払われる。
「こっち来ないで!」
ポーチさえ返してくれれば用はないのに。
パニックになっているのかちっとも話が通じない。
もう、埒が明かない!
「ポーチ、私の! 返してよっ」
上がった息が戻らないまま、途切れ途切れに怒鳴ると、その子はようやく自分が何を手にしているのか思い出したみたいだ。
「あ……」
呆然と見下ろすそれはジッパーが半端なところで下ろされたままだ。
「返して」
「いや! わたし何もしてない!」
興奮状態に陥っている彼女を刺激しないように、なるべく落ち着いて話しかけたつもりだったけど、その子には通じなかった。
手を伸ばすより先に、彼女の腕が勢いよく空を切る。
その放物線の先に、開けっ放しの窓が待ち構えているなんて出来すぎのシチュエーションだ。
放り出されたポーチからばら撒かれる中身は、まるで誕生日パーティのクラッカーみたいに色とりどりで。
目の覚めるようなレモンイエローが尾を描く。
太陽を集めたオレンジがきらめいて
空に灰色が溶け込んで
ネイビーブルーは涙のように一直線に――
「いやああっ!!」
4つのてるてる坊主が真っ逆さまに窓の外に落ちていく。
間に合うわけなんてないのに、追いかけて落ちていけば受け止められそうな気がして窓枠に飛びついて身を乗り出す。
一瞬、胃がひっくり返るような浮遊感で視界が歪んだ。