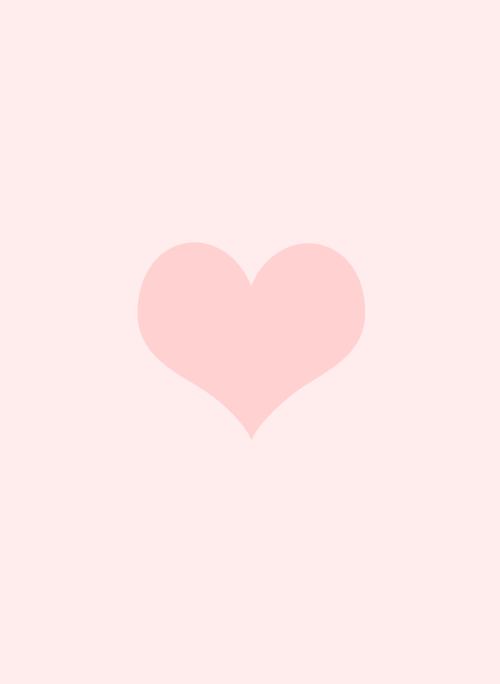そして言われた通り、他の幹部たちがいる会議室に戻る。
扉をノックすると、すぐに返事があった。
扉を開けて、礼をとる。
「律樹です。戻りました。」
「おかえり。どうだっ……」
不自然に止まった梨杜さんの言葉を不思議に思って顔を上げる。
中の人たちは驚いた顔をしていたが、オッドアイの女性、羽澄さんだけは落ち着いた様子でつぶやいた。
「どうしたの?」
そう言われて自分の服を見る。
おそらくレンを運んだ時についたのだろう、ベッタリと大量の血がついていた。
「……あぁ、僕のじゃないです。」
そもそも彼らは血なんて見慣れてるはずだ。
なのに何でそんなに狼狽える必要があるのか。
「いや、そうじゃなくて……」
梨杜さんが言った。
そうじゃないってことは。
「レンのものでも、龍星さんのものでもないですよ。」
「そういうことじゃなくて!」
梨杜さんが僕の肩を乱暴に掴んだ。
その顔は泣きそうだった。
「君、何があったの?」
蒼さんだった。
「誰に、何を言われたの?」
質問の意味がわからなかった。
「何も……。あの、どうしたんですか?」
「もしかして、自覚ない?」
自覚ってなんの?
僕が訳がわからずに困惑していると、蒼さんは呆れたように口を開いた。
「……梨杜姉、彼、いつもこうなの?」
「いや、大体は自分でわかってる……。これじゃまるで……。」
いつもこう?
自分でわかる?
一体何を言ってるんだ。
「つまり、今日だけなんだね。」
蒼さんはゆっくりと僕に近づいてきた。
そして、拳銃を僕の眉間に当てた。
「蒼!?」
「ねぇ律樹くん。僕が引き金を引いたら、君死んじゃうんだけど、どうする?」
どうするって言われても……。
「蒼さんがそう判断されたなら、大人しく殺されます。抵抗もしません。どうぞ、一思いにやってください。でも絶対に外さないでください。」
僕は目線を逸らすことも、怯えることもしないで言った。
どっちかというと、撃ってくれるならありがたかった。
「そう……。」
蒼さんは銃をしまった。
「あの……」
「律樹くん、今、君は異常だ。普通どれだけ肝が据わった人間でも、いきなり銃を突きつけられたら多少は狼狽えるし、動揺する。梨杜姉みたいにね。……でも君は全く反応しなかった。」
それは……それならそれでいいと思ったから……。
「自分の危うさを自覚しろ!」
蒼さんが珍しく声を荒らげ、強い言葉を使った。
「……僕が言いたいのはそれだけ。あとは梨杜姉の仕事だ。だから少し寝な。」
そう言うと、蒼さんは僕の鳩尾に思いっきりパンチを入れた。
「ぅ……」
短い呻き声をあげて、倒れることしかできなかった。
扉をノックすると、すぐに返事があった。
扉を開けて、礼をとる。
「律樹です。戻りました。」
「おかえり。どうだっ……」
不自然に止まった梨杜さんの言葉を不思議に思って顔を上げる。
中の人たちは驚いた顔をしていたが、オッドアイの女性、羽澄さんだけは落ち着いた様子でつぶやいた。
「どうしたの?」
そう言われて自分の服を見る。
おそらくレンを運んだ時についたのだろう、ベッタリと大量の血がついていた。
「……あぁ、僕のじゃないです。」
そもそも彼らは血なんて見慣れてるはずだ。
なのに何でそんなに狼狽える必要があるのか。
「いや、そうじゃなくて……」
梨杜さんが言った。
そうじゃないってことは。
「レンのものでも、龍星さんのものでもないですよ。」
「そういうことじゃなくて!」
梨杜さんが僕の肩を乱暴に掴んだ。
その顔は泣きそうだった。
「君、何があったの?」
蒼さんだった。
「誰に、何を言われたの?」
質問の意味がわからなかった。
「何も……。あの、どうしたんですか?」
「もしかして、自覚ない?」
自覚ってなんの?
僕が訳がわからずに困惑していると、蒼さんは呆れたように口を開いた。
「……梨杜姉、彼、いつもこうなの?」
「いや、大体は自分でわかってる……。これじゃまるで……。」
いつもこう?
自分でわかる?
一体何を言ってるんだ。
「つまり、今日だけなんだね。」
蒼さんはゆっくりと僕に近づいてきた。
そして、拳銃を僕の眉間に当てた。
「蒼!?」
「ねぇ律樹くん。僕が引き金を引いたら、君死んじゃうんだけど、どうする?」
どうするって言われても……。
「蒼さんがそう判断されたなら、大人しく殺されます。抵抗もしません。どうぞ、一思いにやってください。でも絶対に外さないでください。」
僕は目線を逸らすことも、怯えることもしないで言った。
どっちかというと、撃ってくれるならありがたかった。
「そう……。」
蒼さんは銃をしまった。
「あの……」
「律樹くん、今、君は異常だ。普通どれだけ肝が据わった人間でも、いきなり銃を突きつけられたら多少は狼狽えるし、動揺する。梨杜姉みたいにね。……でも君は全く反応しなかった。」
それは……それならそれでいいと思ったから……。
「自分の危うさを自覚しろ!」
蒼さんが珍しく声を荒らげ、強い言葉を使った。
「……僕が言いたいのはそれだけ。あとは梨杜姉の仕事だ。だから少し寝な。」
そう言うと、蒼さんは僕の鳩尾に思いっきりパンチを入れた。
「ぅ……」
短い呻き声をあげて、倒れることしかできなかった。