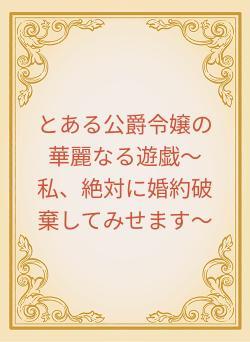「そうだよね。琥太郎くん、困らせてゴメン」
「いえいえ、立栞先輩が気にするのもわかりますし。てか、伊緒先輩なら本当に何かあっても全然心配ないっすよ〜。ま、これが史緒先輩だったら、オレも心配ですけどね」
最後にニヤリとほくそ笑み、そう付け加えた琥太郎くんに私は一瞬、目をパチパチとしばたたかせる。
「ふふっ。それ史緒くんが聞いてたら、絶対怒られるよ」
「ですね。でも、今いないんで問題なしです!!たまには、オレだって史緒先輩に言い返してやりたいんすよ〜。いっつもやられっぱなしなんで」
なんて琥太郎くんが茶化したように言うものだから私はついクスッと笑ってしまった。
きっと落ち込んでいる私を励ますためにわざとそんなノリで言ってくれたんだろう。
琥太郎くん、ありがとね。
心の中でそう呟いた私は「じゃ、クレープどんどん焼いて、千歳たちが帰ってきた時にビックリさせちゃおう」と彼に向かって、笑顔で声をかけたのだった。
ちなみにその後、2人で和気あいあいとクレープ作りに没頭した結果。
「ただいま〜!お!いい匂いじゃん。って、その生地の量いったい誰が食うんだよ……」
帰ってきた史緒くんを呆れさせてしまったのは、また別のお話――。