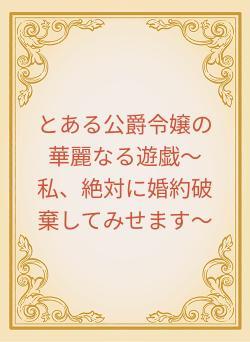そのことが1番憂鬱だった。
直球で話をしたって、お母さんが部活をすることを認めてくれるはずがないのは火を見るより明らか。
真田くんも、鈴城くんも成績はトップクラスで良いものの、中学生で髪を染めているなんて私の母からしたら言語道断。
おそらく見た目だけで「素行が悪い子とは付き合うな」と一蹴されるのがオチだ。
どう話したら、お母さんに部活に入ること認めてもらえるのかな…。
母にグラフィティ部に所属するメリットをどう説明しようか頭を悩ませる。
でも、いくら考えても一向に良い案は浮かばず…。
「あら?御井さん、まだいたの?もう図書室閉めるからね」
「はい!すみません。すぐ帰ります」
図書室の先生に声をかけられるまで、下校時間を過ぎていたことに気づかなかった。
慌てて帰り支度をし、図書室の先生に「さようなら」と会釈をした私は、急いで1階の下駄箱へ向かう。
…ハァ。やっぱりしばらくは、お母さんにナイショで活動するしかないよね。
それに、まだ岸くんが入部してくれないと部活も設立できないわけだし…。
靴を履き替え、校門をくぐり抜けた所で、ようやく達した結論。
しかし、結局は私に勇気がないのと、両親に反対されるのが怖いから、話すことができないことは心のどこかでわかっている。
私はそんな自分の意気地無さに対して、小さく肩を落としたのだった。