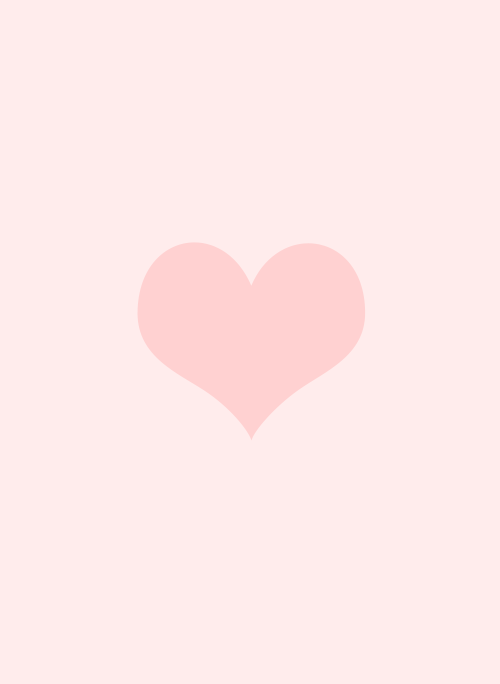ああ、あなたはなんて、わたしにとって最高の婚約者なんでしょう。
「ジュディス?」
きょとんと瞬きをした婚約者のヘイゼルを見つめる。
「わたし、あなたがくれたドレスを着たいわ」
『いつか、私的な場で、あなたがくださったドレスを着たいわ』
わたしが面倒くさがりだからいつでもお仕着せを着ているだけで、陛下に拝謁する夜以外、昼間はお仕着せでなくても構わないのである。
「あなたがくれたドレスを着て、あなたがくれた指輪をはめて仕事をしたいわ。そうしたら頑張れるもの」
見つめた先で、ヘイゼルが甘く伏せられた。
「……ジュディス。私を甘やかさないでくれ。これ以上いろいろ言いたくなったら困る」
吐息混じりの苦情に笑って、手を繋ぐ。
「わたしは困りませんわ。もっと言ってくれてもいいくらいよ。陛下とあなたからいただいたものがそばにあれば、いつでも心強いもの」
「私が困るんだ。まさか、仕事を放り出してきみのそばにいるわけにはいかない」
「ほら、そこで自分のことを言うあなただから、もっと言ってくれても構いませんの。ウィルはわたしの仕事を止めたり、部屋から出ないように言ったりはしないでしょう」
「それはもちろんしないが……」
もちろんと言う、あなただから。
もちろんと言う、あなたが。どれだけわたしにとって得がたい人か、ご自分では分かっていないんだわ。
「わたし、落ち着きのあるドレスが欲しいの。あなたの薄茶なら、上品で、普段使いしやすくて、華美になりすぎないわ。ぴったりだとは思いません?」
控えめな色で、既婚者としてふさわしいようにも思われる。
婚姻後に相談を受け付けるのであれば、それを鑑みて服装や場を設定しなくてはいけないわ。
わたしが結婚していれば、陛下とウィルのお守りがたくさんあれば、わたしも相談に来てくださる方も、お互い悪様に言われるのを避けられるでしょう。
「……きみには何色だって似合うとも」
呻くような低い声とともに腰を引き寄せられた。
「ありがとう存じます」
ウィルの返事があまりにも照れているとわかりやすかったものだから、思わずあげそうになった笑い声を、煌めくシャンパンとともに飲み込んだ。
「ジュディス?」
きょとんと瞬きをした婚約者のヘイゼルを見つめる。
「わたし、あなたがくれたドレスを着たいわ」
『いつか、私的な場で、あなたがくださったドレスを着たいわ』
わたしが面倒くさがりだからいつでもお仕着せを着ているだけで、陛下に拝謁する夜以外、昼間はお仕着せでなくても構わないのである。
「あなたがくれたドレスを着て、あなたがくれた指輪をはめて仕事をしたいわ。そうしたら頑張れるもの」
見つめた先で、ヘイゼルが甘く伏せられた。
「……ジュディス。私を甘やかさないでくれ。これ以上いろいろ言いたくなったら困る」
吐息混じりの苦情に笑って、手を繋ぐ。
「わたしは困りませんわ。もっと言ってくれてもいいくらいよ。陛下とあなたからいただいたものがそばにあれば、いつでも心強いもの」
「私が困るんだ。まさか、仕事を放り出してきみのそばにいるわけにはいかない」
「ほら、そこで自分のことを言うあなただから、もっと言ってくれても構いませんの。ウィルはわたしの仕事を止めたり、部屋から出ないように言ったりはしないでしょう」
「それはもちろんしないが……」
もちろんと言う、あなただから。
もちろんと言う、あなたが。どれだけわたしにとって得がたい人か、ご自分では分かっていないんだわ。
「わたし、落ち着きのあるドレスが欲しいの。あなたの薄茶なら、上品で、普段使いしやすくて、華美になりすぎないわ。ぴったりだとは思いません?」
控えめな色で、既婚者としてふさわしいようにも思われる。
婚姻後に相談を受け付けるのであれば、それを鑑みて服装や場を設定しなくてはいけないわ。
わたしが結婚していれば、陛下とウィルのお守りがたくさんあれば、わたしも相談に来てくださる方も、お互い悪様に言われるのを避けられるでしょう。
「……きみには何色だって似合うとも」
呻くような低い声とともに腰を引き寄せられた。
「ありがとう存じます」
ウィルの返事があまりにも照れているとわかりやすかったものだから、思わずあげそうになった笑い声を、煌めくシャンパンとともに飲み込んだ。