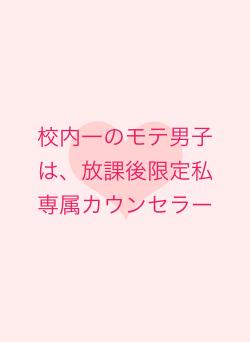旦那様が私の頬に手を当てる。
「家政婦として雇ってから、君の笑顔を始めて見たのは数日後の朝だった」
「君は私を起こしに来て、「おはよう御座います」と微笑んだ」
「あんなに一度でも見てみたかった君の笑顔が、もう一度みたくなった」
「それからも君と過ごすうちに、君が笑顔を見せてくれる度に、もっともっと笑って欲しかった」
「ねぇ、東木さん。さっきのは本心だよ。君が自分の人生を歩めるのなら、家政婦はいつ辞めてもらっても構わない。でも、もし可能なら・・・」
「私と付き合って欲しい」
私は旦那様が触れている私の頬に涙が伝うのを感じた。
「家政婦として雇ってから、君の笑顔を始めて見たのは数日後の朝だった」
「君は私を起こしに来て、「おはよう御座います」と微笑んだ」
「あんなに一度でも見てみたかった君の笑顔が、もう一度みたくなった」
「それからも君と過ごすうちに、君が笑顔を見せてくれる度に、もっともっと笑って欲しかった」
「ねぇ、東木さん。さっきのは本心だよ。君が自分の人生を歩めるのなら、家政婦はいつ辞めてもらっても構わない。でも、もし可能なら・・・」
「私と付き合って欲しい」
私は旦那様が触れている私の頬に涙が伝うのを感じた。