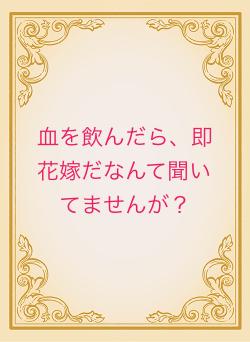「なっ……」
(いま私、翡翠にキスされた――――?)
顔を離した後、翡翠はぺろりと自分の唇を舐めた。赤く、艶やかな舌は今の蘭には刺激的すぎる。
「…………甘いな」
「っ!」
頬に熱が集まる蘭を見て、目を細める翡翠。愛しいものを見るような顔に、蘭はくらくらとめまいがした。
「――――ずっとお前に、こうしたかった……」
(! 『ずっと』……?)
翡翠は瞳の奥にちらりと欲望を覗かせ、もう一度ゆっくりと蘭へ顔を近づける。
「ま、って翡翠っ!」
(ま、まだ心の準備が――――!)
……咄嗟に手を伸ばし、ぎゅっと握ったソレ。
翡翠の動きが止まってくれるかもと思ってした行動だが、功を奏したのかピシリと固まり動かなくなる翡翠。
……しかし、いつまでたっても動かない翡翠。
蘭は心配になり手をのばして、ぺちりと軽く頬を叩いた。
「翡翠……? ごめん、尻尾を握ったのそんなに痛かった?」
「…………」
「ねぇ、ひす――――」
お酒のせいなのか、それとも……。
のそりと顔を上げた翡翠は、ほんのり顔が赤い。
そして先ほどより色濃く欲望を覗かせている瞳は、うっすらと膜を張り濡れていた。
「あまり、俺を煽ってくれるな……」
それは一瞬の出来事。
気付けば蘭は押し倒され、上から翡翠に見下ろされていた。
(…………!!)
「ひ、すい? ……待って、酔いすぎてるんだよっ」
抵抗する蘭。
翡翠は蘭の腕を押さえつけ――――ぺろりと、露わになっている首筋を舐めた。
「――――!?」
声にならない悲鳴が蘭の口内で暴れた。
舐められた部分が外気で冷たく感じ、それが尚のこと恥ずかしさを倍増させる。
ごくりと唾を飲み込んだ蘭の喉へおもむろに視線を向けた翡翠は、誘われるように喉に唇を寄せた。
「ひゃあっ!?」
喉、という急所にキスをされる感覚は何とも言えない。このまま食べれてしまうのでは、という錯覚に陥る。
蘭の声が耳に良いのか翡翠は高揚感のまま、熱に浮かされたように角度を変えながら何度も喉にキスをする。
「ひっ、翡翠、もう……やめっ」
「………うるさい」
「翡翠っ……」
「お前はそうやって、俺の名を囁いていれば良いんだ。昔のように、この先もずっと――――」
(…………昔?)
昔、という気になるワード。
その続きを待っているが、いつまでたっても紡がれる気配がない。
蘭は「まさか……」と思い視線を下に向けた。
すると瞼を閉じて、長いまつ毛を惜しげもなく見せつけながら寝ている翡翠の姿が。
(う、そでしょ。――――この状況で寝れるのっ!?)
そのまさかである。
穏やかな寝息をもらす翡翠に、蘭は毒気が抜かれていく。
しかし、「それ」はやってきた。
かすかな物音と、先程の蘭と翡翠の言い合いで起きたのか居間の襖を少し開け、顔を覗かせた。
「うーん? 誰か起きてるの――――」
「…………!?」
顔を覗かせたのは、口に手を当て噂話が好きそうな近所のおばちゃんぽい仕草をした――廻だ。
「あれまー……、俺、邪魔しちゃった?」
「ごごご誤解ですっ!! ――ちょ、先輩帰らないでっ、翡翠をどかすの手伝ってくださいよっ」
「えー、俺重いの持ちたくなーい。涼太くんでも起こす?」
廻は、面倒くさい事になるカードを的確に出してくる。
「いや、起こさなくて良いですから!」
「ちぇー。つまんないの」
カチンときた蘭を責める人はいないだろう。むしろキレ散らかさないだけ、偉いまである。
「よいしょっ――、うわ、重〜い。ほら、ひーちゃん自分の部屋に戻るよ」
寝ぼけている翡翠の手を肩に回し、少しずつ進みそのまま部屋まで連れて行く廻。
「先輩、私も反対側を支えま――」
「蘭ちゃんは、もう部屋に戻りなよ。俺がひーちゃん布団に転がしとくからさ」
「……ありごとうございます、先輩」
「ん、おやすみー」
二人の姿が見えなくなると、蘭はその場にぺたりと座り込む。
唇を指でなぞれば、翡翠の唇の感触を思い出す。
(もし――――)
(もし翡翠があのまま意識を手放さなかったら、私はどうしてたんだろ?)
(私は……、受け入れようとしていた?)
◇◇◇◇◇
朝ご飯の時間。
皆でテーブルを囲い食べるご飯は美味しい……はずなのだが、昨夜のことがあり蘭は気が気ではない。
「――――どうした、蘭」
翡翠とまともに視線を合わせられない蘭は、チラチラと見てしまいそれを翡翠に不審がられるという負の連鎖。
「っ! 別にっ? あ、愛梨ちゃんそこのお醤油取ってもらっていい?」
「はい、どうぞ」
不自然さは否めないが、どうにかそれ以上の翡翠からの追求を逃れた蘭。
朝ごはんも終わり、お皿を片付け終わると涼太が「ちょっと出てくる」と言った。
「どこ行くの?」
「コンビニ」
それを聞いた廻が「じゃあ、蘭ちゃんと涼太くん買い出し行ってきてよー。お菓子とか〜」と付け加えた。
「あ、なら私も――――」
「はーい、片瀬ちゃんはこっちねー」
「?」
廻はどこから取り出したのかトランプを「はい、よろしくね」と由樹に渡して、シャッフルをするように指示する。
「蘭ちゃんと涼太くん以外は、今から俺とトランプ大会しよう」
「とらんぷ! 澪緒知ってる! あいり、一緒にやろー」
「ふふっ、お手柔らかにね澪緒ちゃん」
「俺はやらんぞ」
「ひーちゃん、ルールわかんない? なら、俺が教えてあげるけど……もしかして、一回聞いても理解できなさそうだから不安?」
「…………ぬかせ。廻よ、お前が泣いて許しを請うまでやってやるさ」
「いきなり重い話になったんだけど、どうしよう神白くん」
「先輩の自業自得でしょ」
顔色を悪くしながらも廻はパチンとさりげなく涼太に目配せし、それを渋々受け取った涼太は「じゃ……行くか」と蘭に言い、玄関へ向かう。
「あ、待ってよ涼太!」
「蘭――」
涼太を追いかける蘭の背に、何かを言おうとした翡翠の肩をガチリと掴んだ廻。
「はーい、ひーちゃんはこっちに座って。神白くん、ババ抜きと神経衰弱どっちがいい?」
「えっ、……ババ抜きかな。神経衰弱はかろうじて一人で出来るけどババ抜きは三人以上居ないと出来ないから、僕あんまりやった事ないです」
唐突に由樹のぼっちエピソードを聞いてしまい、廻は目元を抑える。
「うん……俺、泣きそう。よし、二人が帰ってくるまで沢山やろ! 帰ってきたら、蘭ちゃん達も入れてやろうね神白くん!」
「その頃まで、お前の心が折れずにいればの話だが」
「…………」
翡翠の一言に、廻はぎぎぎっと首を回し由樹を見る。
「か、神白く――」
「僕は知りませんよ。あ、片瀬さん、机の上のそれ移動させてくれる?」
「うん、まかせて!」
「ゆきっ、澪緒もお手伝いするー」
「じゃあ、カードはシャッフルしたから人数分に分けれるかな?」
「らじゃーなの!」
和気あいあいとする後輩と澪緒を見ながら、廻は「うーん、どうにも後輩が皆手厳しいなぁ」と呟く。
ふと翡翠を見れば、ニヤリと殺気だった笑みを向けられた。
「……楽しみだな、廻よ」
「はは――――俺、今日命日なの?」
◇◇◇◇◇
コンビニにやってきた二人は、まさか今日が廻の命日になるかもしれない……事など露知らず。
皆の分のお菓子を見繕っていた。
「ありがとうございましたー」
コンビニを出たあと、涼太はカシュッと缶のエナジードリンクを開けて飲んでいる。
「涼太、それ好きなの?」
「ん? あー……、別に好きって言うか気合い入れる時に飲むやつだから」
「?」
どういうことか気になったが、深く聞くことはせずに飲み終わるまで待ってから、歩き出した。
あと、何度か角を曲がれば家。
――――その時、涼太は立ち止まった。
「……涼太?」
振り返った涼太は、固く口を閉じどこか緊張しているようにも見えた。
――――近くを流れる川の音が、やけにうるさく聞こえるのは気のせいだろうか。
「りょ――」
「なぁ、蘭」
いつになく真剣な表情。
それはこの間、涼太が泊まりにきた夜の出来事を思い出させる顔だ。
「好きだ」
(…………!?)
「――ガキの頃からずっと」
涼太の言葉に、一瞬、息が止まる。
「今この瞬間、俺以外を見ることは許さない」と言わんばかりに、真っ直ぐ蘭を見つめている瞳。
「……俺と付き合って欲しい」
飾らない言葉。
蘭は、すごく涼太らしいと思えた。
(涼太が私を……好き?)
なんと言えばいいのだろうか。
ぐるぐると考えても、最適解の言葉は出てこない。
「えっと……その」
傷つけない断り方は、どうすればいい?
そこまで考えて蘭は、はっとする。
(私はなんで……最初から、涼太の告白を断る前提で考えているの?)
涼太の事を嫌いだと思ったことはない。大切ないとこであり、家族だ。
けれど「好き」と言う言葉を聞いて、蘭が浮かんだ顔は――――。
「――――ごめん、なさい」
「…………」
蘭の頭に浮かんだのは、涼太ではなかった。
(いつも一言余計で、でも優しい時もあって。けど時折、愛おしそうに私を見つめる瞳が、たまらなく心を乱してくる)
当てはまる人物は一人しかいない。
(私は……、翡翠が好きなんだ)
皮肉な事に涼太から告白された事によって、翡翠への恋心を蘭は自覚した。
心はめちゃくちゃで、どこをどう整理すれば落ち着くのかわからない。
けれど、今は言わなければいけない事がある、それだけは理解できた。
蘭は息を吐き、呼吸を整える。
「私を……好きって言ってくれて、すごく嬉しい。まさか、誰かから告白されるなんて夢にも思ってなかったから」
「……あぁ」
「けど、私にとって涼太は大切な家族なの。付き合う……とか、じゃなくてっ」
言葉が詰まり、声も震えてうまく喋れない蘭。
(あぁ……、なんで涙が出てくるんだろう?)
――人の好意を断るというのは、こんなにも重く責任のあることなのだと痛感する。
蘭の瞳から一筋の涙が溢れた。
(――泣きたいほど痛いのは、きっと、涼太の方なのに)
泣いている蘭を見て、涼太は自分の中の様々な感情抑えるため、一瞬ぐっと拳を握る。次に、ふうっと息を吐き全身の力を逃がす。
そして、泣いている蘭に「ごめん」と謝り――――涼太はぎゅうと蘭を抱きしめた。
「っ!!」
「泣くな、ばーか」
涼太の体温が服越しに伝わってきて、重く、冷たくなった蘭の心をじわりとほぐす。
「――重く受け止めすぎ。……お前が俺をフったって、いとこってのはかわらないんだ。俺と蘭の縁が切れたわけじゃない」
その言葉に、ぼろぼろと涙があふれだし、ぎゅっと涼太を抱きしめ返す蘭。
「フラれるのはわかってたし、でも俺のわがままでお前に告白した。……俺がお前を泣かせるのは、これで最後だから」
『だから――、今だけはこうさせてくれ』
涼太の肩口に顔を埋めた蘭の涙が、服に滲んでいく。
どれほど……、そうしていただろうか。
顔を覗き、蘭が落ち着いた事を確認した涼太。
「大丈夫か?」
「……うん。ありがとう」
「ん、よし。いつも通りの蘭だな」
「いつも通りって?」
「ぽやん、としてるってこと」
眉を寄せ「なっ」と言う蘭に、涼太は安堵する。
「蘭」
「……なに? またなにか悪口?」
身構えた蘭に「別に、さっきのは悪い意味じゃない。俺は可愛いと思ってるけど」と、さらりと言ってのけた涼太。
(はっ、恥ずかしいことを何でそんなにさらっと言えるのよ……!)
「なぁ……もし翡翠の野郎に泣かされたら、俺に言えよ」
「! な、んでっ翡翠が出てくるの?」
「それは、……蘭は翡翠が好きなんだろ?」
「!!」
目を見開く蘭に「お前な……、気づいてないとでも思ったか?」と呆れた顔をした涼太。
(私が自覚したのはついさっきなのに、――なんでもうバレてるの!?)
ぽふんと顔が赤くなった蘭。
それを見て「はぁーーーー」と長いため息をついた涼太は、ぎゅううと蘭を強く抱きしめなおした。
「きゃっ!」
甘い匂いも柔らかさも。
蘭の全てが、今だけはこの腕の中にある。
涼太は心の中で思う。
『できることなら。こいつを幸せにするのは、俺でありたかった』と。
だけどそれは、蘭には秘密。
涼太にとって一番優先されるのは、蘭の幸せなのだから。
そう、たとえ蘭を幸せにする人が自分じゃなくとも――。
「くっ、苦しいってば涼太」
「――うるせー、丁度いい抱き枕見つけたんだよ」
「…………それって私のこと!? 私は抱き枕じゃないしっ!」
「んだよ、この抱き枕うるさいな。やっぱり、返品するか?」
「うるさいってなに!? もうっ、ほら帰るよ! 皆が待ってる」
「へーへー」
最後には、いつも通りの雰囲気。
けれど、お互いゆったりと、今だけは二人の時間を惜しむように足を動かした。
◇◇◇◇◇
家に帰りつき、玄関を開けるとなぜか仁王立ちの廻がいた。
ひらり、と手を振り「おかえりー」と出迎えてくれる。
「あ、蘭ちゃん。俺、涼太くんに話あるから先に戻ってもらってもいい?」
「じゃあ、私お菓子持っていっときますね。涼太、袋かして」
蘭は涼太から買い物袋を貰い、先に家に上がる。
蘭の姿が見えなくなってから、廻は口を開いた。
「で、どうだった? 涼太くん」
廻の顔は、どこかいつもより優しげで。それに気づいた涼太は、むすっとした表情で答える。
「……振られましたけど」
廻は両手を広げ「……よし、飛び込んでおいで、先輩の胸に」と言うが、そんな廻を見る涼太の目は据わっていた。
「そういう茶番はいらないです。先輩の言う通り当たって砕けたんで、なんか奢ってくださいよ」
「えぇ、……コンビニのおにぎり一個とかでいい?」
「バカにしてんすか?」
「うそうそ! コーヒーで良い?」
「焼肉奢ってくださいよ」
「うーん、急に話デカくない?」
涼太は「役に立たない先輩は持たない主義なんで。じゃ」と廻の横を通り過ぎようとする。
「まぁ、待ってよ。後輩の失恋記念日だ、俺が奢ってあげよう」
「……マジすか」
「疑ってる?」
「当然」
「俺ってそんなに信用ないのね」
仲がいいのか悪いのかわからない二人だが、後輩を慰め、そしてそれを受け入れる程度には仲が良いのかもしれない。
◇◇◇◇◇
――こうして楽しかった勉強会、という名のお泊まり会の二日目は、皆でお昼を食べた後解散となった。
「蘭ちゃん、澪緒ちゃん、翡翠さんも! またあそびにくるねっ! バイバーイ!」
「うん! またね!」
「ばいばいなのー、あいりー!
ぶんぶん、と大きく手を振る愛梨の後ろで廻や涼太、由樹もひらりと手を振っている。
蘭は一瞬涼太と目が合う。すると涼太は口パクで「またな」と言った。
(……またね、涼太)
同じように蘭も口パクで返せば、ふっと微笑んだ涼太は前を向く。
愛梨達の背中が見えなくなるまで、蘭と澪緒は手を振り続けた。
「……澪緒、やっぱりもっとお見送りしてくる!」
寂しさが勝ったのか、澪緒は持ち前の素早さで、シュパパパッと愛梨達を追いかけていく。
その背中に「ちょ、澪緒ちゃん!? ……もうっ、気をつけてねー!」と言う蘭。
「よほど、楽しかったようだな澪緒は」
「ふふっ、そうだね」
澪緒がいなくなり、翡翠と二人きりになった蘭は何度か視線を彷徨わせてから口を開いた。
「……やっぱり皆が帰っちゃうと、寂しいね」
「静かでいいではないか」
「もう。それがちょっと寂しいって言っての!」
「また遊びにくると言っていただろう。愛梨や由樹くらいならば、いつでも構わん。あの小僧二人は別だが」
「小僧二人って、涼太と廻先輩のこと?」
やや苦笑いをしながら確認すれば「奴ら以外に誰がいる」と言われてしまった。
「寂しいけど……、まぁ、うちには毎日うるさい狐のあやかしがいるしね?」
「ほう? そう言うお前も、俺にとってはまだまだ騒がしい子供だよ」
一言余計な翡翠は、今日も健在のようだ。
だが翡翠への気持ちを自覚した今では、かろうじて受け流せなくもない。……多分。
ちらり、と横顔を見ればやはりどこから見ても綺麗な顔で。
今までとは違って「好き」という思いが心をきゅっと締め上げる。
「ねぇ、翡翠。……今度さ、一緒に――」
「蘭」
『一緒にまた出かけない?』
その言葉を遮られ、むっとして翡翠の顔を見れば、真剣な表情で蘭を見つめていた。
……なぜ、こんなにも胸騒ぎがするのだろう?
嫌な予感に、自然と硬い表情になっていると自分でもわかる蘭。
「なによ、……どうしたの?」
「――俺は少しの間、家を空ける」
……当たってほしくない胸騒ぎほど、的中するものはない。