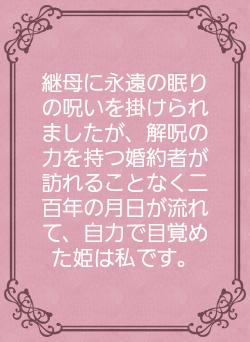バルのその瞳に捕えられたアーサー達は、ひっと短い悲鳴を上げて固まることしかできない。
「さて。大精霊を汚すだったか?一体いつリサリルが汚したと?」
「な、何が言いたいっ」
「使い手としての役目を果たしていなかったのは、その女の方だろう?貴様も王族で婚約者がいる身でありながら、その女と現を抜かしていたくせに。よく言えたものだな。リサリルは毎日欠かさず祈祷をし、精霊の知識を蓄えようとひたむきに努力していた。そんな彼女が汚す?何故?」
「わ、私は!精霊の使い手としてしっかり責務をこなし、大精霊様の声を聞いたのです!リサリル様が大精霊様に危害を加えるとっ!その上使い手の私が邪魔だからと、苛めてくるばかりで。確かに嫉妬されるようなことをした私も悪い――」
「リサリルが貴様に嫉んだり妬いたりする要素は何処にもないとは思うが?それで、どんな嫌がらせを受けたと?具体的には言えんのだろう?」
「っ!言えます!私はこれまでリサリル様に酷く責められてきました!初めて出会った時に庶民は使い手には相応しくないと罵られました!」
バルが私に視線を動かし、楽しそうに微笑む。
一緒に戦ってくれる人が傍にいる。私は言われっぱなしで溜まった呆れを吐き出すように口を開いた。