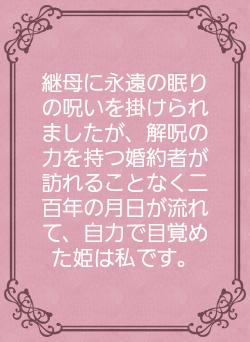でも戦うって決めたんだから、もうどん底に落とされるのが分かっているのなら怖いものは何もない。
意を決して今度こそ口を開いたけど、そっと隣にやって来た人物を見て、言葉にならなかった息が零れた。
「茶番は終わったか?」
凛とした低い声が、あれだけざわめいていた会場を一瞬にして静まり返らせた。
漆黒の髪に黒真珠のような吸い込まれそうな瞳。
紺色の服に金糸で見事な刺繍が施された礼服を着こなした優美な立ち姿だというのに、この場を支配するような威圧感までも纏っていた。
私を庇うようにアーサーとの間に入った彼の姿に思わず心臓が高鳴る。
「貴様、一体何者だ!」
「……まったく、この国も落ちたものだな」
「王家に対する愚弄、ただ済むとでも思ってはいないだろうな!」
「愚弄?どの口が言っている」
地を這うような低い声に、思わずアーサーが口を閉ざした。