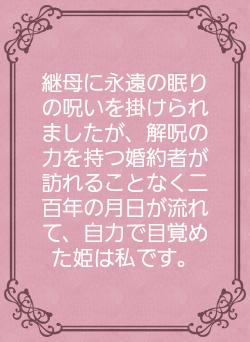僅かに湿っているバルの鼻先にビクンと体を震わせると、どこか不敵な目を一瞬見せた彼に頬を舐められた。
「バッ……?!」
あまりバルからこうやってくることがないせいなのか、驚きのあまり声が出ない。
「今日も疲れたろう?一休みしよう」
そっと私の目の前から離れたバルは尻尾を振って、ベッドの方へと歩いていく。
近い距離感から解放された私は、一つ深い呼吸をしてからバルの言う通り疲れていたのかもと、ベッドへと向かった。
今日のお茶会に緊張していたのね、きっと。
そう思うと、先程までのドキドキが少し緩和されたようなそんな気がしたけど、体に疼く熱は消えないまま。
ベッドの上に寝転ぶと、傍に寄り添うようにバルも伏せた。私の事をよく見て、私のことをしっかりと分かってくれるバルに自然と感謝の気持ちが零れる。
「いつもありがとう、バル」
「礼を言うのは俺の方だ。こんな俺を怖がらず助けてくれた上に、こうして優しく接してくれるリサリルにはいつも感謝している」
「バルはちっとも怖くなんかないよ?」
「そう言ってくれるのはリサリルだけだ」
どこか寂しそうに呟いたような気がして、私はバルをそっと引き寄せた。