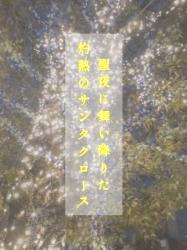すると、水筒を持つ手に沢村くんの手が重なった。
凍った心をじんわりと溶かしていくような、優しい温もり。
再び涙が込み上げてきて、ポロッと一筋、頬を伝う。
──一瞬すぎて、何が起こったのかわからなかった。
気づいたら冷たいアスファルトの上に横たわっていて、尋常じゃないほどの痛みが全身に走っていた。
消えかかった意識の中で、唯一覚えているのは、傘を持ったサラリーマンらしき人が、慌てた様子で電話をかけていたこと。
あとは……足元から、雨のにおいに混じって血のにおいがしたこと。
意識が回復して目を覚ますと、だだっ広い病室のベッドの上で点滴を受けていた。
脇には、目を真っ赤にさせた父と、涙を拭う母と、涙と鼻水まみれの柊太が立っていて。
『良かった、本当に良かった……っ』
両親と弟は包帯が巻かれた私の手をギュッと握りしめていた。
どうやら私は、緊急手術により、なんとか一命を取り留めたらしい。
お医者さんいわく、『ヘルメットを被っていなかったら助かってなかった』と。
私を信号無視で轢いた犯人も、1度逃げ出したみたいなのだが、運良く、通勤中の警察官が近くにいたため、すぐに確保されたのだそう。
凍った心をじんわりと溶かしていくような、優しい温もり。
再び涙が込み上げてきて、ポロッと一筋、頬を伝う。
──一瞬すぎて、何が起こったのかわからなかった。
気づいたら冷たいアスファルトの上に横たわっていて、尋常じゃないほどの痛みが全身に走っていた。
消えかかった意識の中で、唯一覚えているのは、傘を持ったサラリーマンらしき人が、慌てた様子で電話をかけていたこと。
あとは……足元から、雨のにおいに混じって血のにおいがしたこと。
意識が回復して目を覚ますと、だだっ広い病室のベッドの上で点滴を受けていた。
脇には、目を真っ赤にさせた父と、涙を拭う母と、涙と鼻水まみれの柊太が立っていて。
『良かった、本当に良かった……っ』
両親と弟は包帯が巻かれた私の手をギュッと握りしめていた。
どうやら私は、緊急手術により、なんとか一命を取り留めたらしい。
お医者さんいわく、『ヘルメットを被っていなかったら助かってなかった』と。
私を信号無視で轢いた犯人も、1度逃げ出したみたいなのだが、運良く、通勤中の警察官が近くにいたため、すぐに確保されたのだそう。