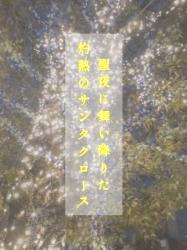このままずっと自責の念に駆られていたら、みんなが悲しみきれない。
そう思い、葬儀の日を最後に、彼らの前で涙を流すのはやめたのだが……。
「当時に比べたら、だいぶ癒えてはいるんだけど……ふとした拍子に思い出すんだ」
ハンドルを切って住宅街に入る。
町中で陽菜に似た人を見かける度に、あの時ああしていれば、こうしていたらと、堂々巡りに陥ってしまう。
特にテレビでいじめのニュースを見かけた日なんかは、拒絶された時の記憶が鮮明によみがえってきて。
一睡もできずに朝を迎えることもあるくらい、酷く胸が痛むんだ。
「ごめんね。最後に暗い話しちゃって」
「ううん。話してくれてありがとう」
千早さんの家に到着し、玄関の前に車を停めた。
天井のスイッチに腕を伸ばして電気を点ける。
「噂は聞いていたけれど……まさか、沢村くんの学校だったなんて」
「千早さんの学校にも広まってたんだ」
「そりゃあ地元だもん。春休みに差しかかる頃だったからあまり話題には上がらなかったんだけど、お母さんが新任の頃、そこで働いてたらしくてね。ちょうどその時期も、2年生の担任やってたから、毎日話してて……」
温かみのあるオレンジ色の光が車内を照らしているが、彼女の顔には影が落ちたまま。
うつむいて言葉を紡ぐ横顔は、どこか悟ったようにも見えて。
「私も、中学はなかったけど、嫌がらせされてたからさ。毎年歳取ると思い出しちゃうんだよね」
ドクンと心臓が揺れ動いたのを感じた。
おもむろに顔を上げた彼女の瞳も揺れている。
「もしかして、私と付き合えないのって……」
「…………うん」
打ち明ける前に気づかれてしまった。
快く気持ちに応えられない1番の理由。
立ちはだかる大きな壁。
それは──陽菜の命日が、君が産声を上げた日だったから。
そう思い、葬儀の日を最後に、彼らの前で涙を流すのはやめたのだが……。
「当時に比べたら、だいぶ癒えてはいるんだけど……ふとした拍子に思い出すんだ」
ハンドルを切って住宅街に入る。
町中で陽菜に似た人を見かける度に、あの時ああしていれば、こうしていたらと、堂々巡りに陥ってしまう。
特にテレビでいじめのニュースを見かけた日なんかは、拒絶された時の記憶が鮮明によみがえってきて。
一睡もできずに朝を迎えることもあるくらい、酷く胸が痛むんだ。
「ごめんね。最後に暗い話しちゃって」
「ううん。話してくれてありがとう」
千早さんの家に到着し、玄関の前に車を停めた。
天井のスイッチに腕を伸ばして電気を点ける。
「噂は聞いていたけれど……まさか、沢村くんの学校だったなんて」
「千早さんの学校にも広まってたんだ」
「そりゃあ地元だもん。春休みに差しかかる頃だったからあまり話題には上がらなかったんだけど、お母さんが新任の頃、そこで働いてたらしくてね。ちょうどその時期も、2年生の担任やってたから、毎日話してて……」
温かみのあるオレンジ色の光が車内を照らしているが、彼女の顔には影が落ちたまま。
うつむいて言葉を紡ぐ横顔は、どこか悟ったようにも見えて。
「私も、中学はなかったけど、嫌がらせされてたからさ。毎年歳取ると思い出しちゃうんだよね」
ドクンと心臓が揺れ動いたのを感じた。
おもむろに顔を上げた彼女の瞳も揺れている。
「もしかして、私と付き合えないのって……」
「…………うん」
打ち明ける前に気づかれてしまった。
快く気持ちに応えられない1番の理由。
立ちはだかる大きな壁。
それは──陽菜の命日が、君が産声を上げた日だったから。