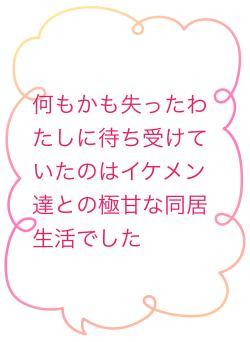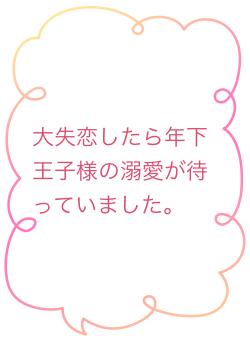「みあ」
「…っ、」
誰よりも愛しい者を見る眼でわたしを見て、なによりも慈しむような声でわたしの名を呼ぶ。
わたしは、途端に呼吸を忘れたように息が苦しくなる。
それと同時に走り出していた。兄のもとへと。
兄を囲んでいた女生徒たちが自然と道を開けて、わたしは兄の正面まできてそのジャケットの裾をきゅっと握った。
「帰ろ…漣」
「っ、みあ」
どうして『お兄ちゃん』と呼ばず『漣』と呼んでしまったのか。
つまらないヤキモチだろうか。
それともみっともない独占欲?
今はそのどちらでもよかったし、両方だったとしてもいい。
ただ一刻も早くふたりきりになりたかった。
自分以外の女の子が兄の事をあんなふうな眼で見ているのが許せなかった。
「ああ、帰ろう。俺たちの家に」
わたしと、漣だけの家に____。