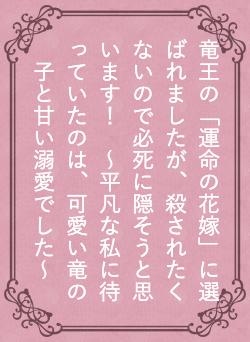そんな俺の険しい表情に違和感を感じたのだろう。真っすぐな気質のケリーは、俺に対しても物怖じせず、意見を言ってくる。
「この作戦は、いったん彼女を別の場所に留置して、取り調べを続けるということではないのですか?」
「…………」
ケリーの発言に、何も言葉が出てこない。なぜなら俺の頭には、彼女を取り調べるという考えがまったくなかったからだ。
(俺はただ彼女を連れて、逃げたい一心だったのかもしれない。これでは本当に騎士失格だ……)
黙り込む俺の態度を見たケリーは、目を丸くして驚いている。それでもまだ俺を信用してくれているのだろう。まるで俺に正気に戻れというように、強い口調で話を続けた。
「そもそも、団長がご自身の命をかけてまで、謎の侵入者を助けることの意味がわからないのです。もちろん王宮に侵入した彼女を、すぐに処刑するのは反対です。その裏にどんな思惑があるのかも、わからないのですから。しかし今の団長は感情で動いているように見えます。違いますか?」
もともと俺とケリーは同じ年で、騎士としてずっと一緒に過ごしてきたのだ。誰よりも俺の行動や考えを理解している。彼女に対しての気持ちを隠していたら、今まで築いてきた信頼すらも裏切ってしまうだろう。