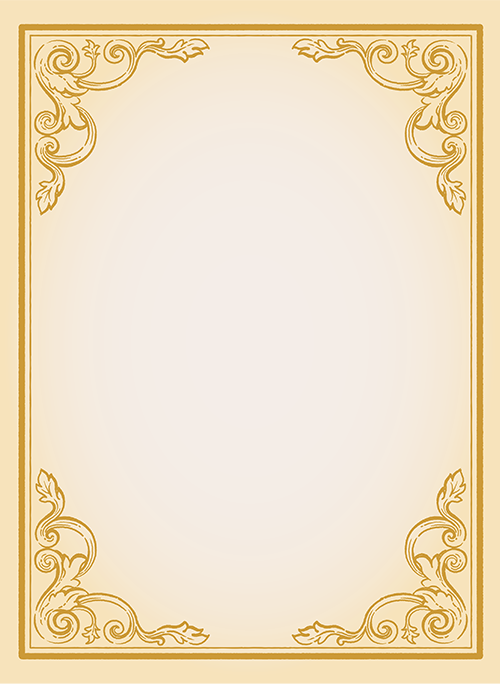「……どうなってるんだ!」
学期末パーティーから三日が経過し、とあることに気づいた僕は我慢ならず声を上げた。
――ユリアーナが会いに来ない。
おかしい。ユリアーナは婚約者という立場を利用して、毎日のように僕の屋敷へ遊びにきていた。もはやストーカーのレベルだ。
自分で言うのもなんだが、僕はユリアーナに相当惚れられていた……いや、いるはずだ。それなのに、彼女が三日も僕の顔を見ないで耐えられるはずがない。
「エーデル家からなにか便りは届いていないか?」
もしかしたら体調を崩したんじゃないかと思い、通りすがりの侍女に聞いてみる。
「いいえ。なにも届いていませんが」
「……そうか」
「そういえば、今日もユリアーナ様を見ていませんね。屋敷が静かで過ごしやすいです」
「……そうだな」
侍女の言う通りだ。ユリアーナが来るといつもうるさくて、ゆっくり過ごせやしない。だから、来なくてみんなが助かっている。
……だけど、もし本当に具合が悪かったら? 婚約者として、一応見舞いくらいには行ったほうがいいだろう。
結局、僕は馬車に乗ってエーデル家の屋敷へ向かった。自らユリアーナに会いにいくなんて何年ぶりだろうか。嬉しくて、ユリアーナの具合もすぐによくなるんじゃないか?
なんて自信満々に馬車を走らせたというのに。
「め、面会拒否?」
「ああ。ユリアーナは今、誰とも会いたくないみたいでね」
眉を八の字に下げたエーデル伯爵が、申し訳なさそうに僕に告げる。
「待ってください伯爵! ……それは、相手が僕でも、ですか?」
ユリアーナが僕の顔も見ず、突っぱねるわけがない。この時僕は、たしかにそう信じていた。
「相手がたとえクラウス様でも、会いたくないそうだ」
「……っ!?」
しかし、現実は僕の思う通りにはいかなかった。エーデル家の屋敷へ一歩も入ることを許されぬまま、僕は馬車に揺られ、感じたことのない虚無感に襲われて帰路につく羽目になった。
「……どうなってるんだ」
本日二度目のこの言葉は、馬車が走る音によってかき消された。
学期末パーティーから三日が経過し、とあることに気づいた僕は我慢ならず声を上げた。
――ユリアーナが会いに来ない。
おかしい。ユリアーナは婚約者という立場を利用して、毎日のように僕の屋敷へ遊びにきていた。もはやストーカーのレベルだ。
自分で言うのもなんだが、僕はユリアーナに相当惚れられていた……いや、いるはずだ。それなのに、彼女が三日も僕の顔を見ないで耐えられるはずがない。
「エーデル家からなにか便りは届いていないか?」
もしかしたら体調を崩したんじゃないかと思い、通りすがりの侍女に聞いてみる。
「いいえ。なにも届いていませんが」
「……そうか」
「そういえば、今日もユリアーナ様を見ていませんね。屋敷が静かで過ごしやすいです」
「……そうだな」
侍女の言う通りだ。ユリアーナが来るといつもうるさくて、ゆっくり過ごせやしない。だから、来なくてみんなが助かっている。
……だけど、もし本当に具合が悪かったら? 婚約者として、一応見舞いくらいには行ったほうがいいだろう。
結局、僕は馬車に乗ってエーデル家の屋敷へ向かった。自らユリアーナに会いにいくなんて何年ぶりだろうか。嬉しくて、ユリアーナの具合もすぐによくなるんじゃないか?
なんて自信満々に馬車を走らせたというのに。
「め、面会拒否?」
「ああ。ユリアーナは今、誰とも会いたくないみたいでね」
眉を八の字に下げたエーデル伯爵が、申し訳なさそうに僕に告げる。
「待ってください伯爵! ……それは、相手が僕でも、ですか?」
ユリアーナが僕の顔も見ず、突っぱねるわけがない。この時僕は、たしかにそう信じていた。
「相手がたとえクラウス様でも、会いたくないそうだ」
「……っ!?」
しかし、現実は僕の思う通りにはいかなかった。エーデル家の屋敷へ一歩も入ることを許されぬまま、僕は馬車に揺られ、感じたことのない虚無感に襲われて帰路につく羽目になった。
「……どうなってるんだ」
本日二度目のこの言葉は、馬車が走る音によってかき消された。