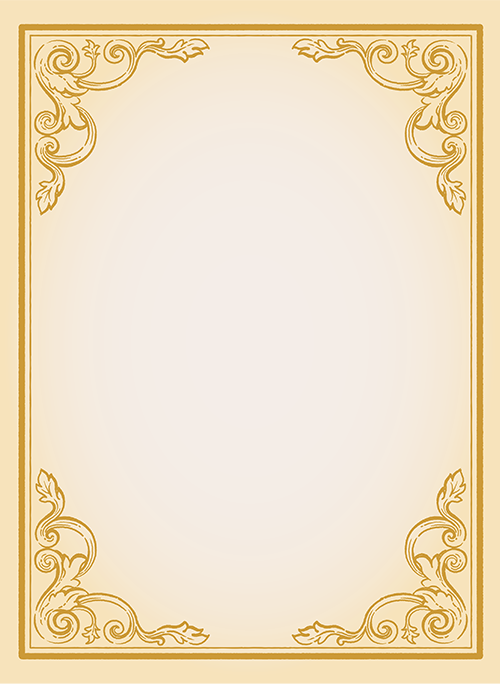「あ、あの……ユリアーナ様?」
声が聞こえて視線をうつすと、床に倒れている私の前に、心配そうな顔を浮かべたリーゼの姿があった。肩にかかるキラキラした金髪に、深緑のカチューシャ……。小説の表紙で見たまんまの姿だ
「大丈夫ですか?」
身体を屈ませて、リーゼは私に手を差し伸べる。
周りはざわざわとしていて、いったいなにが起こったんだという雰囲気だ。
「え、ええ。大丈夫。ありがとう」
とにかくいつまでも床に這いつくばっているのはどうかと思い、私はリーゼの好意に甘えてその華奢で小さな手のひらに自分の手を伸ばした――が。
反射的になのか、リーゼの手はびくりと震え、私が触れる前に引っ込められてしまった。
「あっ……ご、ごめんなさいっ」
泣きそうな顔をして謝るリーゼ。これまで嫌がらせをされてきた相手を前に、怯えてしまうのは仕方のないことだ。
「大丈夫か?」
そのとき、頭上から声が聞こえた。私とリーゼの視線は同時にその声のほうへと向けられる。声の主は予想通り、小説のヒーローであり、私の婚約者でもあるクラウス様だった。
クラウス様はリーゼの震える方を支えると、冷たい眼差しで私を見つめた。
……ああ。〝大丈夫か〟って、リーゼのことね。
派手に転んで恥をかいた婚約者よりも、そちらの心配をするなんて――ユリアーナったら、婚約者なのに全然大事に思われていないじゃない。でも当然か。ユリアーナのイメージって、わがままで傲慢で女王様気質で、常に人を見下して……そんな人、私が男でもきっと好きになるわけがないもの。
「……ふふっ」
おもわず自分で自分に呆れてしまう。ついでに、こんなに脈がないのに必死にクラウスを想っていたユリアーナが滑稽であり、ちょっとかわいそうにも思えた。
「なにがおかしい?」
「いえ。皆様の前で転んでしまったことが恥ずかしくて……笑って誤魔化しただけですわ」
怪訝な顔をするクラウス様に適当な言い訳をして、私は奇跡的に割れていなかったグラスを持って立ち上がる。空になったグラスを近くのテーブルの上に置くと、私はクラウス様と密着したままのリーゼに声をかけた。
「リーゼ嬢、ジュースがかかったり、怪我をしたりはしていない?」
「えっ? は、はい。大丈夫です」
「そう。……よかった」
ここで怪我をさせていたら、ただでさえよくない私の評判がさらに悪くなる。安堵してリーゼに微笑みかけると、クラウス様とリーゼの顔が固まった。
――とにかく、記憶の整理もしたいしこの場からさっさとお暇しちゃおうっと。このふたりと関わったら、私の悪役度が増すだけだわ。私は悪役として人生を終わらせるなんてごめんよ!
「リーゼ嬢、クラウス様、そしてこの場にいる皆様。お騒がせして申し訳ございません。せっかくのパーティーだったのに、楽しい雰囲気を私のせいで中断させてしまいました……。そんな私がこれ以上パーティーに参加することはできません。これは自分への戒めです。どうか皆様は、心ゆくまでパーティーをお楽しみくださいませ」
ドレスの裾をふわりと広げ、完璧な角度で頭を下げる。前世の私は物語のヒロインに憧れて、よく貴族の所作を真似したものだ。このとき、優雅な動きになるよう特に気を付けていた。果たしてできているかは謎だが、悪役令嬢のユリアーナが頭を下げただけでも物珍しい光景のはずだ。
「それではごきげんよう!」
最後に元気な声と満面の笑みを浮かべて、私は会場を去って行った――いや、逃げ出したと言ったほうが正しいか。
途中、外にいてなにが起きたのかわかっていなさそうな男子生徒とすれ違ったので、適当に愛想笑いしておいた。すると、その男子生徒は鳩が豆鉄砲を食ったような顔をした。……これまでの私が、いかに周囲に対して悪態をついていたのかがわかった。
声が聞こえて視線をうつすと、床に倒れている私の前に、心配そうな顔を浮かべたリーゼの姿があった。肩にかかるキラキラした金髪に、深緑のカチューシャ……。小説の表紙で見たまんまの姿だ
「大丈夫ですか?」
身体を屈ませて、リーゼは私に手を差し伸べる。
周りはざわざわとしていて、いったいなにが起こったんだという雰囲気だ。
「え、ええ。大丈夫。ありがとう」
とにかくいつまでも床に這いつくばっているのはどうかと思い、私はリーゼの好意に甘えてその華奢で小さな手のひらに自分の手を伸ばした――が。
反射的になのか、リーゼの手はびくりと震え、私が触れる前に引っ込められてしまった。
「あっ……ご、ごめんなさいっ」
泣きそうな顔をして謝るリーゼ。これまで嫌がらせをされてきた相手を前に、怯えてしまうのは仕方のないことだ。
「大丈夫か?」
そのとき、頭上から声が聞こえた。私とリーゼの視線は同時にその声のほうへと向けられる。声の主は予想通り、小説のヒーローであり、私の婚約者でもあるクラウス様だった。
クラウス様はリーゼの震える方を支えると、冷たい眼差しで私を見つめた。
……ああ。〝大丈夫か〟って、リーゼのことね。
派手に転んで恥をかいた婚約者よりも、そちらの心配をするなんて――ユリアーナったら、婚約者なのに全然大事に思われていないじゃない。でも当然か。ユリアーナのイメージって、わがままで傲慢で女王様気質で、常に人を見下して……そんな人、私が男でもきっと好きになるわけがないもの。
「……ふふっ」
おもわず自分で自分に呆れてしまう。ついでに、こんなに脈がないのに必死にクラウスを想っていたユリアーナが滑稽であり、ちょっとかわいそうにも思えた。
「なにがおかしい?」
「いえ。皆様の前で転んでしまったことが恥ずかしくて……笑って誤魔化しただけですわ」
怪訝な顔をするクラウス様に適当な言い訳をして、私は奇跡的に割れていなかったグラスを持って立ち上がる。空になったグラスを近くのテーブルの上に置くと、私はクラウス様と密着したままのリーゼに声をかけた。
「リーゼ嬢、ジュースがかかったり、怪我をしたりはしていない?」
「えっ? は、はい。大丈夫です」
「そう。……よかった」
ここで怪我をさせていたら、ただでさえよくない私の評判がさらに悪くなる。安堵してリーゼに微笑みかけると、クラウス様とリーゼの顔が固まった。
――とにかく、記憶の整理もしたいしこの場からさっさとお暇しちゃおうっと。このふたりと関わったら、私の悪役度が増すだけだわ。私は悪役として人生を終わらせるなんてごめんよ!
「リーゼ嬢、クラウス様、そしてこの場にいる皆様。お騒がせして申し訳ございません。せっかくのパーティーだったのに、楽しい雰囲気を私のせいで中断させてしまいました……。そんな私がこれ以上パーティーに参加することはできません。これは自分への戒めです。どうか皆様は、心ゆくまでパーティーをお楽しみくださいませ」
ドレスの裾をふわりと広げ、完璧な角度で頭を下げる。前世の私は物語のヒロインに憧れて、よく貴族の所作を真似したものだ。このとき、優雅な動きになるよう特に気を付けていた。果たしてできているかは謎だが、悪役令嬢のユリアーナが頭を下げただけでも物珍しい光景のはずだ。
「それではごきげんよう!」
最後に元気な声と満面の笑みを浮かべて、私は会場を去って行った――いや、逃げ出したと言ったほうが正しいか。
途中、外にいてなにが起きたのかわかっていなさそうな男子生徒とすれ違ったので、適当に愛想笑いしておいた。すると、その男子生徒は鳩が豆鉄砲を食ったような顔をした。……これまでの私が、いかに周囲に対して悪態をついていたのかがわかった。