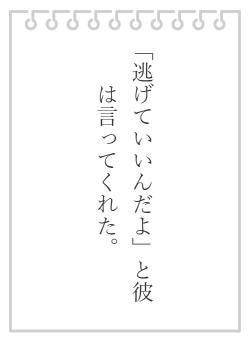黒須は昨夜、私が駅に戻った事を知ってるんだ。
あの時、まだホームにいたんだ。
「僕に会いにわざわざ地下鉄を乗り換えて戻って来たんだろう?」
その通りだと認めるのが嫌だった。
「どうして戻って来た?」
「どうしてって……」
声が弱くなる。
黒須の強い視線に射抜かれ、DVDを持つ指先が震えた。
「春音、どうして?」
優しい声で名前を呼ばれ、胸が苦しい。
これ以上、追い詰めないで欲しい。
目の奥が熱くなった。
彼を目の前にするといつも感情的になる。
「春音?」
黒須が心配そうに見てた。とても優しい表情だった。
自分が特別な存在なのかもしれないと錯覚してしまうぐらい。
「答えたくない?」
助け船を出すように黒須が言った。その言葉に黙って頷いた。
また黒須に負けた。
「わかった。帰るよ。春音に嫌な思いをさせたくないから。ここにも来ないから」
優しい言葉に涙ぐんだ。
「だから春音、泣かないで」
黒須の手が伸びて長い指先でそっと私の涙を拭った。
あの時、まだホームにいたんだ。
「僕に会いにわざわざ地下鉄を乗り換えて戻って来たんだろう?」
その通りだと認めるのが嫌だった。
「どうして戻って来た?」
「どうしてって……」
声が弱くなる。
黒須の強い視線に射抜かれ、DVDを持つ指先が震えた。
「春音、どうして?」
優しい声で名前を呼ばれ、胸が苦しい。
これ以上、追い詰めないで欲しい。
目の奥が熱くなった。
彼を目の前にするといつも感情的になる。
「春音?」
黒須が心配そうに見てた。とても優しい表情だった。
自分が特別な存在なのかもしれないと錯覚してしまうぐらい。
「答えたくない?」
助け船を出すように黒須が言った。その言葉に黙って頷いた。
また黒須に負けた。
「わかった。帰るよ。春音に嫌な思いをさせたくないから。ここにも来ないから」
優しい言葉に涙ぐんだ。
「だから春音、泣かないで」
黒須の手が伸びて長い指先でそっと私の涙を拭った。