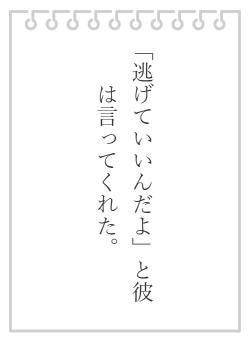「危なっかしいな。春音は」
すぐ近くで声がした。白いワイシャツが目の前にあった。気づくと座っている黒須の太腿の上に座っていた。しかも向き合う位置で。
えっ、なんでこの態勢?
早く、何とかしなくちゃ。こんな至近距離で黒須と見つめ合うような恰好になるなんて心臓がもたない。
どんどん体中が熱くなってくるし、鼓動がさっきから壊れそうな程鳴ってる。
「ごめん。重いでしょ。どくから」
「このままでいい」
黒須にいきなり抱き寄せられた。
わずかにあった空間が埋まって胸と胸がくっついた。
「ちょっと、何するの」
「春音を抱っこしてるんだよ」
クスクスと黒須が可笑しそうに笑った。
抱っこって、なんか小さな子供を抱いているみたいな言い方。
バーで飲んだシャーリーテンプルとゴッドファーザーを思い出した。
黒須も私の事、子どもだと思ってるんだ。なんかムカつく。
「離してよ」
「このままでいいよ」
「私は嫌だ。子どもじゃないんだから」
「子どもだとは思ってないよ。抱き心地のいい猫だと思ってる」
「ね、猫……」
「可愛い猫ちゃんだな。よしよし」
ふざけて黒須が私の後頭部を撫で始めた。
大きな手に何度も撫でられて、ますますドキドキする。平気な顔をしてそんな事をする黒須が憎らしい。
どんなに私がドキドキしているか知っているの?
なんでいじめるの?
「もう、やめてって」
大きな手を強く振り払うと、簡単に私の後頭部から落ちた。
それからドキリとする程、真剣な目で見上げる黒須がいた。
その目は昼間見た鈴原先生の恋人の眼差しに似ている。愛しい人を求めるような熱い目。そんな目を黒須もしている。
どうしてそんな目で見るの?
そう聞きたいのに胸が震えて何も言えない。
すぐ近くで声がした。白いワイシャツが目の前にあった。気づくと座っている黒須の太腿の上に座っていた。しかも向き合う位置で。
えっ、なんでこの態勢?
早く、何とかしなくちゃ。こんな至近距離で黒須と見つめ合うような恰好になるなんて心臓がもたない。
どんどん体中が熱くなってくるし、鼓動がさっきから壊れそうな程鳴ってる。
「ごめん。重いでしょ。どくから」
「このままでいい」
黒須にいきなり抱き寄せられた。
わずかにあった空間が埋まって胸と胸がくっついた。
「ちょっと、何するの」
「春音を抱っこしてるんだよ」
クスクスと黒須が可笑しそうに笑った。
抱っこって、なんか小さな子供を抱いているみたいな言い方。
バーで飲んだシャーリーテンプルとゴッドファーザーを思い出した。
黒須も私の事、子どもだと思ってるんだ。なんかムカつく。
「離してよ」
「このままでいいよ」
「私は嫌だ。子どもじゃないんだから」
「子どもだとは思ってないよ。抱き心地のいい猫だと思ってる」
「ね、猫……」
「可愛い猫ちゃんだな。よしよし」
ふざけて黒須が私の後頭部を撫で始めた。
大きな手に何度も撫でられて、ますますドキドキする。平気な顔をしてそんな事をする黒須が憎らしい。
どんなに私がドキドキしているか知っているの?
なんでいじめるの?
「もう、やめてって」
大きな手を強く振り払うと、簡単に私の後頭部から落ちた。
それからドキリとする程、真剣な目で見上げる黒須がいた。
その目は昼間見た鈴原先生の恋人の眼差しに似ている。愛しい人を求めるような熱い目。そんな目を黒須もしている。
どうしてそんな目で見るの?
そう聞きたいのに胸が震えて何も言えない。