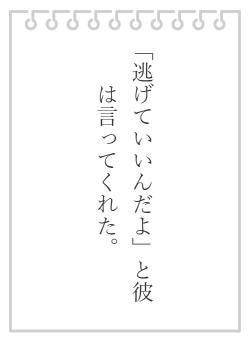この間と同じように、テーブルに肘をついた姿勢で座敷に座る黒須がいた。黒ベスト黒シャツ姿でタブレットに視線を落としていて、驚いた様子はない。
「私だってわかって声をかけたの?」
不思議だった。障子戸を開ける前からわかってたなんて。
「階段をのぼる足音がここの女将さんと違うし、障子の前で迷ったように立ってる気配もあったから、春音だとわかったんだよ」
タブレットから視線をあげ、黒須が微笑んだ。
いつもの黒須だ。余裕があってどこか私をバカにしたような感じで。
「突っ立ってないで座ったら?」
「うん」
テーブルを挟んだ斜め前に腰を下ろすと、興味深そうに黒須が視線を向けてくる。なんか見られていて恥ずかしい。
「私の顔、何かついてる?」
黒須が返事をするようにポットから冷えたほうじ茶をコップに注いで、スッと差し出した。
「喉がかわいたでしょ。走って来たから」
「なんでわかったの?」
黒い瞳が真っすぐこっちを向くと同時に黒シャツの腕が伸びて、指先が私の額に触れた。
触れられた場所が熱い。鼻先を掠めた甘いコロンの匂いにもドキドキする。いきなり何?動揺させないでよ。
「汗かいてるよ」
指で汗を拭うような気配がしてから、黒須の指先は離れた。
何でもない事のように触るんだ。妹だと思ってるからできちゃうんだよね。それとも誰にでもそうするの?
「睨まないでくれよ。せっかくの美人が台無しだ」
おどけたように黒須が笑った。
今日の私はいつもの量販店丸出しの半袖Tシャツで、ジーパンだし、メイクもしてないし、全然美人じゃない。なんでそういう事言うんだろう。
「美人じゃないし」
「その眼鏡は美人の顔には似合ってないな」
また黒須の手が伸びて、今度は眼鏡を取られた。
「ちょっと、何なの?」
「僕は素顔の春音の方がいいな。伊達眼鏡だろ?これ」
黒須が試すように私から取った黒縁眼鏡をかけた。
通った鼻筋にかかる眼鏡が悔しい程似合う。イケてない眼鏡も黒須が使うとお洒落アイテムになるんだ。
「やっぱり度が入ってないね」
「返して」
「やだ」
「か、返してよ」
「必要ないだろ。度が入ってないし」
「あるの」
「どうして?」
ドキドキし過ぎて黒須の顔が見られなくなるからなんて言えない。
眼鏡は透明な壁を作ってくれてたから二人きりでも何とか向き合えたのに。
直接、黒須を見るなんてキツイよ。そんな勇気今はない。
なんでいじめるのよ。黒須のバカ。
「私だってわかって声をかけたの?」
不思議だった。障子戸を開ける前からわかってたなんて。
「階段をのぼる足音がここの女将さんと違うし、障子の前で迷ったように立ってる気配もあったから、春音だとわかったんだよ」
タブレットから視線をあげ、黒須が微笑んだ。
いつもの黒須だ。余裕があってどこか私をバカにしたような感じで。
「突っ立ってないで座ったら?」
「うん」
テーブルを挟んだ斜め前に腰を下ろすと、興味深そうに黒須が視線を向けてくる。なんか見られていて恥ずかしい。
「私の顔、何かついてる?」
黒須が返事をするようにポットから冷えたほうじ茶をコップに注いで、スッと差し出した。
「喉がかわいたでしょ。走って来たから」
「なんでわかったの?」
黒い瞳が真っすぐこっちを向くと同時に黒シャツの腕が伸びて、指先が私の額に触れた。
触れられた場所が熱い。鼻先を掠めた甘いコロンの匂いにもドキドキする。いきなり何?動揺させないでよ。
「汗かいてるよ」
指で汗を拭うような気配がしてから、黒須の指先は離れた。
何でもない事のように触るんだ。妹だと思ってるからできちゃうんだよね。それとも誰にでもそうするの?
「睨まないでくれよ。せっかくの美人が台無しだ」
おどけたように黒須が笑った。
今日の私はいつもの量販店丸出しの半袖Tシャツで、ジーパンだし、メイクもしてないし、全然美人じゃない。なんでそういう事言うんだろう。
「美人じゃないし」
「その眼鏡は美人の顔には似合ってないな」
また黒須の手が伸びて、今度は眼鏡を取られた。
「ちょっと、何なの?」
「僕は素顔の春音の方がいいな。伊達眼鏡だろ?これ」
黒須が試すように私から取った黒縁眼鏡をかけた。
通った鼻筋にかかる眼鏡が悔しい程似合う。イケてない眼鏡も黒須が使うとお洒落アイテムになるんだ。
「やっぱり度が入ってないね」
「返して」
「やだ」
「か、返してよ」
「必要ないだろ。度が入ってないし」
「あるの」
「どうして?」
ドキドキし過ぎて黒須の顔が見られなくなるからなんて言えない。
眼鏡は透明な壁を作ってくれてたから二人きりでも何とか向き合えたのに。
直接、黒須を見るなんてキツイよ。そんな勇気今はない。
なんでいじめるのよ。黒須のバカ。