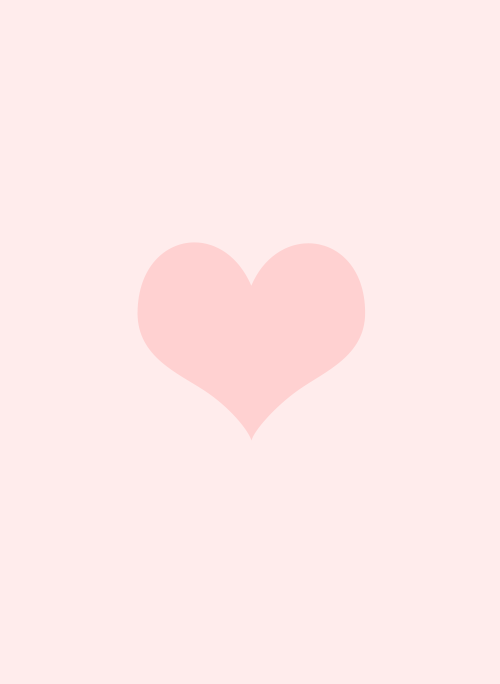からころ今なら飴をすぐに溶かせてしまいそうなほどによく回った舌。
「……回ったついでに、もうひとつだけ、言ってもいい?」
「この際だから、全部言ってくれたほうが僕も助かります」
本人に快諾してもらえたところで、寂しげに目を細めることはなくなった瞳を見て。
「……敬語は、わざわざ外そうとしなくても大丈夫だけど、……もし。もしも、敬語が取れちゃった時、氷昏の前では、訂正したり、取り繕わなくていいってことを、覚えていてくれると嬉しい」
どうか。どうか、氷昏の気持ちぐらいは、知っていてほしいと思った。
あの人は、あの義兄は、本当に。本気で、紫昏くんのことを大切に思っているのが、生活の至るところで表れていたから。
「紫昏くん自身も、ひとりでできるキッチンが張りつめたまんまなんて、やりにくいでしょ?」