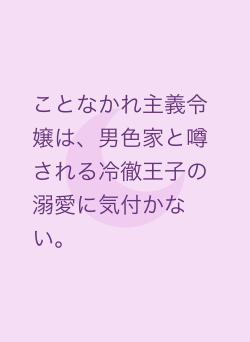安西さんにとっては私なんかその辺のモブで、ライバルになんてなるはずないのに。
こんなことしちゃうくらい藤君のことが好きなんだろうなって思ったら、彼女のことを嫌いになれない。
「…によ」
安西さんが、クシャッと顔を歪めた。
「私の方が絶対、つり合ってるんだから…っ!」
パッと上げられた手に、私は反射的に目を瞑った。
「相崎さん…っ!」
ーーこの声、藤君だ。
振り返るよりも先に、私の体がフワッと包まれた。
「相崎さんに乱暴すんな!」
「ふっ、ふじく…っ」
抱きしめられてる。そう理解するより先に、藤君の腕に力がこもった。
「ちょ、藤君なんで…っ」
安西さん、泣きそうな顔してる。
「サキは藤君が困ってると思ったから、ちょっと注意しただけだよ!」
「だって相崎さんと藤君全然つり合って…」
「そんなん勝手に決めんなよ!」
藤君が声を荒げる。いつも誰にでも同じ柔らかい態度なのに、こんなに怒ってるところ初めて見た。
「とにかく、これ以上相崎さんになにかしたら許さないから」
「藤君酷い…っ」
安西さんは長いまつ毛の大きい瞳に涙を溜めて、そのまま走り去っていく。他の子達も彼女を追いかけて、気がつくと私達以外には誰もいなくなってた。
「酷いのはどっちだよ、ホント」
藤君が、深いため息をついた。
「あ、あの」
「相崎さん、大丈夫だった?」
「それは大丈夫なんだけど、あの…えっと…」
未だに藤君の腕がしっかり回されてて、恥ずかし過ぎて言葉が上手く出てこない。
「あ、ご、ごめん!つい…っ」
藤君はハッとして、慌てて私から手を離した。
頬っぺたも耳も赤くなってる彼を見て、私の方が心臓爆発しそうだった。
こんなことしちゃうくらい藤君のことが好きなんだろうなって思ったら、彼女のことを嫌いになれない。
「…によ」
安西さんが、クシャッと顔を歪めた。
「私の方が絶対、つり合ってるんだから…っ!」
パッと上げられた手に、私は反射的に目を瞑った。
「相崎さん…っ!」
ーーこの声、藤君だ。
振り返るよりも先に、私の体がフワッと包まれた。
「相崎さんに乱暴すんな!」
「ふっ、ふじく…っ」
抱きしめられてる。そう理解するより先に、藤君の腕に力がこもった。
「ちょ、藤君なんで…っ」
安西さん、泣きそうな顔してる。
「サキは藤君が困ってると思ったから、ちょっと注意しただけだよ!」
「だって相崎さんと藤君全然つり合って…」
「そんなん勝手に決めんなよ!」
藤君が声を荒げる。いつも誰にでも同じ柔らかい態度なのに、こんなに怒ってるところ初めて見た。
「とにかく、これ以上相崎さんになにかしたら許さないから」
「藤君酷い…っ」
安西さんは長いまつ毛の大きい瞳に涙を溜めて、そのまま走り去っていく。他の子達も彼女を追いかけて、気がつくと私達以外には誰もいなくなってた。
「酷いのはどっちだよ、ホント」
藤君が、深いため息をついた。
「あ、あの」
「相崎さん、大丈夫だった?」
「それは大丈夫なんだけど、あの…えっと…」
未だに藤君の腕がしっかり回されてて、恥ずかし過ぎて言葉が上手く出てこない。
「あ、ご、ごめん!つい…っ」
藤君はハッとして、慌てて私から手を離した。
頬っぺたも耳も赤くなってる彼を見て、私の方が心臓爆発しそうだった。