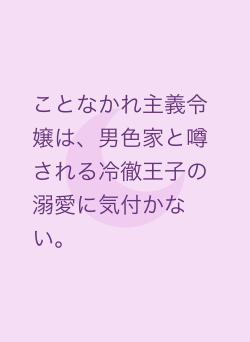この間の、藤君のことを思い出す。嫌われてるような感じはしなかったけど、私から告白されて喜ぶとも思えない。
「藤君、わざわざ小夏のこと追いかけてったし、案外まだ好きだったりして」
「そうかなぁ…違う気がする…」
「ていうかそこは小夏が気にすることじゃないって」
ズズッとバニラシェイクをストローで吸い込んだ華は、珍しく真面目な顔をした。
「さっき言ったでしょ?小夏に告白した人達も、いつかは違う彼女が出来るって。それは藤君もそうなんだからね?」
「藤君に、彼女…」
「むしろいない方がおかしいくらいだから」
華の言う通りだ。今の私は、藤君にとってただのクラスメイトの一人。明日藤君に彼女が出来たとしても、口を出せる権利はない。
私とは正反対の可愛い女の子が、藤君の隣を並んで歩く。幸せそうに笑う顔が浮かんで、心臓が握りつぶされたのかと思うくらいにズキズキと痛んだ。
「…藤君に彼女が出来ちゃうのは、嫌だ」
「だったら告白しなよ。ダメだったとしても、その時は堂々と次に行けるんだし」
「今から次のこと考えるのは無理だって…」
華と違って、私のポテトはまだ一本も減ってない。
「じゃあさ、ほら。告白フラグないの?」
「ええ、ないよそんなの…」
なんかだんだん華が楽しんでる気がする。
「人ごとだと思って…」
「だって完全に人ごとだし」
華は笑いながら、私の肩をぽんと叩いた。
「ま、あの小夏がリアルの恋が出来たってだけで私は嬉しいし」
「華ぁ…っ」
「はいはい。頑張れ小夏」
なんだかんだで、華が一番私のこと分かってくれる。
「藤君、わざわざ小夏のこと追いかけてったし、案外まだ好きだったりして」
「そうかなぁ…違う気がする…」
「ていうかそこは小夏が気にすることじゃないって」
ズズッとバニラシェイクをストローで吸い込んだ華は、珍しく真面目な顔をした。
「さっき言ったでしょ?小夏に告白した人達も、いつかは違う彼女が出来るって。それは藤君もそうなんだからね?」
「藤君に、彼女…」
「むしろいない方がおかしいくらいだから」
華の言う通りだ。今の私は、藤君にとってただのクラスメイトの一人。明日藤君に彼女が出来たとしても、口を出せる権利はない。
私とは正反対の可愛い女の子が、藤君の隣を並んで歩く。幸せそうに笑う顔が浮かんで、心臓が握りつぶされたのかと思うくらいにズキズキと痛んだ。
「…藤君に彼女が出来ちゃうのは、嫌だ」
「だったら告白しなよ。ダメだったとしても、その時は堂々と次に行けるんだし」
「今から次のこと考えるのは無理だって…」
華と違って、私のポテトはまだ一本も減ってない。
「じゃあさ、ほら。告白フラグないの?」
「ええ、ないよそんなの…」
なんかだんだん華が楽しんでる気がする。
「人ごとだと思って…」
「だって完全に人ごとだし」
華は笑いながら、私の肩をぽんと叩いた。
「ま、あの小夏がリアルの恋が出来たってだけで私は嬉しいし」
「華ぁ…っ」
「はいはい。頑張れ小夏」
なんだかんだで、華が一番私のこと分かってくれる。