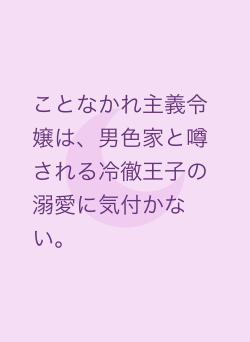藤君に気付かれないように、周りをチラチラと見渡す。手掴みの人もいるし、フォークとナイフの人も居る。
この中の誰か、今すぐ私にあつあつピザを可愛く食べる方法を教えて…!
「相崎さん?食べないの?」
「え?た、食べるよ?」
アハハと曖昧にごまかして、意を決してナイフとフォークを手にした。こうやって食べてる人もいるし、間違いではないよね?
丁寧に、音を立てないようにピザにナイフを入れる。一口大のサイズにしてパクッと食べると、フワッと広がる海鮮の風味とホワイトソースのクリーミーな感じがマッチして、凄くおいしい。
藤君を見れば、彼もフォークとナイフ。私と違うのは、それを使って器用にピザをくるくる巻いて、それを端から切って食べていることだ。
私は思わず藤君を凝視した。
「そうやって食べるものなんだ…」
「え?」
「い、いや。上手だなって」
間違ってたのかもしれないと、少し顔が熱くなる。
「あぁ、これ?母さんが昔イタリアに留学しててさ。イタリアではこうやって食べてたからって教えられたんだよね」
「イタリアに留学?藤君のお母さん、カッコいいね?」
「ありがと、でも別に活かされてないよ。アメリカとかでは手掴みらしいし、別にこの店も敷居高いわけじゃないから」
「そ、そうなんだ…」
「どう?おいしい?」
「うん、凄くおいしい!」
ニコッと笑うと、一瞬間が空いて藤君も同じように笑顔になる。
「よかった」
そういえば藤君、さっき「緊張してる」って言ってた。このお店もきっと、色々考えて決めてくれたんだろうな。
そう思うと、また胸が高鳴る。目の前のピザが、さっきよりももっと輝いて見えた。
「藤君」
「うん?」
「ホントにおいしいよ。ありがとう」
今まで私は、男子の目なんか気にしたことなかった。食べたいものを食べて、やりたいことをやって、それで幸せだった。
だけど今日は、自分のことより相手のことが気になって仕方なくて、少しでもよく見られたいと思う。
笑ってくれると嬉しくて、私まで心が満たされる。
一人より、二人。
もしかしたら「恋」ってそういうことの積み重ねのかもしれないって、ちょっとだけ理解できたような気がした。
この中の誰か、今すぐ私にあつあつピザを可愛く食べる方法を教えて…!
「相崎さん?食べないの?」
「え?た、食べるよ?」
アハハと曖昧にごまかして、意を決してナイフとフォークを手にした。こうやって食べてる人もいるし、間違いではないよね?
丁寧に、音を立てないようにピザにナイフを入れる。一口大のサイズにしてパクッと食べると、フワッと広がる海鮮の風味とホワイトソースのクリーミーな感じがマッチして、凄くおいしい。
藤君を見れば、彼もフォークとナイフ。私と違うのは、それを使って器用にピザをくるくる巻いて、それを端から切って食べていることだ。
私は思わず藤君を凝視した。
「そうやって食べるものなんだ…」
「え?」
「い、いや。上手だなって」
間違ってたのかもしれないと、少し顔が熱くなる。
「あぁ、これ?母さんが昔イタリアに留学しててさ。イタリアではこうやって食べてたからって教えられたんだよね」
「イタリアに留学?藤君のお母さん、カッコいいね?」
「ありがと、でも別に活かされてないよ。アメリカとかでは手掴みらしいし、別にこの店も敷居高いわけじゃないから」
「そ、そうなんだ…」
「どう?おいしい?」
「うん、凄くおいしい!」
ニコッと笑うと、一瞬間が空いて藤君も同じように笑顔になる。
「よかった」
そういえば藤君、さっき「緊張してる」って言ってた。このお店もきっと、色々考えて決めてくれたんだろうな。
そう思うと、また胸が高鳴る。目の前のピザが、さっきよりももっと輝いて見えた。
「藤君」
「うん?」
「ホントにおいしいよ。ありがとう」
今まで私は、男子の目なんか気にしたことなかった。食べたいものを食べて、やりたいことをやって、それで幸せだった。
だけど今日は、自分のことより相手のことが気になって仕方なくて、少しでもよく見られたいと思う。
笑ってくれると嬉しくて、私まで心が満たされる。
一人より、二人。
もしかしたら「恋」ってそういうことの積み重ねのかもしれないって、ちょっとだけ理解できたような気がした。