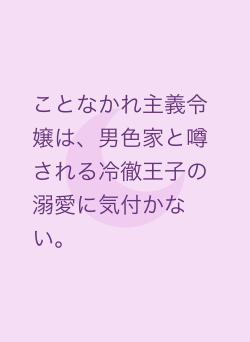思わず難しい顔になった私に、陽子さんは優しく問いかける。
「もしちゃんと告白されてたら、小夏ちゃんオーケーしてた?」
「してないです」
「あらら、即答」
「だって…」
藤君が嫌いとか、そういうことじゃない。ただ、私と藤君が付き合うなんて想像を、一ミリもしたことがない。
話しかけてくれるのは嬉しいし、仲良くなって友達にもなりたい。
でも、彼女となると話は別だ。私があの藤君の、彼女…つまりは恋人になるってこと。
どう考えても、つり合いが取れない。
「今度はシュンとしてる」
「陽子さん。私ね、彼氏が欲しい」
突然こんなこと言っても、陽子さんは笑わないで聞いてくれる。
「恋がしたいし、好きって言いたいし言われたい」
「うん」
「でも、その相手ってどうやって見つけるの?」
藤君と私の間に、フラグなんて立ってなかった。そもそも恋は、きっかけがなきゃきっと始まらない。
私達はただのクラスメイトで、恋愛イベントだって起こってないのに。
「陽子さんは、どうやってお父さんを恋の相手に選んだの?」
「うん?」
「こんなに美人で性格もいい陽子さんと、お父さんはどうして付き合おうと思ったんだろう。どう考えたってつり合ってないのに。分不相応だとか考えなかったのかな」
「こ、小夏ちゃん」
「あ、ごめんなさい変な言い方して」
陽子さんは少し考えるような仕草をした後、ジッと私を見つめた。
「小夏ちゃんが言う、そのつり合うつり合わないって、一体誰が決めてるの?」
「え?」
「あ、分かった。小夏ちゃん怖いんだね」
合点がいったように、陽子さんがパンと手を合わせた。
「もしちゃんと告白されてたら、小夏ちゃんオーケーしてた?」
「してないです」
「あらら、即答」
「だって…」
藤君が嫌いとか、そういうことじゃない。ただ、私と藤君が付き合うなんて想像を、一ミリもしたことがない。
話しかけてくれるのは嬉しいし、仲良くなって友達にもなりたい。
でも、彼女となると話は別だ。私があの藤君の、彼女…つまりは恋人になるってこと。
どう考えても、つり合いが取れない。
「今度はシュンとしてる」
「陽子さん。私ね、彼氏が欲しい」
突然こんなこと言っても、陽子さんは笑わないで聞いてくれる。
「恋がしたいし、好きって言いたいし言われたい」
「うん」
「でも、その相手ってどうやって見つけるの?」
藤君と私の間に、フラグなんて立ってなかった。そもそも恋は、きっかけがなきゃきっと始まらない。
私達はただのクラスメイトで、恋愛イベントだって起こってないのに。
「陽子さんは、どうやってお父さんを恋の相手に選んだの?」
「うん?」
「こんなに美人で性格もいい陽子さんと、お父さんはどうして付き合おうと思ったんだろう。どう考えたってつり合ってないのに。分不相応だとか考えなかったのかな」
「こ、小夏ちゃん」
「あ、ごめんなさい変な言い方して」
陽子さんは少し考えるような仕草をした後、ジッと私を見つめた。
「小夏ちゃんが言う、そのつり合うつり合わないって、一体誰が決めてるの?」
「え?」
「あ、分かった。小夏ちゃん怖いんだね」
合点がいったように、陽子さんがパンと手を合わせた。