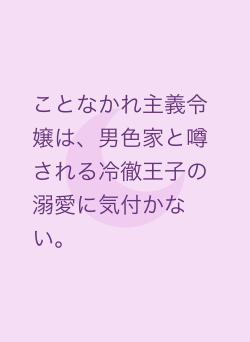「ご馳走様ー」
「ありがとうございましたー」
今日は土曜日。平日の夜は店長であるお父さんと、あと一人私か他のバイトの人が入る。だけど土曜と日曜は昼も夜もお客さんが増えるから、私とバイトの人が両方シフトに入るってのもよくあることで。
「お疲れ様でした、三苫さん」
「お疲れ、今日結構忙しかったね」
今日は、お父さんと三苫さんと私の三人で店を回した。三苫 理久さん、大学一年生の男の人でウチのバイト歴はもう一年になる。
「ラーメン食うだろ、理玖」
「いただきます」
「あ、私も食べる」
「へいへい」
お父さんは三苫さんと私の賄いを作りに、また厨房へと入っていった。
「小夏ちゃん、高校どう?」
三苫さんはいかにも大学生って感じで、余裕があってかっこいい。温和な雰囲気で他のバイトさんやお客さんからも慕われてるザ・いい人だ。
「それなりに楽しいです」
「部活とかは入ってないんだっけ」
「特には入ってないですね」
「偉いなぁ、小夏ちゃん。店の手伝いして」
「バイト代も出るし、好きでしてることだから。それに私、部活で汗流すほどのパッションもないですし」
「ハハッ。ホント小夏ちゃんって面白い」
何か最近、面白いってよく言われる気がするんだけど、なぜだ。可愛いでも優しいでもなく面白い、とは。
「あーでも、高校生になってから急に授業の難易度上がった気がしますね」
重度のバカってわけでもないけど、それなりに努力しないと当然テストは悲惨な結果になっちゃうわけで。
凄いいい点数じゃなくてもいいけど、悪い点数も嫌だ。
「来月初めに期末テストあるんですけど、全然自信なくて」
「俺でよかったら、教えようか?」
三苫さんが、穏やかに笑いながら私を見る。
「でも、迷惑じゃ」
「全然迷惑じゃないよ?まぁ、小夏ちゃんがよければだけど」
「いいじゃねぇか小夏、見てもらえよ」
賄いのラーメンをお盆に乗せて、お父さんが口を挟んだ。
「ありがとうございましたー」
今日は土曜日。平日の夜は店長であるお父さんと、あと一人私か他のバイトの人が入る。だけど土曜と日曜は昼も夜もお客さんが増えるから、私とバイトの人が両方シフトに入るってのもよくあることで。
「お疲れ様でした、三苫さん」
「お疲れ、今日結構忙しかったね」
今日は、お父さんと三苫さんと私の三人で店を回した。三苫 理久さん、大学一年生の男の人でウチのバイト歴はもう一年になる。
「ラーメン食うだろ、理玖」
「いただきます」
「あ、私も食べる」
「へいへい」
お父さんは三苫さんと私の賄いを作りに、また厨房へと入っていった。
「小夏ちゃん、高校どう?」
三苫さんはいかにも大学生って感じで、余裕があってかっこいい。温和な雰囲気で他のバイトさんやお客さんからも慕われてるザ・いい人だ。
「それなりに楽しいです」
「部活とかは入ってないんだっけ」
「特には入ってないですね」
「偉いなぁ、小夏ちゃん。店の手伝いして」
「バイト代も出るし、好きでしてることだから。それに私、部活で汗流すほどのパッションもないですし」
「ハハッ。ホント小夏ちゃんって面白い」
何か最近、面白いってよく言われる気がするんだけど、なぜだ。可愛いでも優しいでもなく面白い、とは。
「あーでも、高校生になってから急に授業の難易度上がった気がしますね」
重度のバカってわけでもないけど、それなりに努力しないと当然テストは悲惨な結果になっちゃうわけで。
凄いいい点数じゃなくてもいいけど、悪い点数も嫌だ。
「来月初めに期末テストあるんですけど、全然自信なくて」
「俺でよかったら、教えようか?」
三苫さんが、穏やかに笑いながら私を見る。
「でも、迷惑じゃ」
「全然迷惑じゃないよ?まぁ、小夏ちゃんがよければだけど」
「いいじゃねぇか小夏、見てもらえよ」
賄いのラーメンをお盆に乗せて、お父さんが口を挟んだ。