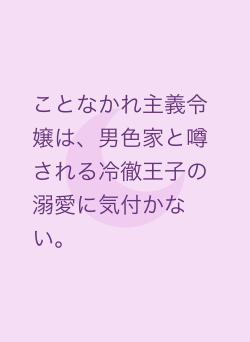♢♢♢
藤君と付き合って、もう一ヶ月が経った。すっかり夏はどこかに消えて、地面には赤や黄色の葉っぱが落ちてる。
「映画、よかったね」
「うん!最後ジーンとしちゃった」
付き合って初めての休日デート。私達はしっかりと手を繋いで、さっき見た映画の感想を言い合う。
手を繋ぐって最初はソワソワして落ち着かなかったけど、一ヶ月経った今でもやっぱりまだ落ち着かない。
「小夏ちゃん、お腹空いた?」
「そうだね、ちょっと空いたかも」
いつの間にか小夏ちゃん呼びに変わり、その度に私は心臓をときめかせてる。
この名前が、なんだか凄く特別に感じる。
「藤君は?」
ちなみに私は、未だに「諒太郎君」って呼べないチキンです。
「俺も空いた。夕飯時だしちょうどいいかもね」
「じゃあ、どっかお店入ろっか」
そう口にした私に、藤君が意外な提案をした。
「小夏ちゃんちのラーメン屋、行ってみたい」
「えっ、ウチ!?」
「ダメ?」
ダメじゃないけど、デートでチョイスする店ではない。
でも、藤君が言ってくれたのはちょっと嬉しい。それにその、遊んでほしそうな大型犬みたいな表情されたら、たとえば今すぐ逆立ちしろって言われても断れない気がする。
「藤君がいいなら、いいよ」
「やった」
そう言って笑う藤君には夕日さえ味方して、彼の後ろでキラキラ光ってた。
「いらっしゃ…ってなんだお前か」
「なんだとはなによ。ヒマそうだね」
「余計なお世話だよ…って、ああ!」
ドアを開けると、チリンチリンと鈴の音がした。お父さんは藤君に気づいた瞬間、目をまん丸にした。
「同じクラスの藤諒太郎君」
「初めまして、藤と言います。小夏さんとお付き合いさせていただいてます」
「お、おお…どうもどうもご丁寧に」
藤君と付き合うことになった時、私はすぐ陽子さんに報告した。
そのついでで、お父さんにもサラッと言っておいた。
藤君と付き合って、もう一ヶ月が経った。すっかり夏はどこかに消えて、地面には赤や黄色の葉っぱが落ちてる。
「映画、よかったね」
「うん!最後ジーンとしちゃった」
付き合って初めての休日デート。私達はしっかりと手を繋いで、さっき見た映画の感想を言い合う。
手を繋ぐって最初はソワソワして落ち着かなかったけど、一ヶ月経った今でもやっぱりまだ落ち着かない。
「小夏ちゃん、お腹空いた?」
「そうだね、ちょっと空いたかも」
いつの間にか小夏ちゃん呼びに変わり、その度に私は心臓をときめかせてる。
この名前が、なんだか凄く特別に感じる。
「藤君は?」
ちなみに私は、未だに「諒太郎君」って呼べないチキンです。
「俺も空いた。夕飯時だしちょうどいいかもね」
「じゃあ、どっかお店入ろっか」
そう口にした私に、藤君が意外な提案をした。
「小夏ちゃんちのラーメン屋、行ってみたい」
「えっ、ウチ!?」
「ダメ?」
ダメじゃないけど、デートでチョイスする店ではない。
でも、藤君が言ってくれたのはちょっと嬉しい。それにその、遊んでほしそうな大型犬みたいな表情されたら、たとえば今すぐ逆立ちしろって言われても断れない気がする。
「藤君がいいなら、いいよ」
「やった」
そう言って笑う藤君には夕日さえ味方して、彼の後ろでキラキラ光ってた。
「いらっしゃ…ってなんだお前か」
「なんだとはなによ。ヒマそうだね」
「余計なお世話だよ…って、ああ!」
ドアを開けると、チリンチリンと鈴の音がした。お父さんは藤君に気づいた瞬間、目をまん丸にした。
「同じクラスの藤諒太郎君」
「初めまして、藤と言います。小夏さんとお付き合いさせていただいてます」
「お、おお…どうもどうもご丁寧に」
藤君と付き合うことになった時、私はすぐ陽子さんに報告した。
そのついでで、お父さんにもサラッと言っておいた。