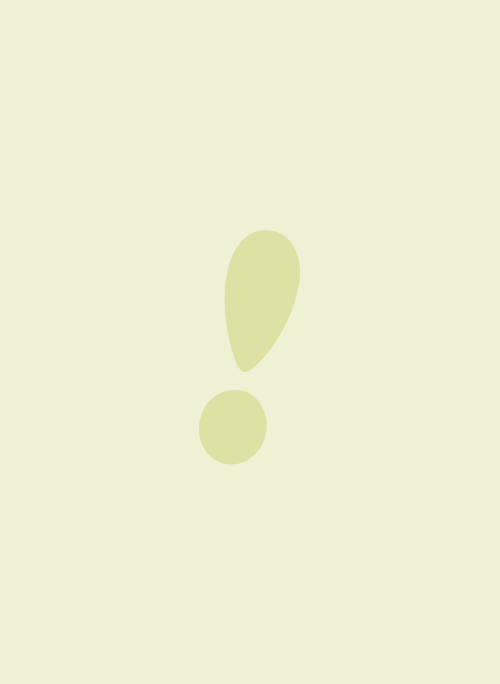婚約者が戦地で働く最中、志津も気丈に日々の仕事をこなしながら過ごしていたが、乙酉の年が近づくにつれて、これまでのように仕事に齷齪するだけでは話にならない日々が始まった。
昨年の暮れには本土への空襲が始まり、区部の中でも東側を中心にその被害は激化している。そしてその流れはいつ西部に来てもおかしくないという状況が続いているのだ。
この頃には二年間の任期を終えた康弘も東京に戻り病院での仕事を再開していたが、やはり二人は会うことすらなく、淡々と、あるいは恐々として目前の業務に努めている。
この正月はおよそ三年越しに志津と康弘、その両家が一堂に会した。
高田家は父と娘の二人は一月三日の午後に高辻家の邸宅を訪ねる。
「どうも、こんちは」
つい昨日一昨日も帝都の空を敵機が襲ったのでは新年を祝う言葉も出せず、志津はこわごわ会釈をするほかなかった。
高辻家には隠居した夫妻と、「高辻醫院」の内科担当で院長である兄夫婦とその二人の子供、そして同じく病院の小児科担当の副院長の康弘という、父と娘の二人暮らしの高田家からしてみると大変賑やかな家庭である。
しかし、育ち盛りの五歳と三歳になる兄夫婦の姉弟もこの日ばかりは燥ぐ様子などは一切見えず、黙って座っていた。
洋館の中央にある食堂にはすでに餅と少しの野菜の入った雑煮と、黒豆や膾、煮染めなどごく少量の料理が置かれている。
「志津や、康弘くんの隣に行きなさい」
父は自らの隣に座ろうとしていた志津に耳打ちする。
昨年の暮れには本土への空襲が始まり、区部の中でも東側を中心にその被害は激化している。そしてその流れはいつ西部に来てもおかしくないという状況が続いているのだ。
この頃には二年間の任期を終えた康弘も東京に戻り病院での仕事を再開していたが、やはり二人は会うことすらなく、淡々と、あるいは恐々として目前の業務に努めている。
この正月はおよそ三年越しに志津と康弘、その両家が一堂に会した。
高田家は父と娘の二人は一月三日の午後に高辻家の邸宅を訪ねる。
「どうも、こんちは」
つい昨日一昨日も帝都の空を敵機が襲ったのでは新年を祝う言葉も出せず、志津はこわごわ会釈をするほかなかった。
高辻家には隠居した夫妻と、「高辻醫院」の内科担当で院長である兄夫婦とその二人の子供、そして同じく病院の小児科担当の副院長の康弘という、父と娘の二人暮らしの高田家からしてみると大変賑やかな家庭である。
しかし、育ち盛りの五歳と三歳になる兄夫婦の姉弟もこの日ばかりは燥ぐ様子などは一切見えず、黙って座っていた。
洋館の中央にある食堂にはすでに餅と少しの野菜の入った雑煮と、黒豆や膾、煮染めなどごく少量の料理が置かれている。
「志津や、康弘くんの隣に行きなさい」
父は自らの隣に座ろうとしていた志津に耳打ちする。