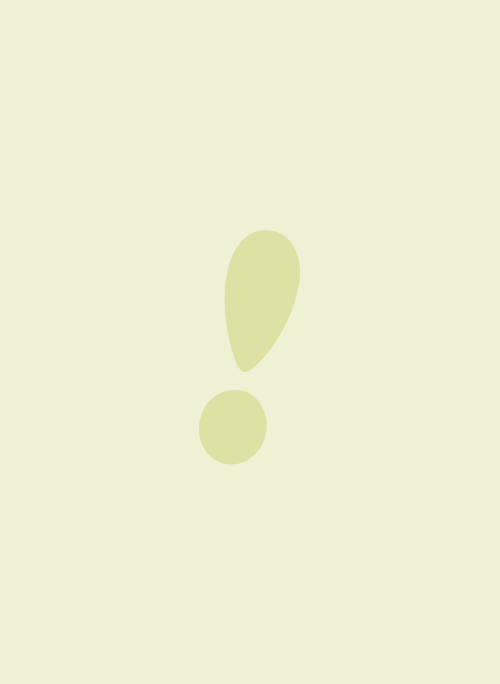世の中は急速に戦時色が強くなり、遂には学生までもが召集される事態となった。街から若者の姿は消え、彩に欠けた景色がそこには広がっている。
志津は暫くあの書店での出来事は忘れていたが、ある秋の夕刊を読んでいてハッとした。
『もとより生還期せず』
そんな中見出しが見えた。
その時、とうに過ぎて憧憬と化したあの日が反射的に思い出されたのである。
彼は帝大の法科生だと言っていた。きっと彼も召集免除を解除されたに違いない。
彼もこの雨の中の競技場を行進し、そして兵隊になるのだろうか。
いや、しかしあの人は帝大の学生だ。きっと士官にでもなって、寧ろ立派な軍人になるだろう。
学問に熱心で物腰も良く、さらには優秀な士官にまでなるのかと考えると、やはり「真の幸福」の存在が目の前をちらつく。
それから約半年の間、志津の頭の中には常にあの思い出の帝大生が居た。
夢見心地になることもしばしばといった調子ながらも普段のように病院で仕事をしていると、ある日、いつもこの病院にかかっている婦人がやってきて、
「ねえ、これに写っているの、志津ちゃんよね」
と処方薬と入れ替わるように一枚の写真を差し出した。
「これは……」
写真に収められていたのは、窓越しに撮られた互いにはにかむ男女の姿である。
立ち並ぶ書架の片隅で本を手に取る美男子と、優美な帯の着物に桃の花の髪飾りの女が微笑んでいた。
「知り合いが出征前に一日だけ小さな個展を開いたのよ、それで観に行くとこの写真が有って……」
志津は何も言えなかった。何と言うべきか、考える頭が働かない。
志津は暫くあの書店での出来事は忘れていたが、ある秋の夕刊を読んでいてハッとした。
『もとより生還期せず』
そんな中見出しが見えた。
その時、とうに過ぎて憧憬と化したあの日が反射的に思い出されたのである。
彼は帝大の法科生だと言っていた。きっと彼も召集免除を解除されたに違いない。
彼もこの雨の中の競技場を行進し、そして兵隊になるのだろうか。
いや、しかしあの人は帝大の学生だ。きっと士官にでもなって、寧ろ立派な軍人になるだろう。
学問に熱心で物腰も良く、さらには優秀な士官にまでなるのかと考えると、やはり「真の幸福」の存在が目の前をちらつく。
それから約半年の間、志津の頭の中には常にあの思い出の帝大生が居た。
夢見心地になることもしばしばといった調子ながらも普段のように病院で仕事をしていると、ある日、いつもこの病院にかかっている婦人がやってきて、
「ねえ、これに写っているの、志津ちゃんよね」
と処方薬と入れ替わるように一枚の写真を差し出した。
「これは……」
写真に収められていたのは、窓越しに撮られた互いにはにかむ男女の姿である。
立ち並ぶ書架の片隅で本を手に取る美男子と、優美な帯の着物に桃の花の髪飾りの女が微笑んでいた。
「知り合いが出征前に一日だけ小さな個展を開いたのよ、それで観に行くとこの写真が有って……」
志津は何も言えなかった。何と言うべきか、考える頭が働かない。