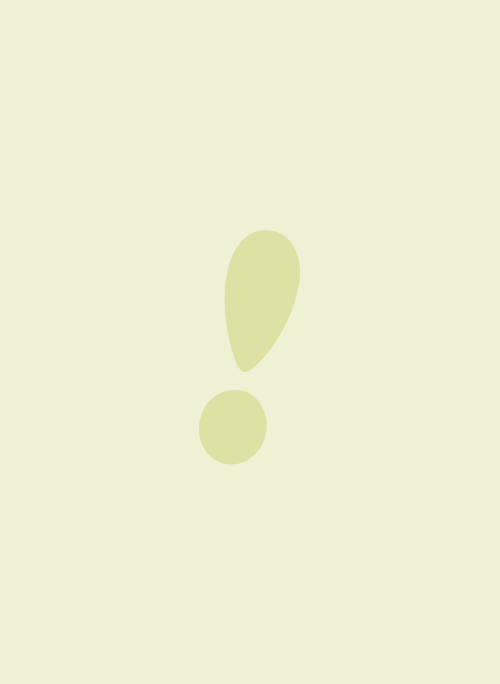志津は、生まれてからずっと、牛込の一角にある小さな診療所の隣の家で生活してきた。幼い頃は、患者が少なければ看護婦達が面倒を見てきた。
志津が薬学を学び薬剤師となった日から、彼女も父と共に家の隣の病院─「高田内科醫院」─へ出勤し、働き、日が暮れる頃になると宿直を残してすぐ隣の家に帰宅する。
この街は学生が多く、駅の付近は栄えていながら、山の手の気風の流れる場所である。
牛込に生れたことは幸いだ──彼女はそう思っている。
田舎でもなく大都会でもないが、慌ただしくせかせかした様子もなく、悠々としている。その地風は彼女そのものを表象しているようでもある。
病院で働いていれば、おもしろいことはいくらでもある。
ある日は持病で定期的に通っている老女がやってきて、
「志津ちゃんは今日も可愛らしいねえ。あんまり気張らず、頑張るんだよ」
と声を掛けてくれる。
たとい患者であるとも、労いの声を貰うことは嬉しいことである。
またある日は、小さな子どもが泣きながら病院の前に立っている。
戸を開けると、擦り剥いたか膝から血を流しながら棒立ちになって泣き声を上げる小学生が居る。
「僕、どうしたの?」
「向こうで遊んでたら転んだんだ。痛いよう、痛いよう」
「まあ、お入んなさいな」
志津は少年を病院の中に招き入れ、
「此処で待っているのよ、今、手当をしますからね」
と言って受付から救急箱を取って来る。
「痛いよう」
「少しの辛抱よ……はい、出来た」
「お姉ちゃん、有難う!」
少年は病院を飛び出て走っていく。
「お大事に」
こんな衛生室のような一幕もあるのだ。
志津が薬学を学び薬剤師となった日から、彼女も父と共に家の隣の病院─「高田内科醫院」─へ出勤し、働き、日が暮れる頃になると宿直を残してすぐ隣の家に帰宅する。
この街は学生が多く、駅の付近は栄えていながら、山の手の気風の流れる場所である。
牛込に生れたことは幸いだ──彼女はそう思っている。
田舎でもなく大都会でもないが、慌ただしくせかせかした様子もなく、悠々としている。その地風は彼女そのものを表象しているようでもある。
病院で働いていれば、おもしろいことはいくらでもある。
ある日は持病で定期的に通っている老女がやってきて、
「志津ちゃんは今日も可愛らしいねえ。あんまり気張らず、頑張るんだよ」
と声を掛けてくれる。
たとい患者であるとも、労いの声を貰うことは嬉しいことである。
またある日は、小さな子どもが泣きながら病院の前に立っている。
戸を開けると、擦り剥いたか膝から血を流しながら棒立ちになって泣き声を上げる小学生が居る。
「僕、どうしたの?」
「向こうで遊んでたら転んだんだ。痛いよう、痛いよう」
「まあ、お入んなさいな」
志津は少年を病院の中に招き入れ、
「此処で待っているのよ、今、手当をしますからね」
と言って受付から救急箱を取って来る。
「痛いよう」
「少しの辛抱よ……はい、出来た」
「お姉ちゃん、有難う!」
少年は病院を飛び出て走っていく。
「お大事に」
こんな衛生室のような一幕もあるのだ。