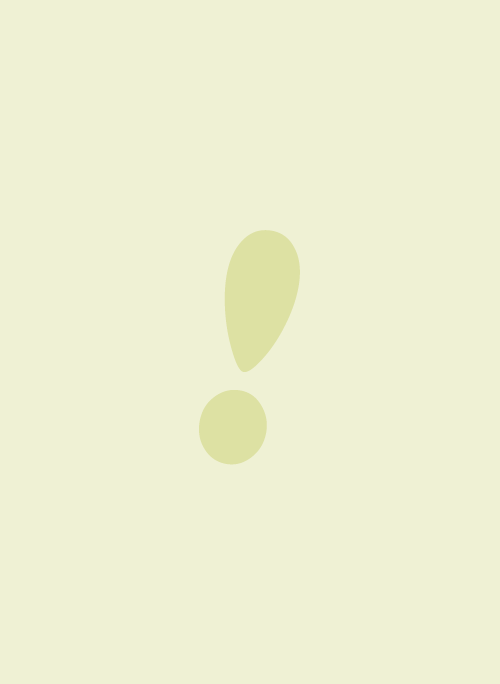幸枝は年の瀬を直前にして山梨へ疎開することになった。その委細を聞いたのは、出陣学徒壮行会からひと月ほど経った頃であった。
いつもの「仕事」を終えた長津は、幸枝に地図と住所を書いた紙を手渡した。
「切符は当日渡すよ。向こうには留守居が居るから、身の回りのことは全て任せてくれて構わない。仕事のことは代表と話し合ったかい」
幸枝はこくりと頷く。やはり東京に居ないのでは出来る仕事も無いのだが、時々父が手紙を出すそうで、その内容に返事するくらいの仕事しかないのであった。結局この「仕事」は父が我が子の次に信頼しているという社員が引き継ぐことになったらしく、父も苦渋の決断の様子であったが、第一、父も父で、折角だから休みなさいと今回の山梨行きを疎開どころか長期休暇のように扱っている節があるように見えた。
「主計中佐はご存知なんです?」
「ああ、知っているよ」
長津は事もなげにそう言う。実際には幸枝の疎開のことは話していない。
主計中佐にこの件を話した場合の反応は大凡予想できる。
分厚い眼鏡越しにあの毒々しい視線を向け、煙草を燻らせながら唸るように話すだろう。
「絶対に間違いを起こすなと言った筈だな」
「あの娘が居なければ話にならないじゃないか」
「公私の区別も付かないとは、君も一介の将校に成り下がったな」
こんな調子であろうか。
「君は何も心配することない」
そうして荷物を纏めたトランクを一つ抱え、東京の街を去ろうとしているのである。
いつもの「仕事」を終えた長津は、幸枝に地図と住所を書いた紙を手渡した。
「切符は当日渡すよ。向こうには留守居が居るから、身の回りのことは全て任せてくれて構わない。仕事のことは代表と話し合ったかい」
幸枝はこくりと頷く。やはり東京に居ないのでは出来る仕事も無いのだが、時々父が手紙を出すそうで、その内容に返事するくらいの仕事しかないのであった。結局この「仕事」は父が我が子の次に信頼しているという社員が引き継ぐことになったらしく、父も苦渋の決断の様子であったが、第一、父も父で、折角だから休みなさいと今回の山梨行きを疎開どころか長期休暇のように扱っている節があるように見えた。
「主計中佐はご存知なんです?」
「ああ、知っているよ」
長津は事もなげにそう言う。実際には幸枝の疎開のことは話していない。
主計中佐にこの件を話した場合の反応は大凡予想できる。
分厚い眼鏡越しにあの毒々しい視線を向け、煙草を燻らせながら唸るように話すだろう。
「絶対に間違いを起こすなと言った筈だな」
「あの娘が居なければ話にならないじゃないか」
「公私の区別も付かないとは、君も一介の将校に成り下がったな」
こんな調子であろうか。
「君は何も心配することない」
そうして荷物を纏めたトランクを一つ抱え、東京の街を去ろうとしているのである。