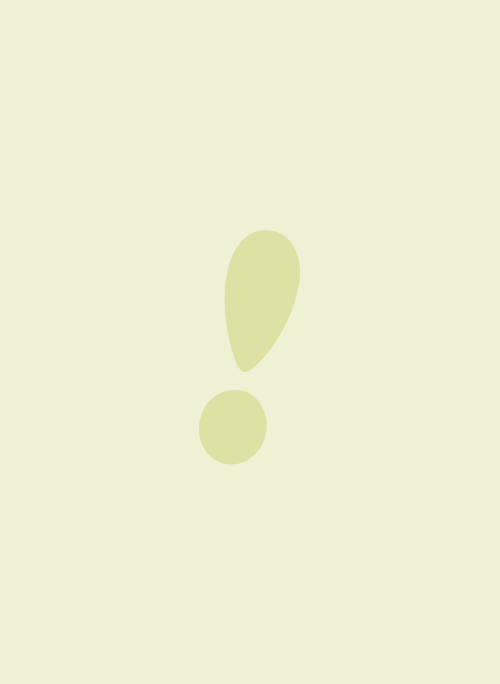冷たい秋雨の降り頻る朝、幸枝はもやもやとした気分で目が覚めた。
数日前から、清士の放った言葉が頭から離れない。寝ても覚めても、脳裏であの落胆したような、全てを諦めた声が繰り返し囁いてくるのである。
戦況が厳しいことは十分理解しているし、最早勝ち目がないことも薄々気が付いてはいる。一方で、突如として戦地に赴かなければならなくなった学生の気持も多少は分かる。それでも、やはり彼は分かっていない、そう思うのだ。
(嫌だわ、このままお別れなんて)
曲がりなりにも「友」として接して来た人間に対して、この悶々とした気持を抱えたまま別れることになるのは決して良い気分ではない。
──伊坂家の食卓はこれまで以上に静かだ。
誰も何も話さず、ただ食物を口に運び、咀嚼して飲み込むだけの作業である。
微かな音量で流れるラジオが戦局やら軍人の話やらを放送しているのみで、朝食を食べながらも、幸枝はやはり清士のことを考えていた。
「……今日って何日だっけ」
「二十一日」
兄がそう答えると、幸枝は勢い良くその場を立った。
「何処に行くんだよ」
「四谷へ」
幸枝は食堂を走り抜けて自室に戻る。
(もう今日しかない……あと数時間しかないんだもの)
クローゼットの奥から一番のお気に入りの服を引っ張り出して着替える。
クリーム色のツイードに二本の紺の線の入ったジャケットを羽織って、同じ色のスカートを履いて机の引き出しで眠っていたアクセサリーを着ける。そして玄関に降り、靴箱の奥で長い間眠っていた、爪先の黒く塗られた駱駝色のパンプスを履いて家を飛び出した。
数日前から、清士の放った言葉が頭から離れない。寝ても覚めても、脳裏であの落胆したような、全てを諦めた声が繰り返し囁いてくるのである。
戦況が厳しいことは十分理解しているし、最早勝ち目がないことも薄々気が付いてはいる。一方で、突如として戦地に赴かなければならなくなった学生の気持も多少は分かる。それでも、やはり彼は分かっていない、そう思うのだ。
(嫌だわ、このままお別れなんて)
曲がりなりにも「友」として接して来た人間に対して、この悶々とした気持を抱えたまま別れることになるのは決して良い気分ではない。
──伊坂家の食卓はこれまで以上に静かだ。
誰も何も話さず、ただ食物を口に運び、咀嚼して飲み込むだけの作業である。
微かな音量で流れるラジオが戦局やら軍人の話やらを放送しているのみで、朝食を食べながらも、幸枝はやはり清士のことを考えていた。
「……今日って何日だっけ」
「二十一日」
兄がそう答えると、幸枝は勢い良くその場を立った。
「何処に行くんだよ」
「四谷へ」
幸枝は食堂を走り抜けて自室に戻る。
(もう今日しかない……あと数時間しかないんだもの)
クローゼットの奥から一番のお気に入りの服を引っ張り出して着替える。
クリーム色のツイードに二本の紺の線の入ったジャケットを羽織って、同じ色のスカートを履いて机の引き出しで眠っていたアクセサリーを着ける。そして玄関に降り、靴箱の奥で長い間眠っていた、爪先の黒く塗られた駱駝色のパンプスを履いて家を飛び出した。